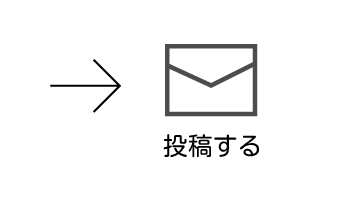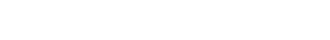マイノリティの歴史について、領域を超えて学べますか?
質問
LGBTに興味を持ったことがきっかけで、マイノリティの歴史について研究したいと思っています。日本史や西洋史、東洋史や時代を越えて学びたいと思っています。このようなことは、文学部史学科で出来ることでしょうか?
回答
領域を超えていろいろな授業をとることは可能で、上智の史学科ではむしろそうしなければならない制度になっています。とくに1年生の「〇〇史概説」は領域を超えて履修しなければなりません。また、上級生になっても、領域に関係なく講義は受講できます。領域を超えた問題関心はいつも持っておくべきことです。
ただし、マイノリティといってもいろいろな種類のものがあり、それぞれの条件や性質は異なります。抽象的にマイノリティを論じても歴史学ではあまり意味がありません。歴史学は個別事例を詳しく調査して過去の事実を解明し、そこから現在や未来の問題を考えるものだからです。抽象的なマイノリティ論ではなく、具体的な「〇〇人」や「▽▽者」を深く研究し、それをレポートや論文にします。したがって、上級生になるにつれて、自分の専攻する地域や時代の個別事例に特化していくことになります。しかし、領域を超えた問題関心を持っていれば、そこから現在や未来の問題にひきつけて考えられるようになると思います。