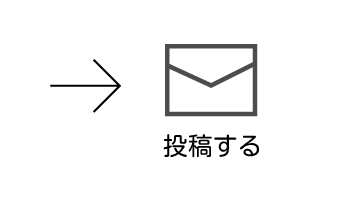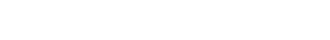大学院でも、学芸員や図書館司書の資格が取れますか?
質問
大学院でも、学芸員の資格や図書館司書の資格が取れますか?
回答
お問い合わせありがとうございます。
学芸員課程については、大学院在籍中でも、学部生と同じ授業を履修し、資格を取得することが可能です。しかしその場合は、年度初めの決められた時期に課程センターへ申し込み、「科目等履修生」として課程履修を許可される必要があります。詳しくはこちらから、募集要項を確認してください。
また本学以外でも、科目等履修生として、例えば7月末〜9月中旬などの集中講義で、学芸員資格を取得できる大学があります。必要に応じ、情報を収集してみてください。
なお、司書資格については、本学では取得できません。