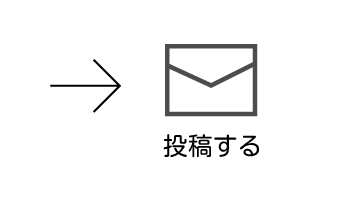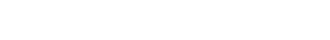世界大戦期、戦後日本も含めた世界の動向を研究できますか?
質問
世界大戦時や戦後の日本も含めた世界の動向について広く研究することはできますか?
回答
ご返事が遅くなり申し訳ありません。
現在、当史学科では、アジア・日本史系に長田彰文教授、笹川裕史教授、ヨーロッパ・アメリカ史系に井上茂子教授がおり、近現代史の研究・教育に従事しています。
長田教授は、戦前・戦中期を対象に、中国・朝鮮半島・日本・アメリカをめぐる国際政治史を研究しています。
笹川教授は、民国〜戦中期の中国社会史が専門で、近年は政治体制と中国社会との関係について論及しています。
井上教授は、ナチス期のドイツ近現代政治史が専門で、ナチスの諸政策やホロコーストの問題、現代ドイツの歴史認識などを研究しています。
ほかにも、総合グローバル学部や外国語学部などで、近現代史を扱う授業はさまざまに開講されています。
これらの教員に指導を受けつつ、他学部他学科の授業も参照し、希望の研究テーマを深めてゆくことは可能です。