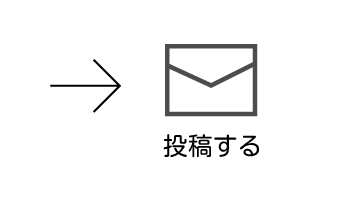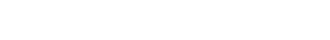第二次大戦の日本の戦争について学べますか?
質問
第二次世界大戦における日本の戦法、武器、生活や他にもあらゆる戦争について深く学びたいと考えております。戦争史などは学べるのでしょうか?
回答
質問ありがとうございます。
まず、どんな質問にも最初にお答えしていることですが、基本的に大学は自分の問題意識に基づき、研究を進展させてゆくところです。
指導教員は、可能な限り皆さんの関心をより専門的に育てるような形でアドバイスしてゆきますので、頭ごなしに否定をすることはありません。
あとは、教員の専門研究の性質によって、指導のあり方が変わってくることはありえますが、学生の皆さんの多様な興味に対応できるような教員を配していますので、概ね問題はなかろうと思います。
戦争は、日本史・東洋史・西洋史といった分野、古代から現代に至る時代を問わず、政治・経済・社会、および地球環境にも多大な影響を及ぼすファクターです。よってどの教員も、それぞれの専門領域における「戦争」について、講義や演習でそれなりに扱っており、毎年の卒業論文でも、テーマとする学生は少なくありません。日本史に限ってみても、古代史の北條勝貴教授には日中の兵法の比較に関する論考がありますし、中世史の中澤克昭教授は城郭史や武力の歴史が専門です。
そして、日本近現代史の長田彰文教授は、東アジア国際関係史が専攻ですが、日本の近代戦時代の政治・外交に関する多くの論著を公刊されています。
戦争に関して、さまざまな面からアプローチすることは可能と思います。