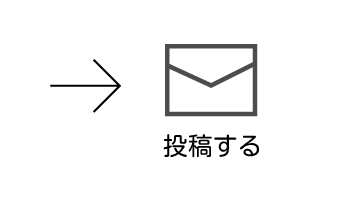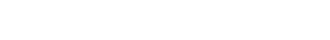ローマ帝国時代の地中海の島々を研究できますか?
質問
上智大学史学科の受験を考えている高校3年生です。
ローマ帝国時代の地中海の島々(特にシチリア島など)について研究したいのですが可能でしょうか?
回答
お問い合わせ、ありがとうございます。
「ローマ帝国時代の地中海の島々(特にシチリア島など)」を研究されたいとのこと、ローマの属州となったシチリアやサルデーニャ、コルシカなどの島々についてということでしょうか。日本ではあまり研究がないですし、卒業論文のテーマとしては少し難しいかもしれませんが、可能です。
「ローマ帝国時代」とは、アウグストゥス以降のいわゆる帝政期のことだと思いますが、それよりも前、共和政期の属州シチリアについては以下の本があります。
・吉村忠典『古代ローマ帝国ーその支配の実像ー』岩波新書、1997年
共和政期の属州シチリアについてならば、邦訳のある史料を使えますので、研究しやすくなります。
地中海の島々は、様々な人々が交流する場となってきました。その様相について学ぶことで、多様でありながらも共通するものが見られる、現代の地中海世界についての理解も深まることでしょう。