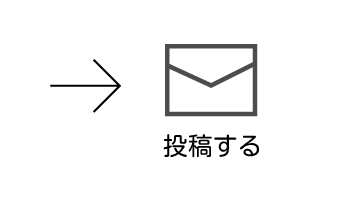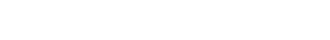史学科で文化人類学や民俗学は学べますか?
質問
貴学科のカリキュラムについてお伺いしたく、ご連絡差し上げます。
史学科では、日本史や世界史を中心とした学問分野のほかに、文化人類学や民俗学のような領域についても学ぶことは可能でしょうか。
回答
上智大学史学科のQ&Aへのご投稿をありがとうございます。
史学科のカリキュラムに関する質問ですね。上智の史学科で文化人類学や民俗学が学べるかということですが、文化人類学は史学科の正規の授業としてございます。民俗学そのものは授業としてはありませんが、北條勝貴先生(日本古代史)のように民俗学の手法を取り入れた先生がいますので、そのもとで学ぶことは可能です。
ただし、あくまで歴史学の学生向けの補助学問という位置付けです。文化人類学や民俗学を主として学びたい場合は、上智の他の学部や他大学を検討された方がいいでしょう。
では頑張ってください。
人々の生活や文化(特に食文化)に興味があるのですが…
質問
人々の生活や文化(特に食文化)に興味があるのですが、貴学科でこのようなことを学べますでしょうか?
回答
上智大学史学科情報サイトへのご質問、ありがとうございます。
質問者さんは、生活に根ざしたテーマに関心があるようですね。とりあえず「食文化」に絞ってお答えします。いうまでもなく、食文化は人間の生活の基本的なものであり、歴史学においても重要なテーマの一つといえます。本学には各時代・地域について幅広い見識をもつ教員がおりますので、もちろん専攻することは可能です。
ただ、一つ注意していただきたいのは、食文化について歴史学ならではの視点や方法が存在するということです。「過去の人々がどんなものを食べていたのか知りたい」というのは、研究の出発点としては大切な動機です。しかし、食材や調理法の解明は基礎的な作業ではあるものの、歴史学における研究のゴールにはなり得ません。
むしろ、食が当時の人々や社会にとってどういった位置付けや機能をもっていたのか、という論点が歴史学にふさわしいものです。具体的には宗教・政治における儀礼的な側面などが挙げられるでしょう。また、食文化を専攻するためには、該当する地域・時代について広く知ることが必要となります。
それでは頑張ってください。
追記:過去に類似の質問と回答がありますので、よろしかったらそちらもご参照ください。
レコンキスタ前後のスペイン史を学びたいのですが…
質問
私は中世~近世にかけての西洋史(西欧州メイン)を学びたいと思っているのですが、二つ質問があります。
1)レコンキスタ前後のスペイン、或いは大英帝国最盛期は専門的に学ぶことは可能でしょうか
2)上記の内容、特にレコンキスタ前後のスペイン史において、キリスト教と組み合わせながら学んでいきたいと思っているのですが、可能でしょうか。
回答
お問い合わせありがとうございました。
レコンキスタ前後のスペインの歴史について学べるかとのお尋ねですが、本学科にこの主題を専門とする教員はおりませんが、卒業論文作成のための研究を指導することは可能です。
レコンキスタ自体は長期にわたる運動ですので、どの時代に着目するのかは検討する必要がありますが、西洋中世史のゼミナール、もしくは西洋近世史のゼミナールに所属して、卒業論文を作成することはできます。これまでも、両ゼミナールで、この主題で卒業論文を提出して卒業した学生は複数おります。また、本学科の上に位置付けられる大学院の史学専攻には、この主題を専攻する院生が在籍していますので、アドバイスを受けることもできます。
また、本学には、外国語学部イスパニア語学科にスペイン近世史を専門とするスタッフもおり、神学部では「キリスト教の歴史」をはじめキリスト教史関連の授業も開講しておりますので、それらを組み合わせて履修していただければ、ご関心に近づくことは可能かと思います。
次に、大英帝国最盛期について学ぶことができるのかというご質問ですが、こちらの主題につきましても専門とする教員は本学科に在籍しておりませんが、卒業論文作成の指導を本学科で受けることは可能です。
大英帝国最盛期とはいつを指すのか(これ自身が大きな歴史学上の論点です)という問題はありますが、仮にヴィクトリア女王治世期と考えますと、この主題については、西洋近現代史ゼミに所属することで卒業論文を作成することが可能です。これまでも、この時代を扱っ卒業論文は複数提出されています。
さらに、文学部英文学科や外国語学部英語学科の関連科目を履修することで、視点をさらに深めることも可能でしょう。
芸術の歴史的背景を研究したいのですが…
質問
私は芸術(特に文学や絵画、演劇)の歴史的背景について研究をしてみたいと考えています。文学部英米文学科と史学科で迷っているので、ご意見いただきたいです。
回答
ハワイ/アジア系移民研究は、アジア史/アメリカ史?
質問
ハワイのアジア系移民の歴史の研究の場合、アジア史アメリカ史どちらの視点になりますか?
回答
これは、近代の移民ということでしょうか。どの視点から何を明らかにしようとするかで、分野が違ってくると思います。あくまで、移民元の地域から、そのアイデンティティーに基づいて事象を追いかけようとすれば、アジア史の分野になるでしょう。逆に、国民国家アメリカの範疇において、受け容れ側の視点で考えるならば、アメリカ史ということになります。あるいは、ハワイ島独自の長大な歴史・社会・文化において、近代の限定的問題を捉えるならば、ポリネシア史の文脈で考えたほうがよいかもしれません。それらすべてが交渉する全体像を、グローバル・ヒストリーの視点で総合的に把握してゆく方法もあります。
自分が何を明らかにしたいのか、その問題意識如何で、分野は異なってくると思います。最終的には全体的な把握を目指し、まずは最も関心があるところに足場を築いて、考えてゆけばよいのではないでしょうか。
天璋院篤姫の研究はできますか?
質問
天璋院篤姫に関する研究はできますか。
回答
戦史についての研究は可能ですか?
質問
貴学部の受験を考えている者です。貴学部に進学した暁には、古代から近世の、所謂「近代兵器」が発達する以前の戦争について、その背景も含めて主に地政学的観点から研究したいのですが、どの程度可能でしょうか?また、研究を行うにあたって決まった専門分野を持たず、勃発や勝敗の要因を考察する上で重要な地理的、政治的、宗教的その他様々な観点や兵法など多岐にわたる分野について広く研究を行うことは可能でしょうか?
回答
中世の地中海や貿易について研究できますか?
質問
上智大学の史学科への進学を志望しているものです。私は大学で中世の地中海貿易史について研究したいと考えています。他の質問者様へのご回答を拝見したところ、ローマ帝国時代や共和制期の地中海の島々についての研究は可能であるとのことでしたが、中世の地中海や貿易についての研究することは可能でしょうか?また、それに関する講義はありますか?
回答
東欧近現代史について、どの程度研究ができますか?
質問
上智大学の史学科への進学を希望している者です。私は東欧近現代史に興味を持っています。近現代の東欧はソ連からの強い影響が及んでいた地域であり、この地域の歴史を学ぶ上でソ連についての学習は避けられないものと考えていますが、ほかの質問者様の投稿を拝見したところ、「上智大学文学部史学科にはソ連・ロシア史を専門とする教員は在籍していないが、必要に応じて外国語学部ロシア語学科の教員からサポートを受ける事が可能」と書かれていました。東欧近現代史について、上智大学ではどの程度研究ができるのでしょうか。また東欧諸国との相関関係の中でソ連を見る場合に、外国語学部の先生方からはどの程度のサポートを受けられるのでしょうか。
回答
お問い合わせありがとうございました。
東欧近現代史およびソビエト連邦を東欧諸国との関係性の中で学んでみたいとのことですね。確かに、上智大学文学部史学科にはソ連・ロシア史を専門とする教員はいないですし、東欧近現代史を専門とする専任教員もおりません。しかし、東欧諸国と西で境を接するドイツ近現代史を専門とする教員はおりますので、卒論を準備するにあたって様々な助言を得ることができると思います。
また、ご指摘の通り、上智大学外国語学部ロシア語学科には、現代ロシアの地域研究を専門とする専任教員がおります。史学科の学生でも、外国語学部を含む他学部や他学科の授業を履修することも可能ですので、ご自身の関心に結びつくようなロシアに関わる授業を受けることも可能でしょう。こうした授業を履修する中で、先生に直接コンタクトを取る機会もあるのではなかと思います。
ご自身のやる気と努力があれば、道は開かれると思います。がんばってください。
帝政期ローマの都市の研究は可能でしょうか?
質問
上智大学の史学科において、帝政期ローマの都市(特にトリーアなど)の研究については可能でしょうか?
回答
お問い合わせ、ありがとうございます。
本学において帝政期ローマの都市についての研究は可能です。
ローマ世界の研究は、英語が主ですが、地域・分野によっては、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語などの文献があります。それらの文献も読むことができれば、理解が深まります。
本学においては、ラテン語とギリシア語も含め、様々な言語を学ぶことができるので、古代ローマ史を学ぶ環境が整っていると言えると思います。