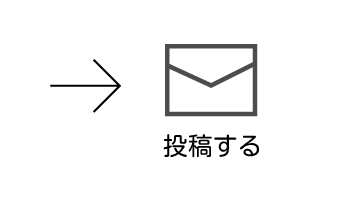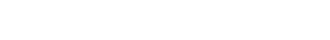中世ヨーロッパ史を調べるうえで、幾つか質問があります。
質問
中世ヨーロッパ史を調べるうえで、幾つか疑問が生じています。下記のとおりですが、部分的にでも教えていただけると嬉しいです。
① 史料をどう調べたり、読んだりされているのでしょうか。
② どこまで調べるべきでしょうか。
③ テーマを決めた方が良いでしょうか。
回答
ご質問ありがとうございます。よく勉強されているようですね。
ヨーロッパ中世を研究する場合、「司教」を始めとした聖職者が残した記録は、避けて通ることができません。彼らは、少なくとも中世の初期までは、社会の知的営為をほぼ独占的に担っていた存在であり、政治的にも大きな役割を果していたからです。日本語で読めるものとしては、トゥールのグレゴリウス『歴史十巻(フランク史)』、尊師ベーダ『イングランド教会』、エインハルドゥス『カール大帝伝』などがあるので、手にとって読まれるといいでしょう。あと中世では『黄金伝説』という聖人伝が一種のベストセラーとして有名ですが、これを編纂・執筆したのは、ジェノヴァ大司教のヤコブス・デ・ウォラギネという人物です。彼がなぜ、こうした本を製作したのかも興味深いです(この書も邦訳があります)。
ヨーロッパ中世の元々の史料は、「マニュスクリプト」(手稿・写本)というかたちで文書館などに所蔵されています。使用されている言語はラテン語や古英語・古仏語などです。こう聞くとハードルが高いように感じるかもしれませんが、活字化されたもの(「刊行史料」)や英訳などの現代語訳も多数あります。また欧米の第一線の研究者でも、すべて写本から見ているわけではないですよ。
あと西洋中世史の卒業論文では、必ずしも「史料」から議論を起こす必要はなく、欧米の研究をきちんと消化して自分なりに考えてみる方がよいと指導しています。ただし、論文や研究書を正しく理解する場合、史料についての基礎知識は必須です。史学科では、1年次の必修科目でその事をきちんと学ぶことができます。また上智大学ではラテン語などの古典語も学べますし、図書館には貴重な資料が豊富にあります。西洋中世史を学ぶには格好の大学だといっても過言ではないでしょう。
最後にテーマについてですが、現段階でこまかく絞る必要なく、西洋史の他の時代や日本史や東洋史も広く学んでおく方がよいのかなと思います。現役の学生をみていますと、2年生の段階でだいたいの領域(地域と時代)を決め、3年生の間に自分の関心と先行研究を踏まえてテーマを決めているようです。それでも毎年、優れた卒業論文がたくさん提出されています。上智大学の史学科は少人数制で、2年次から実質的なゼミが始まりますので、指導教員や先輩のきめ細かいアドバイスが受けられるのもメリットだと思います。
もちろん「貴族階級」というのも、中世ではきわめて重要な存在で、テーマとして興味深いです。よく勉強している質問者さんが、上智大学史学科にご入学され、ともに学べることを楽しみにしています。