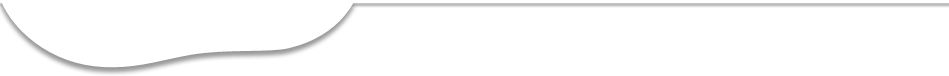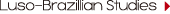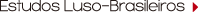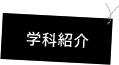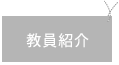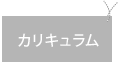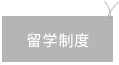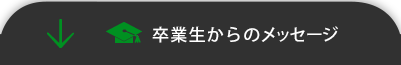上智大学外国語学部ポルトガル語学科は、1964年、ブラジル人のヴェンデリーノ・ローシャイタ神父を中心に正式に設立されました。学科の母体となったのは、ブラジルへの移民に関わる人材育成のため、1959年に設立されたポルトガル・ブラジルセンター(2008 年4 月にポルトガル語圏研究所に名称変更、翌年4 月にイベロアメリカ研究所に統合)です。
多くの日本人、ポルトガル人、ブラジル人教員が学科を発展させてきました。また長い歴史の間には多くのイエスズ会の神父が教壇に立ち、キリスト教精神に基づく「他者のために、他者と共に」を理念に、時に厳しく、そして常に辛抱強く学生たちをポルトガル語の世界に誘い育ててきました。その理念は、今も受け継がれています。
皆さんはポルトガル語を公用語とする国々を知っていますか?ポルトガル、ブラジル、6つのアフリカ諸国(アンゴラ、モザンビーク、サントメ・プリンシペ、ギニアビサウ、カーボベルデ、赤道ギニア)、さらには東ティモールと計9か国あります。それ以外にも、ポルトガル人が大航海時代にポルトガル文化を持ち込んだことから、現在ではポルトガル語だけが英語以外に5つの大陸で話される言語となっています。これもひとえにポルトガル人固有の探検魂の結果といえましょう。
ポルトガル語学科では言葉を学ぶだけでなく、その地域に対する理解を深めることを目指しています。学科の教育のモットーは「言語と地域研究の両輪」です。今はAIの時代。簡単に外国語を日本語に、また日本語を外国語に翻訳することができます。でもどんなに機械翻訳の技術や精度が上がっても、人間が自分の言葉で相手とコミュニケーションをする意味は常にあります。ではそのためには何が必要か。そこで大事になるのがその地域の歴史や文化、社会事情に対する知識や理解です。学科では学生たちの知的関心を高めるべく、さまざまなポルトガル語圏に関する科目を用意しています。それらを支えるのが学科教員の幅広い研究関心です。その一旦をご紹介しましょう:ポルトガルの近現代史研究、ブラジルやアジア、ヨーロッパのポップカルチャー研究、ブラジルの政治や外交戦略、アフリカの政治や歴史、ブラジルの人種関係の研究、ブラジルの貧困地域におけるコミュニティ教育、在日ブラジル人の生活、世界に散らばるブラジル移民の研究、ブラジル北東部地域を中心とした文学の研究など、です。
21世紀も早や20年が過ぎました。私たちの日常を変えたコロナウイルスのパンデミック、地球温暖化による異常気象や頻発する自然災害、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルとハマスとの戦闘、分断が深刻化する国際社会など、日本はこうした不安定な世界の中でどう行動すべきか。ポルトガル語圏には日本にとって不可欠な食糧やエネルギーに富んだ国々が存在します。一方で貧困や格差、治安などの問題を抱える国も少なくなく、日本の経済・技術協力に強い関心を示しています。ブラジルのように移民を介した歴史的な関係を持っている国もあります。日本がこれまで以上に目を向けるべき地域がポルトガル語圏の国々だといえます。ポルトガル語、そしてポルトガル語圏の世界を学んでみませんか?