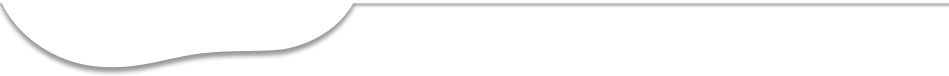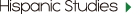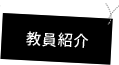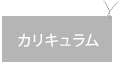スペインが生んだフランシスコ・デ・ゴヤ(1746-1828年)は、近代のヨーロッパ絵画を代表する画家のひとりです。裸身を晒して鑑賞者に挑戦的なまなざしを投げかける《裸のマハ》(図1)や、生まれたばかりの幼子を貪り食う恐ろしい異教の神を描いた《わが子を食らうサトゥルヌス》(図2)などの代表作は、日本でもテレビや書物などでしばしば紹介されることから、一度はどこかで目にしたことがあるという人が少なくないと思います。これらの2枚の絵が物語るように、ゴヤという画家の作品はなかなかクセが強く、同時代にスキャンダルを巻き起こしたものもあれば、現代の私たちの目にもセンセーショナルと映るものさえあります。こうした作品を生み出したゴヤに対して多くの人が抱くイメージとは、どのようなものでしょうか。
ゴヤの後半生のスペインは、対仏独立戦争(1808-1814年)やその後の国王フェルナンド7世による抑圧的統治などを経験した動乱の時代でした。またゴヤ自身は40代後半に患った重病の後遺症で、聴覚を完全に失ってしまいました。そうした暗澹たる社会的状況とゴヤを襲った個人的不幸が、いつの間にかサトゥルヌスの絵のようなおどろおどろしい作品と結びつけられて、まるで作者ゴヤ自身が音のない孤独な世界に生きる、どこか狂気じみた画家であるかのような伝説的イメージが先行しているきらいがあります。
しかし、実際のゴヤは孤高の人でも狂気の人でもなく、きわめて俗っぽくて人間臭い、ごく当たり前の(もちろん素晴らしい画才には恵まれていましたが)人でした。そのことを証明してくれるのが、ゴヤ自身が身近な人たち、特にマルティン・サパテールという名の親友に宛てて書き送った数多くの手紙です。現存する120通以上のサパテール宛ての手紙には、崇高な芸術論などとは無縁の、どこまでも世俗的なゴヤの日常が綴られています。そこから立ち現れるゴヤは、宮廷での栄達と蓄財を夢見る野心家で、強すぎる矜持ゆえに職場での先輩でもある義兄や注文主と衝突するかと思えば、他方では郷里の家族に絶えず仕送りをしたり、妻や子の病気におろおろしたりする心優しい家庭人でもあります。画業の初期には意外にも挫折続きだっただけに、ひとたび宮廷で人気画家にのし上がるや、金ぴかの馬車を乗り回したり高価な衣装を誂えさせたりして誰はばかることなく成功を見せびらかすその姿は、どこかコミカルで愛嬌に満ちていて、要するに「愛すべきキャラ」なのです。
私事で恐縮ですが、つい最近、そのサパテール宛て書簡を含むゴヤ自筆の手紙と文書類をほぼすべて収録した翻訳書を恩師とともに出版しました(大髙保二郎・松原典子共編訳『ゴヤの手紙(上)』岩波文庫、下巻は6月中旬刊行予定)。この本は、ゴヤ自筆のものばかりでなくゴヤ宛てに書かれた手紙やゴヤ関連の公文書までも網羅して14年前に出版した単行本を基にしています。単行本が1万円を超える高額で、研究者やごく一部の愛好家の手にしか届かなかったのに対して、文庫本であれば広く一般の方にもフランシスコ・デ・ゴヤという人間の真の姿を知ってもらう契機になりうるのではと期待しています。
文庫版の「あとがき」にも書きましたが、等身大のゴヤを知ることは、単にゴヤの人となりやその人生を知るためだけでなく、ゴヤの作品の真価を理解するうえでとても大切です。ゴヤが人の心の奥底に切り込んだり、美しいものだけでなく醜いものも絵画の主題として真っ向から取り上げたりして、近代絵画の先駆者たりえたのは、その本質において私たちと何ら変わらない当たり前の人間だったからこそだと思うからです。そしてそのことは、当たり前の人間の手で生み出されてきた美術作品が、一見いかに私たちの日常とはかけ離れたものに思えるとしても、実は常に普遍的な意味を内包しているのだということに改めて気づかせてくれるような気がします。
『ゴヤの手紙』、書店で見かけたら是非一度手に取って、偉大な画家にして魅力的な人間ゴヤの肉声に耳を傾けてみてください。