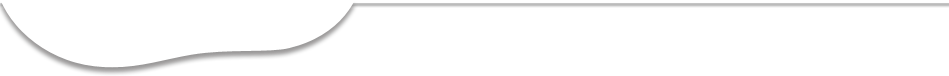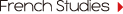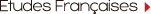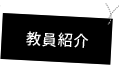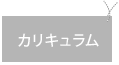フランス語学科シネクラブでは、昨年12月19日にフランソワ・トリュフォー監督作品『野生の少年』を観ました。エルヴェ・クーショ先生に、そのときの様子を文章にしていただきました。フランス語学科在籍の学生であるシネクラブの参加者およびヘルパーが、春休み中に日本語訳に取り組みました。
Qu’est-ce qu’une bonne éducation ? : à propos d’un débat sur L’enfant sauvage de François Truffaut
Face aux tourments manifestés par Victor, l’enfant sauvage formé aux dures exigences de la civilisation par l’enseignement du docteur Itard, une étudiante se demande s’il n’aurait pas mieux valu pour lui qu’il reste vivre dans sa forêt aveyronnaise où, privé de toute société, il semblait au moins jouir de la liberté et s’adonner aux plaisirs simples d’une vie naturelle. Cette quasi objection, qui fit fondre en larmes l’autodidacte Truffaut lors d’une présentation de son film en Suède, n’en soulève pas moins quelques problèmes toujours très actuels en matière de pédagogie : comment expliquer en effet que le plaisir de l’enfant soit aussi peu pris en compte dans cet apprentissage aussi austère que systématique, d’où le rire lui-même semble proscrit, et au cours duquel le docteur va jusqu’à faire subir une injustice à l’enfant pour s’assurer de son sens moral ?
D’autres étudiants relèvent l’importance du rôle joué par la gouvernante, Madame Guérin, qui semble compenser par ses soins attentifs et sa tendresse maternelle les rugosités d’une éducation trop disciplinaire qui tourne parfois au « dressage ». L’humanité pudique du docteur Itard, soucieux d’obtenir rapidement des résultats afin que son élève ne soit pas renvoyé dans un asile d’aliénés, est perçue par une étudiante qui remarque également son encouragement de la créativité de Victor au moment où ce dernier fabrique un porte-craie à partir d’un os de gigot.
Au final, le débat sur cette adaptation cinématographique datant de 1970 — soit deux ans après les grandes manifestations étudiantes de mai 68 — d’un mémoire rédigé dans les dernières années du siècle des Lumières, repose un problème que tout professeur rencontre inévitablement au cours de son enseignement, quelles que soient l’époque et la culture dans lesquelles il exerce son métier : quelles parts respectives accorder au plaisir d’apprendre et à la nécessaire acquisition de règles permettant la vie en commun ? Et comment stimuler le désir d’apprendre qu’un excès de rigueur disciplinaire autant qu’une absence de repères finissent toujours par scléroser ?
イタール博士の教育によって文明の厳しい要求で育てられた野生の少年ヴィクトールが悩みを表明するのを見て、〔シネクラブに参加していた〕学生の一人が、彼にとってはアヴェロンの森で生き続けていたほうがよかったのではないかと疑問を漏らした。森のなかでは社会性というものが完全に奪われているが、少なくとも彼は自由を享受し、本来の生き方の素朴な喜びにふけることができたように見えるからだ。これはほとんど反論であって、独学の人トリュフォーもスウェーデンで彼の映画が上演されたときにこのような反論に涙を見せたことがあるのだが、それでもこの問いかけは教育に関してつねに非常にアクチュアルで重要ないくつかの問題を提起する。実際、このように厳格かつ体系的な学習において、子どもの喜びがほとんど考慮に入れられていないのはどう説明したものだろう。笑いそのものが禁じられているようだし、学習過程でイタール博士は、ヴィクトールに不当なことを加えるまでして、彼の道徳感覚を確認しようとする。
家政婦のゲラン夫人の役割の重要性を指摘した学生もいる。彼女は、行き届いた心遣いや母親のような愛情で彼を包むことによって、ときには「調教」と言えるようなあまりにな厳しいごりごりの教育の埋め合わせをしているように思われる。イタール博士は、自分の生徒であるヴィクトールが精神病院に送り返されることがないよう、結果を早く出したいと気にかけていたが、そのような博士の慎ましい人間性に気が付いた学生もいる。その学生は、ヴィクトールが羊の骨からチョーク入れを作ったとき、その創造力に博士が自信を持たせようとしていた点も指摘してくれた。
最後に、啓蒙の世紀の最後の年月に書かれた記録を、1970年という時期――すなわち、68年の5月の大規模な学生運動の2年後――に映画に翻案したことをめぐって、議論が行なわれた。そこでは、教師であれば誰でも、どんな時代や文化においてその職業に従事するにせよ、教育過程において必ずや出会うことになる問題がもう一度提起された。学ぶ喜びと、共同生活を可能にするのにどうしても必要な規則の習得は、それぞれどのくらいの配分にすればよいのか。そして、過度に厳格なしつけも、指針の欠如も、最終的には学習意欲を硬直化させてしまうわけだが、そうしたなかで学習意欲を刺激するにはどうすればよいのか。