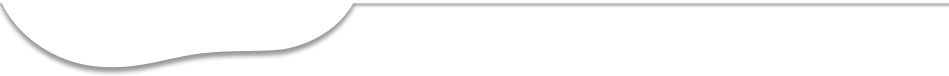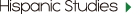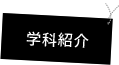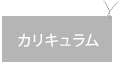「ラ・ビエヘシータ」
1956年入学(第2期生)高山智博
2022年6月16日 記
信じられないことが起こった。単なる脇役に過ぎなかった私が、終演後に演劇部の学生から「部員にならないか」と懇願されたのだ。しかも声をかけられたのは自分だけだった。もちろん、慌てて断った。しかもその後発行された上智大学新聞には、舞台の真ん中で歌っている私の写真が載っていた。その記事には「駐日スペイン大使館と武蔵野音楽大学の協力を得ておこなわれたもので、日本では初めての試みである」と書かれていた。
舞台の後ろで歌っていた私が、いつの間に前面に出たのか全く覚えていない。それだけでなく、人前で歌うのも話すのも苦手な自分が、どうしてスペイン語劇に出演したのかさえ覚えていない。同期の連中がこの劇に出ることにしたので、つられて参加したとしか思えない。それに舞台ではメガネを外していたので、客席がよく見えず、羞恥心も吹っ飛んでしまっていたのだろう。
1957年1月、課外活動の一つであるスペイン語文化研究会は、上智大学1号館講堂で、スペインのサルスエラ(喜歌劇)「ラ・ビエヘシータ(おばあちゃん)」を公演した。台本ミゲル・エチェガライ、作曲マヌエル・フェルナンデス・カバジェーロによる作品で、首都マドリッドでの初演は、1897年だったそうである。
1号館は1932年に竣工した上智で一番古いレンガ風建物だ。その二階にある講堂は、スペインの時代劇を演じるには、舞台としてピッタリだと思った。主な出演者では、文学部外国語学科イスパニア語専攻の1期生だった八戸公明さんと和田稲雄さんが、軍の将校として準主役を演じた。入学して10ヶ月も経たない我々2期生は、竜騎兵として舞台の後ろで合唱を担当した。これに吉岡晋也君や蕨誠君など12、3人が参加した。この公演は文学部外国語学科イスパニア語専攻が、外国語学部イスパニア語学科にかわる1年前のことである。その頃、全学の学生数は少なく、現在の約10分の1の1500人前後しかいなかったと記憶している。教師には外国人のイエズス会士が多く、彼らはローマンカラーに黒い制服を着ていた。学生も学生服姿なので、大学全体が黒一色の地味な感じがした。
しかも当時は男子校だったので、女子は一人もいなかった。そこで主役の「おばあちゃん」役として選ばれたのが、武蔵野音楽大学(日本で初めて認可された音楽大学)の声楽専攻の女子学生だった。その面影は今でもはっきり覚えているが、名前はどうしても思い出せない。彼女にとってスペイン語は初めてなのに、しっかりセリフや歌詞を覚えて、舞台では見事に演じてくれた。傍から見ていて、“すごい”と感心したものだ。この他にも、聖心女子大学の学生が数名参加していた。ともかく、女性が参加したことで男性群はハッスルし、合同練習は一気に花が咲いたようになった。
余談になるが、大学ではこの年、女子学生の入学を認めるか否かで、学生投票が行われた。その結果、女子の入学賛成が多数決で決定したのである。翌年から女子学生が入って来た。以後、女子学生の数が増えて、上智の雰囲気が一変した。男子も学生服姿が少なくなり、背広を着たおしゃれも出て来た。
サルスエラ「ラ・ビエヘシータ」の筋書きは、軍の将校であるカルロスと侯爵の姪であるルイサが、愛し合うことからはじまる。しかし彼女に求婚していたのはフェデリコだ。しかもルイサの叔父の侯爵はフェデリコの保護者である。こうした人間関係の中で、カルロスはおばあちゃんに変装する。喜歌劇はここから新たな展開となる。
出演者を一人で指導してくださったのが、ホセ・テホン(後にエリザベット音楽大学の学長に就任)というスペイン人神父である。ピアノを弾きながら、音符も読めない我々男子学生を、どうにか形がつくまでまとめあげてくれた。その努力は大変だったに違いない。
次の問題は舞台衣装をどうするかだ。その頃は学生服しか持っていないような貧乏学生が多かったため、新たに衣装を作るわけにもいかない。そこで1期生の仲谷湍さんの実兄が、文学座の有名俳優の仲谷昇氏だったので、氏にお願いすることにした。お陰で文学座の衣装を借りることができた。主役と準主役には役に合った衣装が用意され、竜騎兵の我々は、一人一人若干異なるが軍服があてがわれた。その結果、舞台はビックリするほど立派なものになった。1期生の堀口進一さんは英国軍の隊長の役を演じた。彼が「腰に帯びたサーベルは、以前文学座がハムレットを公演したとき、主演の芥川比呂志氏が使用したものだったそうで、たいへん光栄に思った」と述懐していた。
当日、会場には駐日スペイン大使をはじめ、ラテンアメリカ諸国の大使館や公使館の館員や家族、それに出演者の家族なども詰めかけ、大変な盛況であった。我が家からも母と妹が観に来てくれた。幕が降りると、盛大な拍手が沸き起こった。観客の中には涙を流しているスペイン人らしき夫人もいた。拙い演技であったが、熱意だけは伝わったのだろう。舞台に出ている私を観て、母が「とても喜んでいたよ」と妹が教えてくれた。自分にとってこれほどうれしかったことはない。我が青春の一幕である。
回想 サルスエラ「LA VIEJECITA」のこと
1955年入学(第1期生)堀口進一
2011年5月29日 記
1期生堀口進一さんのエッセイの一部を、ご本人の許可のもと掲載します。写真は1期生豊田正喜さんにもご提供いただきました。
本邦初演のサルスエラということで、何か歴史的に意味があるように思われるが、これに出演した我々学生達は、それまでサルスエラというものを見たこともなく、初演ということの意識や気負いはあまりなかったと思う。
この劇はタイトルのとおり、一人のおばあちゃんを主演にした時代劇であるが、この公演に関しては資料が何も残されていない。
当時のことで映像記録や録音はなかったし、プログラムや台本、譜面といったものも消失してしまっている。僅かに残っている数葉の写真から出演者の顔ぶれや舞台の雰囲気を偲ぶことしかできない。
当時、スペ研で発行されていた「CORREO」誌には関連記事が掲載されていると思うが、それがどこかに残っているかどうか。
あとは、出演者の記憶に頼るしかないが、何分半世紀以上を経て出演者も高齢化し、その記憶も不確かなものになってしまっている。
私の場合も例外たり得ず、当時のあれこれを回想しようとしても、すべてが霧の中にかすんでしまっていて、劇のストーリーも、公演を終始指導してくださったスペイン人神父様のお名前すら想い出せない。
まことに頼りない話ではあるが、それでも残された記憶をたどり、比較的はっきりと印象に残っていることだけでも書き出してみたい。
この劇が上演された1957年1月といえば、イスパニア語1期生にとって2年次の学期末に当たるが、どうにかスペイン語の中級が理解できるようになった程度で、語劇を演ずるには未だ力不足であったと思う。それでもサルスエラをやろうということになったのは、指導に当たられたスペイン人神父様の熱意と、好奇心の強い学生が大勢いたからだったと思う。この神父様は、ピアノだけを使って音楽面から演技のひとつひとつまで全てについて一人で指導してくださった。それまで演劇の経験もなく、音譜も読めない私共をして、なんとかかっこうのつく劇にまとめあげるのには、非常なご苦労があったと思われる。
次いで特筆されるべきことは、やはり他校の女子学生との共演が実現したことである。当時の上智には女子学生は在学していなかったので、主役を含めた女性出演者を校外に求めざるをえなかった。どのようなツテがあったのか知る由はないが、武蔵野音大等から7~8人の女子学生が共演していただけることとなり、これが上演を可能にした鍵となった。彼女たちの中には声楽専攻の人もいて、サルスエラの音楽的な魅力とその出来映えは、彼女たちの美声に負うところが大であった。さらに女子との共演は、我々男子出演者を大いにハッスルさせ練習にも一段と熱が入るという現象を生んだ。
練習会は、いつも1号館4階の大講堂に全員が集合し、神父様のピアノの先導でソロやコーラスの練習が繰り返された。当時の学内は学生数も少なく、女性の姿はなく、キャンパスには、厳粛な空気がただよっていたが、その一角から時折華やいだ混声コーラスが流れていった。
私事であるが、この頃私はある学生連盟の活動に参加していて、その関係でときどき練習会に出られないことがあった。私一人が欠けることで、みんなに迷惑をかけることになったが、こんな状況を見兼ねたのか、女子学生の一人から個別の特訓をしてあげてもよいとの申し出があり、何度かマンツーマンの指導をしていただいた。アミーガもいなかった私にとってそれはとても楽しいひとときであった。
1957年頃は、未だ貧しさの残っていた時代で、アルバイトに追われている学生も少なくなかった。
このサルスエラでも、時代劇の舞台を盛り上げるための大道具、小道具などは、資金がなく何もできなかった。だが、残っている写真を見ると、出演者の衣装は中々立派で、スペインの時代劇らしい雰囲気が充分にかもし出されている。
実はこの衣装は、1期生の中谷君の実兄昇氏が劇団文学座の俳優さんであった縁で同劇団から借用できたものである。この衣装は舞台を盛り上げるうえで、大きな効果があった。因みに、私は劇中、英国士官という役柄を演じたが、腰に帯びたサーベルは、以前文学座がハムレットを公演したとき、主演の芥川比呂志氏が使用したものであったそうで、たいへん光栄に思ったことであった。
この劇の主演をつとめたのは、音大、声楽専攻の方、お名前を失念してしまったが、よく解らないスペイン語で、長いソロをしっかりとこなしてくださった。準主役は1期生の八戸公明君と和田稲雄君、脇役が新井範明君と私、出演者は25人前後で、うち女子が7~8人であった。2期生で参加した者の中には、後年上智の教授になられた高山君、民放アナウンサーで活躍された吉岡君などもおられた。
1期生と2期生の絆は、今でも強いように思われるが、スペ研活動やこのサルスエラをいっしょにしてきたことからであろう。
本番は、たったの一回であった。当日、会場となった1号館の講堂には駐日スペイン大使他、中南米各国の在日公館の方々、その家族等を含め多くの観客が集まり大層な賑わいであった。
当日、出演者は夭々に盛装し、メーキャップをして晴れの舞台に立った。とにかく全員とても緊張していたし、無我夢中の演技であったと思う。
幕が下りると観客から盛んな拍手をいただいた。初めて味わう感激であった。出演者みんなの顔には安ど感と達成感が現われていた。
今になってみると、このときの拍手と感激が、翌年も語劇をやろうということにつながり、さらに、その後今日まで語劇が続いてきたことの原点になったように思える。
劇中に、一ヶ所だけ私のソロがあった。女子学生から特訓までしていただいたにもかかわらず、なんと本番で大トチリをしてしまった。
極短いソロであったが、タイミングよく歌えなかったのである。すぐに失態に気付いたものの既に万事休す。ああ劇全体を台無しにしてしまったと思うと、悔やんでも悔やみきれず、この思いは今でも苦渋の一滴のように残っている。
私にとっては、それこそ人生に一度の晴れ舞台、もう少しかっこうよく演じていればという思いである。
この公演を振り返ってみるとき、出演者側にとっては、練習会、本番を通して、とにかく楽しく、忘れ難いよい想い出を残すことができたと思うが、他方、観客の側に立ってみれば、果して劇そのものを本当に楽しんでいただけたのかどうか、疑問であり、不安が残る。
私の大トチリを含めて、劇の完成度は、それ程高いものではなかったに違いない。
それでも観客のみなさんは、スペイン語にも未熟な学生達が、果敢にサルスエラに挑んだ、その勇気に対して拍手を送ってくれたのだと思う。
上智大学新聞掲載記事
スペイン語のオペレッタ ”ラ・ヴェシイタ”を上演
スペイン語文化研究会は、十九、二十日の両日、本学講堂でスペインのオペレッタ「ラ・ヴェシイタ(おばあちゃん)」をスペイン語ではじめて公演した。
これは駐日スペイン大使館と武蔵野音楽大学の協力を得ておこなわれたもので、日本では初めての試みである。
二十日には駐日スペイン大使をはじめ数多くのスペイン人や中南米関係者が鑑賞して、他国で演じられている母国語の芝居に拍手を送っている姿が見られた。
なお、これはソフィア祭に上演する予定だったが中止になったため延期していたもので、五月のはじめおこなわれるフレッシュマン・ウィークに再上演されることになっている。同研究会では今後一年に一度ずつこの種のオペレッタを上演する予定である。