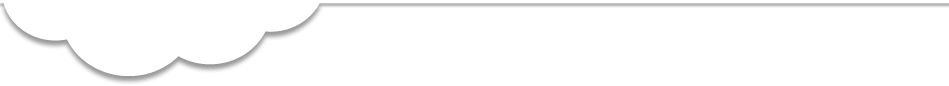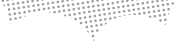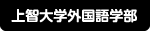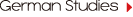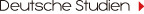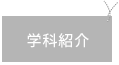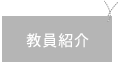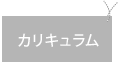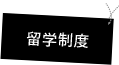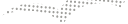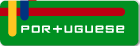Guten Tag! 現在ハイデルベルク大学に留学中のドイツ語学科3年堀川ゆいみです。フランス国境近くのSaarland大学で在外履修を終え、1年間の交換留学が始まったところです。合計で1年半のドイツ留学、日本の大学生活の半分近くをドイツで過ごしていると考えると自身でもなかなか胸にくるものがあります。新学期が始まって1ヶ月弱ですが、今回は前学期と比較しながら、ハイデルベルクの新しい生活について書かせていただきます。
半年程海外にいれば、「ああ、こういうものか…」と慣れてくるものですが、ドイツは手続き関連の進行がとにかく遅いです。私の場合は、在外履修の終了直前にVISAが切れると発覚し、日本に一度帰国する日の二日前に入国管理局へ直談判をしに行きました。VISAがないとドイツへ再入国できず、日本からは手続きが難しいので、何が何でも更新しなければならないと必死でした。幸いにVISAの更新はなんとかなったものの、続いて2ヶ月に渡り保険手続き及び学生登録が出来ない問題に当たりました。問題なのは、この2点が終わらないと学生証が手に入らないため、ハイデルベルク大学の履修登録やMoodle (e-Learning学習管理システム) など、あらゆる大学の施設やツールが使えないということでした。そのため、可能な限り早く保険手続きを…と思っていたのですが、ドイツ国内の住所が変わったがために、次の大学へM10 (保険加盟証明書) を送れないとのことでした。Saarlandにいた際には、保険カードが手に入らない (カードがなくても保険は効くと耳にはしましたがカードが手に届かないというのは一大事らしいです) 、日本への一時帰国分を払い戻ししてもらいたい、などの問題に拍車がかかり、ドイツ人の友人に保険会社へ電話してもらってもらいましたが、「ドイツ人からしても厄介な問題だ」と言われました。ドイツは日本のように違う部署にいても、ある程度のノウハウがある、と思ったら大間違いで、担当者から担当者に回されるのは当たり前です。オフィスに行っても無駄足になったり、些細な問題でも一つ一つメールをして返さなければならないので、忘れられているのでは、と不安になるほど時間がかかります。私の性格的に日本にいたら、「どうしよう」と焦ってしまいますが、何度も対面しているうちに私みたいな人は沢山いるし、ドイツの人もこの事情を分かっているだろう、と開き直りました。現在はDeutschlandticket (ドイツ全国定期券) の解約と新しい保険の手続きに立ち向かっているところです。
さて、実生活の方はどうかというと、前学期の苦労が嘘だったかのようにスッと馴染んでいます。もちろん、ドイツ自体に慣れてきたということ、それから、基地となる自室をすぐに整えられたことは大きな要因だと思います。閑話休題にはなりますが、自室のQOL (生活の質) を上げるというのは、精神的に非常に大事だと感じています。色のあるものを取り揃えたり、写真や旅行のお土産を飾ってみたり、スピーカーから音楽を流したりして無防備になれる場所というのは1人であればあるほど重要です。
前学期での経験を踏まえ、私はドイツ語を話す機会を増やす、という大まかな目標を立てていました。というのも、前学期にドイツの方と日常的に話す機会というのはゼロに近かったからです。Buddy(バディ)制度とともにTandem(タンデム)制度もあったのですが、両者とも連絡がつかなくなってしまいました。当然 「ドイツ語を学ぶ授業」にドイツ人がいるわけもありません。私が履修したIntensive Deutschkurs (ドイツ語コース)は平日は木曜日を除き毎日、朝8:00-お昼の13:00あたりまで授業がありました。日本で履修した授業と比べると、「こんなものか」と思いましたが、それを全てドイツ語で、更に、お昼休憩もなく毎日、加えて、宿題や家事もとなると午後からドイツ語を話す体力は残っていません。話す力という観点においては、結局クラス内でのみに留まってしまいましたが、文法 / リスニング / リーディングにおいては、群を抜いて力を付けることができる大学だったと思います。授業も4技能に分かれて時間が設けられているので、ドイツ語を根本から鍛えたいという方には、Saarland大学は非常におすすめです。それに比べ、ここハイデルベルク大学の授業は上智大学でいうところのコミュニケーションに近い形で行われます。語学コースが少ない分、他科目の配分は自由で、人によってはVorlesung (講義) やJapanologie (日本学) の授業をとる人もいます。私は前学期の時間割の関係で旅行に行く時間が取れませんでした。土・日は休みでしたが、日曜は営業外のところが多く、日帰りで土曜日に旅行していました。なので、今学期は連休を作って見聞を増やす機会を増やしました。それ以外の時間は、2人のドイツ人の友人と固定のTandemをしていて、少なくとも週4時間、多くて10時間以上をほぼドイツ語で話しています。ハイデルベルクに来てから1ヶ月しか経っていませんが、明らかに話せるようになったな、としみじみ感じています。ありがたいことに旅行を含めると目まぐるしいほどの1ヶ月です。
ハイデルベルクで生活していて、ひしひしと実感するのは、都市ごとの日本文化の浸透割合、国籍と治安の違いです。人種差別をするわけではありませんが、個人的な見解として、国籍と治安は密接に結びついているのではないかと思っています。Saarlandはアフリカ圏、または、南アジアからの渡航者が殆どで、私のクラス内にヨーロッパの留学生はいませんでした。国籍の割合に比例して、イスラム圏の店舗も数多く揃っています。旅行などで早朝に寮を出る場合、または、冬時間の20:00以降は駅付近の治安に不安を覚えることもありました。一方のハイデルベルクはというと、アジア人、とりわけ中国人が3割にアメリカ系の人々が3割、その他、ヨーロッパと多岐に渡っています。ドイツ随一の学生都市ということもあり、深夜近くでもバス/電車の本数は多いですし、繁華街の治安も非常に良いと言っても過言ではないと思います。とはいえ、4月から大麻が合法化されたので、気をつけるに越したことはないと思っていますが。
また、ハイデルベルク大学の特徴と呼べるのはJapanologieの存在でしょう。授業という括りではなく学科規模で日本語を学ぶ生徒がいる、つまり、それだけ日本文化に興味を持った学生が在籍しているので、日本人もコミュニティに入りやすい環境です。前学期(Saarland)は日本人がとても少なく、日本語学科はなかったので、現地で出会った心許せる日本人の方とただ「日本語を話せる」ということが大きな支えとなっていました。文化に興味を持つことからコミュニケーションが広がると思っているので、Tandemのしやすいこのハイデルベルクの環境、そしてMensa(学食)に行けば必ず知り合いがいる、という安心感に心から感謝しています。加えて、ハイデルベルク大学にはCafé Parkという名の、ある種のアジアコミュニティカフェが存在しています。日本語学科の方はよくここで新しい日本人と出会ったり、Tandemをしてみたりするのがよく見られる光景です。店主の方も韓国人で、アジア文化に理解があるので、非常に良くしていただいています。このカフェの有難いところは、店内にあるダッシュボードでTandemパートナーを探せるところです。ダッシュボードに「Tandemパートナーを探しています」、と連絡先を記入しておくと日本に興味を持っているドイツ人から連絡が来たり、逆もまた然りです。私のハイデルベルクでの交友は全てここから始まったので、もしハイデルベルクに訪れることがあれば、一度このカフェに立ち寄ってみることをお勧めします。
最後に、簡単ではありますが、私なりの留学への全体的な感想をもって総括とさせていただきます。どちらの都市も住めば都、離れたくないほどに愛着が湧くものです。当初は1都市で1年半の留学も考えましたが、同じ国内でも「当たり前」だと思っていた環境が、都市によって大きく異なるのだと知ることができただけでも、苦労して、様々な手続きを終えた甲斐があったのではないかと感じています。私も先輩方の過去のブログを読み、こんなことが1人でできるのか、と不安を覚えていましたが、現地で助けてくれる方は沢山いらっしゃいますし、自分でやるしか方法がないとなったら、自然と身体は動きます。ドイツへの留学を考えている方にとって、このブログが気負わずに生活できる一助となれたら幸いです。