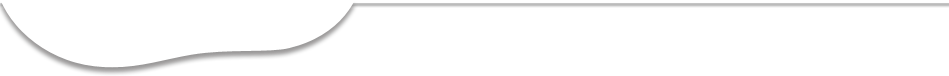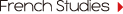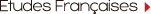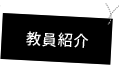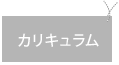わたしは三年ほど前から,週に一度か二度,やはりどうしても週末のことが多いのですが,午後の仕事が終わりこれから夕食の準備にとりかかるという短いひとときを,ひとりで,あるいは妻とふたりで,またときにはその場に居合わせた娘とともに,またあるときには遠方から訪れた友人とともに,少量のウイスキーをたのしみます.とりたててめずらしいとも言えない習慣ですが,わたしの場合は,ある方との出会いがなければ手にすることのなかったかもしれないたのしみです.そのある方とは,わたしにフランス語で作品を発表する機会を与えてくださった,今は亡きジャン=ベルトラン・ポンタリス先生です.

老師ポンタリス先生のことを日本語で書くとなると,おのずとジャン=ベルトラン・ポンタリス先生という言い方になってしまうのですが,これは実はしっくりしません.老師の名前をフランス語で表記すると,Jean-Bertrand Pontalis.高名な精神分析学者,哲学者,作家,エディター(フランス出版界の老舗ガリマール書店の編集委員会のメンバーで,「無意識の世界へ」と「その人ともうひとりの人」というふたつの重要な叢書を創設したことで知られています)として,フランスの知的世界では人々の尊敬を集め,だれからも一目置かれる存在でした.著作の表紙には,J.-B. Pontalisとファーストネームが省略形で書かれていることとも関係するのだと思いますが,老師は一般には「ジーベー・ポンタリス」と,そしてまわりの親しい人たちからは単に「ジーベー」(J.-B.をこう発音します)と呼ばれていました.わたしが,ジャン=ベルトラン・ポンタリス先生ではしっくりしないと言うのは,わたしもある時点から老師のことを「ジーベー」と呼ぶようになったからです.
2008年の9月のことだったと記憶しています.『学校の悲しみ』の翻訳をとおして親しくなった小説家ダニエル・ペナックが親友の老師を紹介してくれることになり,ペナック邸で夕食をともにしたのが,老師との最初の出会いでした.食卓での語らいは,それはそれはたのしいものでした.老師は,とりわけ,異邦からやってきたフランス語話者としてのわたしというのでしょうか,わたしのフランス語とのかかわり,いやわたしのフランス語それ自体に関心をもたれたようでした.パリから遠く離れた日本の地でフランス語を手に入れるにいたった経緯はどんなものなのか,どうして18世紀フランスなのか,そのなかでもなにゆえにルソーなのか,といったことについていろいろと尋ねられたのをいまでも鮮明に覚えています.老師は文系の学生ならば一度は開いたことのある『精神分析学事典』をジャン・ラプランシュとともに上梓した高名な精神分析家ですから,冗談まじりに言えば,わたしの「ケース=症例」に関心をいだいたということなのかもしれません.その忘れがたい夕食が終わりかけたころ,ポンタリス老師は,わたしに,「今夜の話には優に一冊の本を書くだけの材料があると思うが,どうだろう」とおっしゃったのです.最初は真に受けなかったのですが,夜中の12時が過ぎ,タクシーに乗り込んでこれから帰宅というときの別れ際に,老師は,わたしに念を押すように,「さっきの話は冗談ではないからね」とわざわざ言い残してくれたのでした.
これが,日本で生まれ,日本で育ち,東京で仕事をし,生活するわたしがフランス語で書物を発表するようになった直接のきっかけです.「今夜の話には優に一冊の本を書くだけの材料があると思うが,どうだろう」という提案から生まれたのは,『他所からやってきた言語』(2011)という著作です.わたしは,それまでも,自分自身を相手に,ひそかに———まるで戦争中に渡辺一夫が官憲の目をのがれるためにフランス語で日記をつけていたように———フランス語で文章を書いていましたが,この経験を機に,フランスの読書界を宛名人とする仕事に沈潜するようになったのです.フランス語による最初の書物『他所からやってきた言語』を準備する過程で老師とは何度か会い,議論し,アドバイスをもらう機会があったのですが,その過程でわたしは老師にTu(親しい間柄で使う二人称人称代名詞)で話しかけ,老師のことを単に「ジーベー」と呼ぶようになりました.ガリマール書店の3階にあったオフィスで,ポンタリス老師はわたしに,お互いTuで呼び合うことにしようではないか.ぼくのことを「ジーベー」と呼んでほしい,君のことは「アキラ」と呼ぶからね,ということになったのでした.
J.-B. ポンタリスに送ったふたつ目の原稿は,わたしが12年という無視できない長さの時間をともに過ごした,「犬」という普通名詞で指示するほかはないある存在=生命体の生と死をめぐって綴った文学的・哲学的文章でしたが,この原稿を読んだ老師は,大いに心を動かされたと見えて,一字一句も変えずにそのまま出版したいと言ってくれました.それが『メロディー,あるパッションの記録』(2013)です.サバチカル休暇にあたっていた2012年度のほとんどをパリで過ごすつもりでいたわたしは,『メロディー』の原稿を仕上げた直後の7月にフランスに向かったのでしたが,パリに着いた翌々日には,ジーベーのアパルトマンで『メロディー』の活字化のための打ち合わせをしていました.じつは,そのとき,老師がウイスキーを愛好していることをダニエル・ペナックから聞いていたわたしは,あるプレゼントを用意してガリマール書店のすぐ近くにあるパリ7区の自宅アパルトマンを訪れたのです.そのプレゼントとは,ほかでもない一本のウイスキーなのですが,少々変わった装いのもので,「Le Songe de Monomotapaモノモタパの夢」という名前とポンタリス老師の写真,それにラ・フォンテーヌの「モノモタパに二人の無二の友人が住んでいた.そのうちのひとりが所有するものは,すべて他のもうひとりが所有するものでもあった」という引用文が彫り込まれた品物だったのです.もちろん,そんな銘柄のウイスキーが存在するわけがありません.『モノモタパの夢』は,冒頭に「ダニエル・ペナックに捧げる」という献辞が印刷されている,ジーベーが2009年に上梓した美しい友情論です.そして,ダニエル・ペナックの名前とともに掲げられているのが,たった今引用したラ・フォンテーヌのフレーズなのです.わたしは,形の美しいウイスキー瓶を一本手に入れ,中身を抜き,ラベルを剥がし,すぐ近くでサンドブラスト彫刻工房を開いている職人の方に「モノモタパの夢」という文字とラ・フォンテーヌの引用文に加えて,老師の写真を一枚彫り込んでもらうことにしたのでした.完成した瓶を空のままフランスに携え,パリで日本のウイスキーを購入し,中身を「モノモタパの夢」に流し込み,『メロディー』出版に向けての最初の打ち合わせの際に持参したというわけです.
「モノモタパの夢」というめずらしいウイスキーを見つけたので持ってきたよと言うと,ジーベーは若干メガネを持ち上げながら怪訝そうに瓶をとって眺め,数秒後に大輪の笑みを咲かせると,これは人生で最高のプレゼントだといって喜んでくれました.その日は午後の数時間をずっと『メロディー』の話にあて,その後ジーベーと奥さんのブリジット,そしてわたしとでセーヴル・バビロンヌにあるレストランに食事に赴き,すっかり日が暮れてもうあとはそれぞれが家に帰るだけということになっても,なかなか別れがたく,バック通りとサン=ジェルマン大通りの交差点にある小さなカフェで遅くまで話しこんだことが脳裏から離れません.その六ヶ月後にジーベーが89歳で,『メロディー,あるパッションの記録』のできあがった最終的な姿を見ることなく他界したことを思うと,あの夏の日の美しい日差しの午後以降,何度も一緒にウイスキーを味わいながら交わした会話のことが思い出されるのです.
ジーベーには,毎週月曜日の6時から8時まで自宅を親しい友人に開放し,ともにウイスキーをたのしみながら,談笑する習慣がありました.わたしも,『メロディー,あるパッションの記録』以降,この「月曜会」(といってもこういう名前があったわけではありません)の仲間入りをしました.これまで,老師ポンタリス,いやジーベーについて,やや長々と書いてきたのは,じつはこの「月曜会」について話したいと思ったからです.
「月曜会」は友情の空間です.月曜日の6時から8時まで,ジーベーのアパルトマンの広い居間に,職業的にはやはり精神分析学者,作家が多いのですが,ジーベーのもっとも親しい友人たちが招待を受けることもなく集まってきて,ウイスキー一杯と簡単なつまみだけで,夕べのひとときを一緒に過ごすのです.週によって異なりますが,毎週,5人から10人ぐらいが参集するでしょうか.目的はただひとつ.ジーベーと彼のまわりに集まる人たちとの座談をたのしむためです.フランス18世紀には女性が主催する「サロン」という文芸的公共性の言語空間が存在しましたが,「月曜会」はまさに「サロン」とはひょっとしてこういうものだったのかもしれないと思わせるほど,言葉の交換をたのしむ場です.職業も年齢も性別も国籍も,その他いっさいの外的要因が捨象されて,参加している人はただひとりの個人として,それぞれの直接的な帰属集団をはなれて,そこにいるのです.人々を結びつけているのはただひとつ,ジーベーと特別に親しい関係にあるということだけです.そのことだけが接点となって,いかなるヒエラルキーに配慮することもなく,まことに多種多様なテーマについて,個別に,あるいは全員のあいだで言葉が交わされるのです.家族の近況について,構想中,執筆中の著作について,新聞・ラジオ等で議論の対象になっている映画や芝居,書物について,フクシマの原発事故について,フランスの原発政策について,現下の政治状況について,国際関係について,などなど,私的な話題もあれば,公共的な意味をもつ,つまり市民(政治)社会全体にかかわる問題もあります.「月曜会」は,したがって,友情が交換される場であると同時に,討議・議論の空間でもあるといえるでしょう.
ジーベーの「月曜会」はウイスキーを片手に週一回開かれる気軽な座談の場ですが,ふつうは食前酒に始まって食後酒におわるディナー,招いては招かれる食事の機会をとおして,このような関係を紡ぎ,広げてゆくのがフランス流の社会関係の基本だという気がします.
上智大学の法学部で教鞭をとられたこともある,日本を代表する比較憲法学者の樋口陽一先生が,『ふらんす—「知」の日常をあるく』(平凡社)という本のなかで次のような文章を綴っておられます.わたしのこの文章を読んでくださる方々のなかには高校生もいるかもしれません.そしてそのなかには,将来フランス語学科で勉強することになる方もいるかもしれません.この本は,フランスといえば,ルーヴル美術館とエッフェル塔があって,美食とファッションとサッカー,そして深刻な移民問題で知られる国ぐらいのイメージしか持っていない公算が大きい,そういう高校生にまっさきに読んでもらいたい文献のひとつです.その樋口先生の文章です.
話をグルマンディーズに戻すこととして,大事なのはみんなが集まって話をすることであって,食べ物なんか持ち寄りでいいんだ,と言う人もいます.もちろんそういうパーティーも結構ですけれども,それだけではつまらない.日本の文化を代表するもののひとつ,お茶事だってそうでしょう.亭主のあらゆる心づかい,それに応えつつ醸し出される和の雰囲気.やはり話が弾むためには,それなりの労力をかけておいしいものをつくり,それに合うお酒を考えて,それで人を招く.人に招かれたら招き返すという中で,次第に紡がれていく人間関係です.これが,一人ひとりが個であって,それが一つの公共をとり結んでいく一番の原点ではないでしょうか.
広げていえばフランス共和国という公共があります.共和国Républiqueは「公共の事」(Res publica)から来た言葉です.個が結びあって公共をつくる.広げればそこに行くのですけれど,まず食があって,飲むことがあって,人を招くことがあって,招かれたらそれに応えるまた心づかいがあって,そこから始まるのが本当の意味での「ソシアビリテsociabilité」です.それを「社交」と訳してしまうと,何だかちゃらちゃら,ひらひらしたような,社交界なんていう言葉を連想されてしまうと困るのですが,本当の意味でのソシアビリテというのかな,これが大事なのです.
食卓を囲む個が言葉の交換をとおして紡ぎあう関係が公共であり,それが最終的にはもっとも大きな公共としての共和国,「みんなのもの」という意味のres publicaというラテン語表現に由来する公共社会=政治社会=国家につながるという考え方.本来ならば,ここから話をもう少し先に進めて,個と個が結びあうというその肝心要の点を原理的に考察するために「社会契約」という政治哲学上の最重要概念の話をしたいところなのですが,それはこの文章の範囲を大きく逸脱してしまいますので,あきらめざるをえません.ただ,ひとつだけ記しておきたいのは,個と個が結びあって公共を形成するという生き方というか,あるいはその生き方を根底から支え可能にしている考え方・発想・政治的無意識とでもいうのでしょうか,それがわたしたちの生きるこの国においては伝統的にきわめて希薄だということです.日本では,公共どころか,個人や社会という言葉ですら,じつは人々の意識の根源から湧き上がってくるような,深い「経験」に根ざした言葉ではないということを学問の問題としてとりあげ,それを「世間」という主題を軸に展開し,もって日本の学問全体の根底的な批判におよぶような仕事に手をつけ,いくつかの忘れがたい著作を残したのが,ドイツ中世史の専門家,阿部謹也氏でした.たとえば,阿部氏の『西洋中世の愛と人格—「世間」論序説』には次のような言葉が読まれます.
日本人の多くは世間の中で暮らしている.しかし日本の学者や知識人は「世間」という言葉から市民権を奪い,「世間」という言葉は公的な論文や書物には文章語としてはほとんど登場することがない.「世間」という概念を学問的に扱わなければならないはずの日本史学においても,まともに世間を論じた人を私は知らない.吉川弘文館の『国史大辞典』には「世間」という項目すらないのである.現実の日常生活では世間の中でくらしているにもかかわらず,日本のインテリは少なくとも言葉のうえでは社会が存在するかのごとくに語り,評論家や学者は,現実には世間によって機能している日本の世界を,社会としてとらえようとするために,滑稽な行き違いがしばしば起こっているのである.このことは政党や大学の学部,企業やそのほかの団体などの人間関係のすべてについていえることであり,それらの人間関係は皆そこに属する個人にとっては,世間として機能している部分が大きいのである.個々人はそれら世間と自分との関係を深く考えず,自覚しないようにして暮らしているのである.
90年代以降,とりわけ21世紀に入ったころからでしょうか,デモクラシー(デモス=人民の支配)は今や危機に瀕しているという指摘が心ある人々によってなされるようになりました.デモクラシーを生み出した西欧世界での話です.事態は,一見したところ,この国でも同じように進行しているように見えます.日本は,フランス革命からちょうど100年後の1889年に,国民主権ではないにせよ立憲主義的な要素をいくらかはもつ憲法をなんとか成立させ,あの恐るべき15年戦争を経てようやく近代の自然法的・市民法的秩序とその表現としての日本国憲法をもつにいたったわけですが,現下の状況をうかがうに,それが少しも牢固とした構造体ではなく,逆にきわめて脆弱で,今や瀕死の危機に直面しているように見受けられるからです.たしかに,極度に不誠実な政治家たちの極度に劣化した言語を放置するようでは,デモスの支配など絵空事にすぎません.しかし,どうでしょうか.西欧世界による苦渋の経験としてのデモクラシーの危機とこの国における危機を同質のものと理解してもよいものでしょうか.そうではないはずです.個と個が結びあう関係が公共社会を構成するという世界での話がデモクラシーです.個も公共も社会も,したがって,じつを言えば西欧近代の政治哲学が定義するところの人民も市民も存在しないところに接木した「デモクラシー」が戦後70年たっても少しも内面化されていないことから来る危機は,また別種の問題性をもつに違いないからです.
「月曜会」にもどりましょう.
ジーベーは,2013年1月15日,89歳の誕生日にこの世の人ではなくなりました.12月19日の夜に電話で話をしたのが最後でした.じつは20日にジーベー夫妻と『メロディー』に序文を寄せてくれた作家ロジェ・グルニエと奥さんのニコルを日本料理の店に招待して,一夕を過ごすことになっていたのでしたが,ジーベーが電話を寄こして,身体の具合がよくないので,残念だが明日は無理だと言ってきたのでした.そして1月15日の悲報です.ジーベーがこの世の人ではなくなったのですから「月曜会」も当然なくなるだろうとわたしは思ったのですが,じつはそうではないので,驚きました.ジーベーが亡くなってからも,「月曜会」はじつは奥さんのブリジットを囲んで維持されたからです.わたしは,フランス語で著作を発表するようになってから,フランスやスイスで開かれる作家会議や討論会に参加するために,それに何よりも次の著作の打ち合わせのために,少なくとも年に2回はパリにやや長期の滞在をするのですが,夏のヴァカンスシーズンがあけると再開する「月曜会」には,都合のつく限り足を運ぶことにしています.ジーベーの姿はもはやなく、彼を思い出させるものといえば,アパルトマンのあちこちに飾られた彼の写真とテーブルの真ん中に置かれたウイスキーの瓶「モノモタパの夢」だけなのですが,以前と同じように,琥珀色の液体の入ったグラスを片手にブリジットのまわりに集まる人々との座談に参加し,何よりもそれを心の底から生き,たのしむためです.
わたしは,『他所からやってきた言語』の出版を機に,「経験」をフランス語で言語化する作業に自分を意識的に追い込むようになりました.それは,第一義的にはフランス語で「書く」ことを意味するのですが,「月曜会」とそこから同心円的に広がったソシアビリテを生きることも含まれています.たとえば,わたしは,ジーベーのおかげで,2011年以来,学部学生のころからの長いあいだ,その作品をとおしてただただ深い尊敬の念をいだくだけであった巨匠ジャン・スタロバンスキーと親交を持つようになりました.ジーベーはパリで,スタロバンスキーはジュネーヴですが,ふたりは互いに,「ジーベー」,「スタロ」と呼び合う仲だったのです.ジーベーが亡くなって二ヶ月ほどがたった2013年の3月にスタロバンスキーを訪ねたとき,話がジーベーのことにおよぶと,眼から涙があふれ出し,崩れ落ちるようにソファーに腰を下ろしたスタロの姿がよみがえってきます.
日本人の親から生まれ,日本で,そして何よりも日本語で育ったわたしを,徹底的にフランス語の思考と感性の,その細心・最小の襞にまで分け入る「経験」へと導くのは,究極的には,17・18世紀に始まり今日にいたるまで牢固として動かぬ近代市民法的世界の岩盤を何としても探りあて,みずから触知したいという願望です.ヨーロッパ市民社会に固有のソシアビリテの根底に降り立ち,それを「経験」化し,そこから言葉を紡ぐ作業とも言えるでしょうか.いずれにせよ,断崖絶壁に立たされている感のあるこの国とそこに住む自分を見つめる自分の心の奥底で激しく動いているのは,言語それ自体からすべてをやり直さないことには何事も始まらないのだという切迫感です.加藤周一の言葉にこういうのがあります.「東京ほどヨーロッパに関する知識の豊富なところはない.あまりに豊かでヨーロッパとヨーロッパに関する知識を区別することさえむずかしいのである.しかし経験と知識はちがう.」百万冊の知識をため込んでも白鳥の羽の上を滑り落ちる滴のような知識では,どうにもならないのです.その証拠を見せつけているのが戦後70年の歴史を経たこの国の姿ということになりましょうか.チェコ出身の小説家ミラン・クンデラのように,フランス語の外で生まれながら,表現言語としてフランス語を選び取った人たちがいます.彼らがついに言語的越境に踏み切った理由はまちまちでしょうが,日本語からフランス語への越境を内奥から生きるスリルに満ちた個人的「経験」(「経験」は重い言葉です.わたしの念頭にあるのは,すでにお気づきの方もおられると思いますが,森有正の,あの忘れがたい『遙かなノートルダム』です)のなかに,わたしは深く,深く公共的な意味を見いだしているのです.
フランス語はわたしのなかで長い時間をかけて,単なるツールであることを越えて,生きてゆくために欠くことのできない最重要外国語,いや最重要言語になりました.日本語ではついに到達することのできない「経験」の層というものがあり,その層から言葉を紡ぎ出すことこそ今やわたしが生きていることの証だからです.あと二年もしないうちに終わる教師としての仕事の核心にあるのは,そういうことを若い人たちに少しでも伝えることだろうというのが,今のわたしの到達点です.ハンナ・アーレントが恐れ,ジャック・デリダが警戒を促していたことですが,今や,大学は,とりわけ金力などの外部の力に対して無防備・無抵抗なこの国の大学は,露骨な「自動車教習所」化の磁力にさらされるようになりました.ですから,わたしが考えるような,「社会のニーズ」とはおよそ無縁な教育は風前の灯火なのかもしれません.それでもしかし,わたしはみずからの信念に背くつもりは少しもないのです.なぜそこまでフランス語に執着するのか.それは,この国に生きる人々,この国でこれからおそらくは途方もなく長い時間をかけて,その名に値する公共世界を築くという困難な作業(はたして可能なのか…)にかかわってゆく若い人々にとっても,ある意味では,フランス語は最重要言語であるに違いないからです.なにしろ,フランス語は,デモクラシーの故郷,基本的人権の思想の故郷,近代市民法(とりわけ憲法と民法)の故郷,近代人文学的教養(モンテーニュ,ラブレーからヴォルテール,モンテスキュー,ディドロ,ルソーまで)の故郷,近代市民社会の様相とそこに生きる人間を活写した教養小説(スタンダール,バルザック…)の故郷なのですから.フランス語は,間違いなく,非ヨーロッパ地域に計り知れない犠牲と苦しみを強いたヨーロッパ近代とともに生まれた言語のひとつですが,しかしその血塗られた近代を対象化する強靱な思考を生み出した言語でもあります.そのような言語が,この国の同じように血塗られた,近代ならざる過去と現在を考え,未来を透視するために役立たないはずはありません.
さて,長くなりすぎたこの文章を終えるときが来ました.
この文章を締めくくるにあたって,わたしの思いはふたたびジーベーへと向かいます.わたしはもう40年以上も前からひたすらフランス語を勉強する毎日を送ってきました.その結果,わたしの実存全体が,いまや,あるひとつの巨大な,しかし目には見えない空間,フランスという国の六角形とは少しも重ならない巨大な空間に根をおろすようになりました.フランス語で書く作業はそのもっとも重要な側面です.この内的な,したがって自由な空間を,わたしは,ジーベーにならって,「中間の王国」,「王のいない王国」,「神も支配者もいない無限の領土」としての「中間の王国」と呼びたいと思うのです.「中間の王国」がわたしにとって何にもまして貴重なのは,そこに生きることで,この日本をしばし離れ,遠くから曇りのない目で,また周囲の雑音に邪魔されることなく眺めることができるからです.そして,この点をわたしは強調したいのですが,この「中間の王国」の扉を開けることができる鍵は,わたしの場合,唯一フランス語,わたしにとっての最重要言語,フランス語だけなのです.
わたしは,今後もずっと,命のある限り,フランス語に住み続けるつもりです.