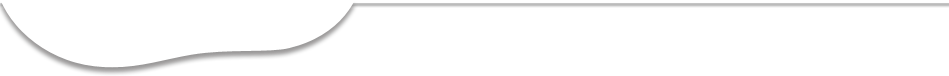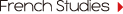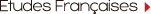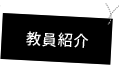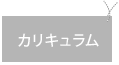2017年度、私はサバティカルで、カナダはケベック州のモンレアル(モントリオール)にて1年間を過ごしました。サバティカルとは、大学教員が一定期間勤続したあとに取得できる研究休暇のこと。大学教員の仕事は「研究/教育/大学行政」の3本柱とよく言われます。現物が今手元にないのでうろ覚えですが、1990年代に出版されたある本には、大学教員の仕事の時間配分は「研究6割/教育3割/大学行政1割」が標準的という趣旨のことが書いてあったと記憶しています。私もこれが本来の姿であり、そのほうが日本の大学の国際競争力もつくとさえ思っていますが、今はどこでも雑務が増え、時間をかけた伸び伸びとした研究が難しくなっているのが現状ではないでしょうか。サバティカル中は教育と大学行政の負担を免除され、研究に専念することができます。研究《休暇》でもあるわけなので、私も10年以上ぶりにジーンズをはいてみたり、普段は便利な大学暦対応の手帳に別れを告げて市販の手帳に予定を書き込んでみたり。それだけでもずいぶん開放的な気持ちになったものです。
もちろん《研究》休暇としての本分である研究にしっかり打ち込み、成果を出す必要もあるわけで、一定のプレッシャーと緊張感を抱えながらの生活でした。ケベックの研究環境は、フランスと比べてもよかったというのが個人的な実感です。北米にあってアメリカに近いのだと言えば、便利そうな感覚は伝わるでしょうか。大学図書館で利用手続きを済ませると、紙媒体もそうですが、インターネットでアクセスできる資料や論文が多く、研究がはかどりました。
滞在の前半は、フランスのライシテについての本の執筆に一番のエネルギーを注ぎました。「ライシテ」はフランスの歴史や社会や文化を知るうえで最も重要な概念のひとつです。共和国とは何か。宗教的・文化的背景を異にする人びととの共生を実現するには、どうすればよいのか。どのような教育が望ましいのか。近年の変化を歴史の歩みに照らしていかに評価し、新たな課題に向き合えばよいのか。このようなときには、必ずと言ってよいほど「ライシテ」というキーワードが出てきます。さらに言えば、国のあり方や公的な社会制度だけでなく、個々人の生き方を支える価値観やセクシュアリティなど、私的な生活における事象でも、現代フランス社会の問題を多少なりとも掘り下げていくならば、早晩「ライシテ」という言葉にぶつかることになるでしょう。
ライシテはよく、「フランス独特の厳格な政教分離」と説明されます。公的な場におけるイスラームのスカーフの着用規制が典型例として挙げられることが多いです。「かつてのライシテの敵対相手はカトリックだったが、現在はイスラームになっている」という指摘が、それなりに的を射ていることはたしかです。そして、「政治と宗教を分けるライシテの発想は、キリスト教にはあるがイスラームにはないので、フランス社会がムスリムと共生することは困難だ」といった物言いに、説得力があるように見えてしまったりもします。日本とは大分事情がかけ離れているので、日本との関連性は薄いと思われるかもしれません。
このように評価される現象があり、説明の根拠に一定の妥当性があることを否定するのは難しいのが現状です。けれども私は、ただそれを追認するのではなく、それに挑戦し、部分的にでも修正する必要があると考えてきました。それを『ライシテから読む現代フランス--政治と宗教のいま』(岩波新書、2018年)にまとめました。新書なので、ライシテについても、現代フランスについても、特段の前提知識なしに読める本であることを目指したつもりですが、ライシテについて聞きかじっただけだと、つい抱きがちな通念の裏をかき、理解の地平を押し広げることも狙ったつもりです。手に取って読んでもらえたら幸いです。
滞在の後半は、ケベックのライシテ研究に重心を移していきました。フランスとケベックの比較研究をそろり、そろりとはじめたのは、もう10年近く前になりますが、最初は右も左もわからず、振り回されていました。ケベックには何回も足を運んでいましたが、今回のサバティカルが初の長期滞在となり、だいぶ研究の土地勘がつきました。
研究対象の近くに身を置くことも、そこから身を引き離して距離を取りながら考えることも、どちらも大切です。何が当事者たちにとっての論点であるかを理解するには、やはり現地の空気を吸い、定評のある研究を押さえ、生身の人間に接することが欠かせません。けれども、それだけでは現地の専門家には到底敵わないことが明らかです。そこで、日本の学術研究の文脈における切り口を意識して利用するということにもなってきます。
ここでは感覚的な言い方しかできませんが、2000年代に5年間を過ごしたフランスから眺めた日本像というものが私のなかにはありました。今回、北米のフランス語圏に住んでみて、また違った日本像が見えてきたような気がしています。そのようにして感覚的に掴んだと思えるものを、少しずつ研究の場で具体的な成果として出していければと念じています。
ケベックはカナダの一州ですが、北米のフランス語圏として「独自の社会」を自任しており、英系カナダや連邦政府の考え方と似ているところもあれば、ずいぶん違うところもあります。類似と差異は、ケベック(およびカナダ)とアメリカ合衆国との関係についても言えます。ケベックらしさの把握は、イギリスらしさ、フランスらしさ、カナダらしさ、アメリカらしさの把握と連動しているところがあるので理解が深まります。
日本のフランス語学習者は、英語を第一外国語として学習したうえで、大学からフランス語を第二外国語として選択して勉強するケースが圧倒的に多いわけですが、留学先としてはやはりフランス志向が強く、ケベックを思い浮かべることは比較的少ないようです。ところで、モンレアルは英仏二言語の街と言ってよく、英仏語を学習する日本人留学生をもっと引きつけてもいいような気がしています。それを阻害する要因として考えられるのは、ケベックのフランス語がしばしば訛っているとされること、そして冬の厳しさでしょうか。
ケベック訛りにも度合いがあります。ある程度は聞けて話せたほうが、フランス語力があるということになるのではないでしょうか。長く厳しいと言われる冬ですが、実際に過ごしてみると、冬の表情の多様さにも打たれます。それでも春の訪れが待ち遠しいというのが通常の感覚なのでしょうが、今年の私にかぎっては、春の足音がサバティカルの終わりを告げる合図に聞こえて、まだまだ冬が続けばいいのにと思えて仕方ありませんでした。
『ライシテから読む現代フランス』岩波書店のページ
*目次と冒頭数ページが見られる「立ち読みPDF」もあります。