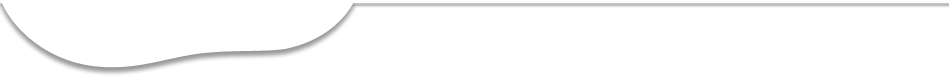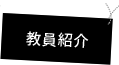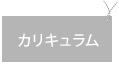教員BLOG
-
Why the Elderly Rule the Gym
2013/06/30Every time I visit my local gym in Minatomirai, I am both surprised and impressed by the number of elderly patrons swimming laps, taking yoga lessons, pumping iron, and generally taking care of their bodies through regular exercise. The blue-haired, tank-topped, spandexed sexagenarians at my gym are dynamos; they aerobicize, handle the weight machines like pros, and have forged a tight-knit community dedicated toward healthy living. But where are the gym rats of the younger generation? While I have observed a fair number of men in their 20s and 30s hitting the weights at my gym, the young female population is largely non-existent. In talking with one fitness trainer, I <続きを読む> -
PechaKucha Presentations
2013/01/29The academic year is drawing to a close and first year students in my English Skills class have been making presentations. For the final presentation I asked them to use Power Point. However, experience has taught me that students often struggle the first time they try to make a presentation with Power Point. They tend to include too many words and too much information on the slides. Many of them simply present their script on the screen, not really understanding how to best exploit this type of visual aid. To help them with their presentations, I introduced the class to PechaKucha. PechaKucha is a style of presentation created by two <続きを読む> -
留学前準備の賜物
2012/11/29英語学科で主に応用言語学系の科目を担当している和泉です。今日(11月23日)は勤労感謝の日であるにも関わらず上智大学では授業実施日となっており、普段通りのスケジュールで授業を行いました。休日出勤でいいのは通勤電車が空いているということですが、大学に着くまでは「今日は本当に大学の授業はあるのかな」と少し変な感じを持ちながら出勤しました。でも、大学に着くと、いつも通りのにぎわいで何かホッとしています。 さて、つい先程、応用言語学のゼミの授業を終えて研究室に帰ってきたところです。このゼミでは、学生の興味やニーズに合った形で様々な応用言語学トピックについての論文を読み、それを学生主体で発表してもらい、意見交換をしながら話を深めていくというスタイルを取っています。今日の主題は、「留学の効果とその違いはどこから来るのか」でした。 とかく留学と言うと、多くの人は過大な期待を持っていることが多いようです。例えば、「留学すれば、必ず英語がペラペラになる」だとか、「ネイティブのような発音や表現が身につく」、はたまた「金髪で青い目の彼女・彼氏ができる」等々。彼女・彼氏の話は別として、英語能力の進展に関しては、実際は必ずしも思ったような成果が得られない場合が少なくないようです。「ペラペラ」とは何を差して言っているのかが不明確な場合も多いです。日常生活に不自由しないというレベルから、大学の授業でディスカッションやディベートが行われる際、現地の学生に引けを取らないくらい議論に参加できるというレベルまであるでしょう。日常生活に不自由しないと言っても、どれくらい複雑な内容が扱えるのかといったら、それも随分差が出てきます。例えば、普通に買い物ができるといったレベルから、釣り銭をごまかされそうになった時に抗議できる、交渉できるといったレベルまで様々です。いずれにしても、そのようなレベルでも留学の成果としての個人差はそれなりに出てきます。学問的な分野での高度な英語能力の獲得では、それはなおさらです。 さて、それでは留学の成果の違いはどこから来るのでしょうか。今日のテーマの元となった論文の著者であるRobert DeKeyserは“Study abroad as foreign language practice”という論文の中で、次のように言っています。すなわち、留学の成果の違いは、留学した最初の時点でその人がどこまでの英語運用能力を獲得しているかということが一番大きな原因になっている。もし初心者の学習者が留学するとどういった状況に陥りやすいかと言うと、こうなります。他の人の言っている英語が聞き取れない、自分の言いたいことが何も言えない、じっと黙って我慢していることが多くなる。友達がなかなかできない。精神的に追いつめられる。日本人、日本語が恋しくなる。結果、外国にいても日本語で暮らせる環境を求めてしまい、日本人同士でつるんでしまう。自分の回りにLittle Japanをどうにかして築き上げてしまう(外国にいても、実はこれって思ったより簡単にできてしまったりするんですよね)。 英語を使う状況に遭遇した場合は、どうしてもコミュニケーションのプレッシャー(時間的制約、状況的制約等)が強くなりやすいため、決まり文句(例えば、I see. Could you ~? What’s that?等のチャンクで使える言葉)を多用することが多くなる。なかなかこれまで習ったはずの高度な英文法などを駆使して話すチャンスが得られない。結果、「ペラペラ」になると言っても、決まり文句程度の日常英会話ぐらいしか身につかず、限定的な「ペラペラ」となってしまいがちである。このような状況は、まだ英語運用能力がそれほど身についてない初心者が比較的短期的なプログラム(数週間から1年程度)に参加した場合によく起こる現象である。つまり、一般的に信じられているような、「留学すれば必ず英語が上手くなる」というのは必ずしも本当ではないのです。 留学経験を最大限に活かすためには、それなりの準備が必要であり、理想的には少なくとも中級程度の英語運用能力を既に獲得している必要があるというのがDeKeyserの主張です。ここで大事なのは、英語運用能力という言葉で、それは単なる文法を「知っている」という静的な知識のことではなく、それをスピードは多少遅くとも少しは使えるという実践的な能力です。そういった能力が留学最初の時点からあると、それをフル活用して留学経験で面する様々な日常生活での英語使用場面だけでなく、より高度な学校/大学での英語使用場面でも役立たせることができるのです。それでこそ、留学環境を「心地よくチャレンジングな環境」とすることが可能になるのです。 このあとの議論もまだまだ細かくあるのですが、今日のゼミの授業ではこういった話について学生同士の議論を交えて話を進めていきました。後半のディスカッションでは、「では、日本にいる時にどういった準備をすればいいのか」、「英語教師は生徒のためにどういったことをしてあげればいいのか」といった、学習方法、教育方法へと話が進んでいきました。そこで特に印象に残ったのが、一人の生徒が確信を持って言った次の言葉です。「英語学科で最初は守られつつもチャレンジングな環境で自分自身を充分鍛えてから留学すればいいのではないでしょうか。私はそのおかげで充実した留学経験ができました。」少し英語学科の宣伝じみた話になってきてしまい恐縮ですが、上智英語学科では毎年多くの学生が留学します。私の知る限り、1年間弱という比較的短い留学期間でも、確かに皆さんかなり英語の力をつけて日本に帰ってきます。気持ち的にも、自信を深め、留学前よりも堂々と臆することなく英語を駆使して自分の意見を言ったり、また何十ページもの英語論文を書いたりするようになります。これもDeKeyserの言う、留学前準備の賜物と言えるのではないでしょうか。 長くなりましたが、ちなみに、これらのディスカッション・講義は全て英語で行われたということも付け加えておきます。I hope you will join us and share with us your ideas in the near future!! Best wishes, Sean Izumi<続きを読む> -
9.11の記憶
2012/11/259.11の記憶 みなさん、こんにちは。今回teacher_blog担当の出口真紀子です。みなさんは、2001年9月11日には何をしていたか覚えていますか?まだ幼かったでしょうから特に記憶がないかもしれません。当時、わたしは大学院生で、アメリカのボストンという街に住んでいました。その日は、とても緊張していました。なぜなら、大学で初めて自分の授業を持たせてもらったばかりで、その日がまだ二回目の授業の日。先生としての経験が浅いわたしは、どのように授業を進めていいのかがわからず、朝から固まっていました。 午前9時半ぐらいでしょうか。まだ自宅にいたわたしに、東京で朝日新聞記者をしている友人から突然国際電話がかかってきました。「今すぐテレビをつけて!」友人は切迫した様子で叫んでいます。私は日本に大地震でも起きたのかと、慌ててテレビをつけると、ちょうどニューヨークの世界貿易センタービルに、航空機が突っ込む映像が目に飛び込んできたのです。後でわかったのですが、その航空機は、世界貿易センタービルに突っ込んだ二機目だったのです。 何が起こったのかすぐには理解できず、テレビの報道を追ってしばらくすると、まさにニューヨークの象徴である世界貿易センタービルの二棟が跡形もなく崩れ落ちてしまったのです。とても現実とは思えぬ展開にただ呆然としていました。また世界貿易センタービルに突入した航空機は二機ともボストン発(ロサンジェルス行き)の便だということがわかると、「次の標的はボストンではないか」とボストン住民たちもかなり動揺していました(結果的に無事でした)。こうした事件の一連が「アメリカ同時多発テロ事件9.11」と呼ばれるものだったのです。犠牲者はおよそ2,900人でした。 このように、9.11はわたしが初めて教えた学期の始まりと重なったことからも、深く記憶に刻まれています。また、この事件はアメリカという国自身のアイデンティティを大きく揺さぶりました。多くのアメリカ人は「Why do they hate us so much?」と自問するようになり、そして国自体は政治的にも社会的にもどんどんおかしな方向に進んでいくのです。次回はテロ事件直後のアメリカ社会におけるアイデンティティの揺らぎとその教訓について書こうと思います。(出口真紀子)<続きを読む> -
日本のなかのリトル・ブラジル
2012/11/15みなさん、こんにちは。今回のteacher_blog担当の飯島真里子です。私の「太平洋日系移民史」の講義では、戦前、海外に渡った日本人移民の歴史と日系人の文化について学びます。「日系人ってどんな人たちなんだろう?どんな文化を持っているんだろう?」と疑問を持つ学生も多いので、一年に一回、日本のなかの日系コミュニティ見学にいきます。下の写真を見てください。みなさんは、どこだと思われますか? (飯島撮影) これは、群馬県の大泉町で撮影されたブラジルスーパーの写真です。大泉町は、全人口の15%を外国籍者が占め、その大部分がブラジルからやってきた日系人です。大泉には、パソソニック、富士重工、味の素などの大企業の工場があり、日系人はそのような工場や近隣の町(館林や太田など)のお弁当屋さんなどで働いています。日系人のほとんどは、1990年の入管法改正を機に日本にやってきて、リーマンショック、東北大震災を経験しながらも、日本で長期間住むことを決めた人々です。 日本にやってくる日系人は、日本人移民の子ども、孫の世代で、必ずしも日本語が流暢とはいえません。また、「血統的」に日本人であっても、ブラジル生まれ・育ちであるため、日本で住み始めた時のカルチャーショックは大きいのです。さらに、工場での重労働、日本人社会からの冷たい目、連れてきた子どもたちの教育など、日本で生活してみると多くの問題が発生します。そのような問題を解決する手助けをしているのが、今回学生と訪ねた際にインタビューさせて頂いた大泉日伯センターの創立者高野さんご夫妻です。高野さんご夫妻も、戦後ブラジルにわたり、1980年末に日本に戻ってきた元ブラジル移民です。1990年代、増加する日系人問題に心を痛め、日系ブラジル人子弟のための教育機関「日伯学園」(現在生徒数120名)も設立し、現在、センターは大泉ブラジルコミュニティと地元社会を結ぶ「架け橋」的存在となっています。 (大泉日伯ブラジルセンター、飯島撮影) 様々な問題を抱えている一方で、日系ブラジル人の日常生活の支えとなっているのが、ブラジルの商品を売るお店です。西小泉駅から5分ほど歩くと、ブラジルの食材や服飾品を売るお店が7-8軒ほど連なっています。私たちはいくつかのお店に入り、店員の方とお話をしたり、ポンデケージョ(ブラジル風チーズパン)を味見させてもらったりしました。ここでは、私たち日本人が「マイノリティ(少数派)」となり、日系ブラジル人が「マジョリティ(多数派)」となります。しかし、日系ブラジル人の人々は、私たち(マイノリティ)を温かく迎え入れ、積極的に話しかけてくれます。逆に、日本社会でマジョリティである日本人は、マイノリティの人々を同じように迎え入れているのだろうか、というような疑問がふと頭をよぎります。 今回の大泉の滞在時間は5時間ほどで、コミュニティを理解するには不十分です。しかし、この少しの滞在だけでも、五感を通じて、色々な情報を得ることができます。また、「マジョリティ」から「マイノリティ」への立場の転換は、私たちが日頃見過ごしてしまう社会的な問題を気づかせてくれますし、心がかよったコミュニケーションの大切さを教えてくれます。東京から約2時間半-是非リトルブラジルに足を運んで、日本のなかの移民コミュニティを体験してみてください。(飯島真里子)<続きを読む> -
Filming the Tempest
2012/11/09At the moment I’m pretty busy preparing for the release of my new film, Sado Tempest which will be shown in Eurospace in Shibuya from February the 16th of next year. Sado Tempest played in the Raindance Film Festival in London in October this year. There it was described as “gloriously demented.” I hope this is a good thing. You can see an interview with me at the following link, or if you google Sado Tempest, Raindance Film Festival. Sado Tempest is a rock musical version of Shakespeare’s last play, The Tempest (Arashi in Japanese). It might sound difficult, but actually the film is pretty easy to understand and I <続きを読む> -
教員のBLOG
2012/10/31英語学科にはとにかく女子学生が多い。第一回目となるteacher_blogはできれば女性を(もちろん男性も)元気にするお話をしたいと考えました。古居みずえ監督のドキュメンタリー映画『ガーダ―パレスチナの詩』(2007)は逞しい女性たちの物語。生きていく勇気がもらえます。 このドキュメンタリー監督の古居みずえ氏は、37歳の時、原因不明の関節リウマチに襲われ、1ヶ月後には歩行器なしで動けなくなりました。「もうだめだ」、と諦めかけた時、投薬した薬が奇跡的に効いたのだそうです。「一度きりの人生。何かを表現したい。」その時、古居氏は普通のOL生活から女性ジャーナリストとしての再出発を決意します。彼女は心機一転パレスチナの地へ。ハンユニス難民キャンプでガーダという若い女性と出会いますが、彼女はパレスチナの紛争に巻き込まれながらも、力強く生きる道を模索している女性。 古居監督は「パレスチナの人たちの素顔を伝えたい」という思いで、長年にわたり、彼らの生活、戦場、信念を貫く姿をカメラで追い続けました。1988年、イスラエルの占領に反対するパレスチナ人の抵抗運動(インティファーダ)が起こっていたころに、ガーダとその家族の記録を撮り始めた彼女は、2004年までそれを継続しました。その間に、ガーダは結婚し、ガザ地区に引っ越します。長女ガイダに続いて、長男ターレックを出産し、母親となるのです。しかし、2000年には第二次抵抗運動がおこり、わずか13歳であった甥カラムがその犠牲となります。武器のない市民も石を投げることで抵抗に参加していたので、「石の闘い」とも言われていて、カラムが銃で撃たれたのはその最中でした。 ガーダはこの出来事をきっかけにパレスチナ人のアイデンティティや歴史を守っていく必要性を強く感じ、1948年の戦争を生きた女性たちをインタビューし、本に書くことにします。古居氏はガーダのその活動の一部始終をカメラで追います。ガーダはもともと向学心があり、結婚しても大学に通いながらパレスチナの歴史や政治情勢について研究すること続けてきました。彼女が出会った女性たちの声を通して、パレスチナが他国に次々と占領され、土地を略奪されてきた民だということが伝えられます。 80歳にもなるガーダの祖母ハディージャは、その昔、故郷の地ベイトダラスの土地で野菜や果物を作り幸せに暮らしていましたが、戦争がはじまり、そのすべてを置いて逃げだします。ガーダが初めて農民ウンム・バシーム(67歳)から話を聞いたのは2001年ですが、そのころはまだ自給自足生活が送れていました。オレンジの木や花が咲き乱れ、昔の生活様式をそのまま残していました。夫がウンム・バシームへの愛を歌で表現するのが印象的です。 「日が沈み、月がでて、 ずっと口付けしていても思いはつきない たとえなにが起ころうとも あなたから離れたくない ウンム・バシーム 君はとても大切な人 死ぬまでずっとあなたを愛する 私の愛するあなた」 しかし2002年には、イスラエル軍によって土地も畑も奪われてしまい、ウンム・バシームの生活は大きく変わります。 ハリーマの場合は、2台のブルドーザーに家を壊されてしまいます。彼女はこのような占領が自分たち苦しめ、アラブを苦しめるのだ、と訴えます。「最初の占領はトルコ、次はイギリス。いろんな国が来たけど今のイスラエルほどではない」という彼女の表情は悔しそう。近年になってもイスラエル軍はガザ地区南部にある入植地に隣接したパレスチナ人の家を破壊することがあります。これによって多くのアラブ人たちがテント暮らしを強いられました。 2001年の9.11以降、アフガニスタン戦争、イラク戦争などに対して、アメリカがアンチ・テロリズムをスローガンに掲げる時代に突入してから、パレスチナの抵抗運動が「テロ」という範疇に入れられ、日本のマスコミによって伝えられました。この『ガーダ』というドキュメンタリー映画を見た後では、日本のマスコミから流れてくるパレスチナ像はあまりに偏っていると感じます。産み、育む女性たちの力強い生き方がテーマとなっているこの映画は、日本にいる私たちにもいろいろと考えさせてくれます。(小川公代)<続きを読む>