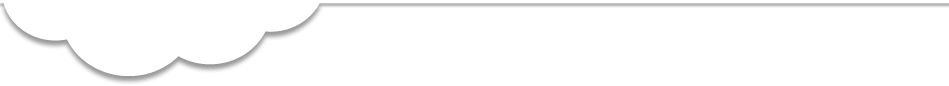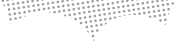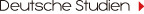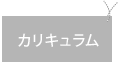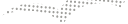畑で溶けだした煩悩
私は大学を卒業してから、ほぼ10年ごとに仕事を変えて、現在は4つ目の職業として自宅のある相模原市で有機栽培の専業農家をやっています。67歳です。
そのような風変りな人生を振り返って、人生の節目で起こった出来事にスポットライトを当ててみようと思います。それがこれから社会へ旅立つ皆さんの何らかの参考になれば幸いです。
私は最初は普通の企業に就職して、そこで12年間働きました。その会社はカーステレオのメーカーでしたが、その間、ドイツに4年間駐在しました。そして、現地で出会ったスイス人と結婚し、2男を授かって1983年に30歳で日本に戻ってきました。そして、その4年後に会社を辞めることになりました。辞めた直後に畑で体験したことを書いてみたいと思います。
今からもう40年以上も昔、私がまだ中学、高校だった頃、農家はかなり蔑視されていたように思う。高校時代、車窓から田畑で働く農家を見て、私は心の中で「かわいそうになあ。あんな仕事をやらされて」と思っていた。同情というより、軽蔑していたのをはっきりと覚えている。私の当時の関心はただただ有名な大学に入ることだけだったので、農業のことなど全く関心がなかった。だから、当時の普通の高校生ならきっと私と同じように思っていたに違いない。農業と聞けば、よく3kとか言われるように、“きつい、きたない、くるしい”とか“くさい”とか、とにかく全然良いイメージがなかった。だから、絶対にやってはならない職業だぐらいに思っていた。だから、私と同じ60歳前後の連中は総じて農業に関心がない。
農業には無関心な私ではあったが、私は食養(マクロビオティック)と出会った。そこから、有機農業に強い関心を抱くようになって、関東で有機栽培をやっていた農家を訪ねて回った。そして、弟子入りしようかと訪ねて行った有機栽培農家から「素人だって野菜は育つよ。」と言われたことが励みになり、自力で有機栽培の野菜作りを始めた。それは確か昭和60年(1985年)のことだった。当時はまだ有機農業に取り組んでいる農家は非常に少なくて、農薬の害は知られていても、その便利さゆえに大いに使われていた。有機肥料を作る手間暇そして重労働を考えると、化学肥料は実に簡便で、なおかつ即効性があって、外見は実に見事な野菜ができることから、農家は敬意を込めて「金肥」と呼んでいた。農薬、化学費用全盛の時代だった。
私が借りた畑は150坪ぐらいあったろうか、まだ会社に務めていたので、もっぱら土日に通い詰めた。野菜の栽培の仕方は周りの農家に教えてもらうこともあったが、彼らの話は化学肥料が前提なので、あまり役に立ったことはなかった。私の先生はもっぱら『無農薬でつくるおいしい野菜』(1985年、夫人の友社)だった。その本で書かれていることを唯一の手掛かりに野菜を育てた。その本には素人でも分かるように無農薬栽培に必要な知識が万遍なく載せられていて、具体的な栽培の仕方は図解入りでとても丁寧にわかりやすくまとめらている。素人の私は畑に行くときは必ずその本を持って行って、わからない所はその場で広げて読んでから作業に当たった。汚れた手で何十回、何百回とめくったので、最後にはすっかり泥だらけになってしまい、雨にも何度か当たって、シワシワで、ゴワゴワになってしまった。
脱サラしたその日から、「もう一人の自分」が私を責めたてた
その畑で一所懸命農作業に取り組んだのは会社を辞めて、日本語教師の勉強が本格化するまでの4年間ぐらいだった。1987年に会社を辞めた時のことは今でも忘れない。5月に辞めたのだが、その翌日からは毎日せっせと畑に通って、汗だくになって耕した。ところが、耕していると、「もう一人の自分」が執拗に質問を繰り返えしてくるのだ。私はそれに必死で答えなくてはならなくなった。
「どうして会社を辞めたんだ。」
「会社は努力しても評価されないし、失敗しても責任を取らなくていい。信賞必罰がないから、社員は緊張感がない。」
「それなら、能力のないお前に打ってつけじゃないか。」
「何を言うか。自分はそんなに無能じゃない。だけど、あんなぬるま湯につかっていたら、自分もふやけてしまう。」
「周りに感化されてしまうようじゃ、所詮お前は大した人間じゃない。」
「いいや、一人で頑張っても限界はある。みんなが緊張感を持って切磋琢磨するから、会社は伸びるんだ。あそこにはそんな雰囲気がなかった。」
「ふーん。しかし、たったそれだけの理由で辞めたのか。」
「いいや、会社の技術力もたいしたことはないから、将来性もないと思った。」
「会社の役員でも、技術者でもないのにどうしてそんなことがわかるのか。」
「そりゃあ、技術の人間と付き合って入れば、それくらいのことはわかる。」
「わかるわけがない。お前は全くの素人だ。」
「いや、そんなことはない。例えば、ドイツのB社の製品の回路とあの会社の同格の製品の回路を比べれば、あの会社のは配線がごちゃごちゃしている。B社のは実に整然としていて、線がずっと少ない。そこに技術力の差がはっきり見て取れる。」
「しかし、お前の会社の製品は市場シェアが一番高いぞ。それだけ優れた製品があるからだろう。」
「確かに今はそうだ。しかし、自分は将来のことを言ってるんだ。」
「そうか。しかし、会社の将来性は、技術力だけでは決められないだろう。辞めた本当の理由は何なんだ。」
「理由はたくさんある。」
「例えば,何だ。」
「自分は営業の仕事に向いてない。」
「どうしてそう思うんだ。」
「営業の連中は、夜に客と一緒に飲み食いする時に俄然活気づくような連中だ。2次会、3次会と行って、午前様になるのを自慢するような連中だ。そんなことには何の関心もない。」
「しかし、それはむしろ”お遊び“の部分で、営業の大事な部分じゃないだろう。」
「たしかにそうだ。自分は残念ながら会社の製品を売ることに楽しみを感じない。」
「何を言ってるんだ。楽しいから、会社に勤めてるんじゃないだろう。食うために努めてるんだろう。子供が3人もいるのにこれからどうするつもりだ。」
「子供たちのことは自分も考えた。」
「本当に考えたのか。」
「考えた。」
「日本語教師で食っていけるのか。」
「たぶん食っていけると思う。」
「たぶんで済む話か。子供二人を育てるだけでも大変なのに、お前は3人もいるんだぞ。そんないい加減でお前は親の責任を果たせるのか。」
「責任はちゃんと果たす。」
「どうやって果たすんだ。日本語教師の収入では3割以上減るんだろう。それで子供を育てられるのか。」
「確かに収入は減る。しかし、これから日本語を学ぶ外国人はどんどん増えるから、日本語教師の給料もきっとよくなっていく。」
「どこにその保証があるんだ。」
「保証はない。」
「だったら、どうしてそう言えるんだ。」
「あくまで見通しだ。」
「それじゃ、当てにならない。世の中そんなに甘くないぞ。」
「自分は健康のことは大丈夫だ。健康でさえいれば、何とかなる。」
「何とかならないから、こう言っているんだ。」
「いや、なんとかなる。日本語教師で食っていけなかったら、他のバイトをする。なんでもやる。」
「新米教師にそんな時間があるのか。」
「それはわからない。」
「わからないなら、そんな口は利くな。」
「もう一人の自分」はこういった口調で自分を攻め立てた。むしろ「私」よりずっとしっかりしていたかもしれない。たしかにそうだった。私が会社を辞めた同じ月に3人目となる長女が生まれた。私は生まれたばかりの長女の顔を覗き込んだときのことを今でもはっきりと覚えている。しかし、私は正直こんな思いでその赤ん坊の顔を見つめていた。
「この子は果たして10歳まで育てられるだろうか。」
私がその時から勉強を始めようとしていた日本語教師は当時はまだ職業として確立されてはいなかったので、食っていけるという保証はどこにもなかった。しかも、私は一から勉強し直さなければならない。だから、当分は僅かな貯金とわずかな退職金を食い潰すしかなかった。それで生活が成り立つのか。家族を養っていけるのか。それを心配した「もう一人の自分」が私にしつこく詰め寄ったのだ。
来る日も来る日も畑で同じことが繰り返された。2週間も同じことが続くと、自分の頭の中で毎日繰り返される尋問と答弁にうんざりしていた。
煩悩が大量の汗となって溶けて流れ出た
そうして自動問答機が作動し始めてから1か月ぐらいがたったころ、さすがに「もう一人の自分」は疲れたのか、それとも飽きたのか、追及が弱まってきた。詰問の頻度も少なくなってきた。そうして2か月もすると、「もう一人の自分」はとうとう黙り込んだ。
「ああ、やれやれ。どうやら終わったらしい。」
私は深いため息をついた。
私は会社を辞めるということが自分にとってそこまで重大で深刻な事態だとは知らなかった。とんでもないことしてしまったのかもしれないと思った。しかし、もう後戻りはできない。前に進むしかない。そう決意して、7月の炎天下で、私は毎日畑で無我夢中で体がびしょびしょになるまで汗を流し続けた。
それから何か月か経った頃、私はふと気が付いた。「もう一人の自分」とは、私の潜在意識に巣食っていた煩悩だったのだと。小市民として生きるための、小賢しい知恵と言っても良い。それが論戦地獄の2か月の間に汗となって溶けだして、大地に吸い取られていったのだ。それ以来、私は思考の仕方が以前よりも単純明快になり、うじうじすることがなくなった。そして、間違いなく金銭に対する執着が減って、以前よりずっと世間体を気にしなくなった。その分、心は束縛が無くなって、自由になった。
田畑で汗を流して、肉体と精神のバランスを取り戻す
コロナ災害の時代、脱サラして農家になりたい人も少なくないだろうから、このような私の体験も参考にしていただきたい。確かなのは、田畑で汗を流すと、足裏から体に大地の気が入っていく、ということ。頭の中のごちゃごちゃしたや悩みやストレスなどが大地の気によって溶かし出される。あるいは精神の不純物を大地が吸い取るのだろう。すると、顔の表情から緊張が取れて、柔らかくなる。つかえていた気持がすっきりする。だから、ストレス社会に息づまるような思いをしている現代人は週に1回ぐらいは土に触れて、体と心の不均衡を正したらいいと思うのだ。土は大いなる癒しの力を持っている。
そして、思い切って会社を辞めて、無心で畑で農作業をやっていると、ついには現代社会の歯車の中にすっぽりと組み込まれてしまっている「自分」を支配し、束縛していた価値観や固定観念や常識なるものの集合体、すなわち煩悩から開放されることもあるのだということをぜひ知っておいていただきたい。