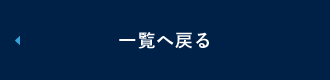授業紹介:グローバル・スタディーズ入門

教員からのコメント Comment of Professor
グローバル・スタディーズ入門は、文字通り総合グローバル学部での学びの入り口です。わたしたち(教員も、学生もです)は戦争・紛争、経済、貧困、教育、ジェンダー、さらにはこれらに限らずさまざまな社会課題にかかわる研究を進めることになります。しかし多くの場合、ひとつの学問領域(=ディシプリン[discipline]と呼びます)から問題の性質を十分に理解することはできませんし、問題の理解ができなければその解決を目指すことも当然できません。もっといえば、漠然と「戦争」や「貧困」といった問題を取り上げてみても、その具体的なあらわれかたは国によって、地域によってまったく異なることもあります。複数の社会課題が実はつながっていた、ということもしばしば起こります。こうした複雑な社会課題にアプローチするためには、さまざまな学問領域から多角的に問題の実像に迫っていくことが重要になるのです。
総合グローバル学部の「グローバル・スタディーズ」はこのような考え方に基づき、大きくみれば国際関係論を中心とするグローバルな視点と、地域研究を中心とするローカルな視点を重ねあわせるかたちで構成されています。さらに細かくみていくと、このような視点は政治学、経済学、社会学、歴史学、人類学、ジェンダー論、教育学など、多様な学問領域によって成り立っています。この講義では、こうした多様な学問領域に広く触れることで、学術的に地球規模課題を分析していくために取りうる選択肢を考えていきます。そのうえで、これからさまざまに習得していくことになる学術的方法論を組み合わせ、あるいは取捨選択していくことで、自身が関心を持った課題に対してもっとも有効なアプローチを組み立てるための思考を身につけることが最終的なゴールです。
学生からの声 class interview
① 授業概要
地域研究、政治学、経済学、社会学、歴史学、人類学、ジェンダーなど、幅広い学問分野の視点から世界で起こる課題について考える科目である。それぞれの学問からの課題への見方や、各学問がどのように発展してきたのかを学ぶ。問いを立て、それに対して複数の視点から考える姿勢が重視されている。
② この授業を履修しようと思った理由
この授業は1年次必修科目であるため履修した。各回に違う教員が専門分野について話すことによって多様な学問分野に触れながら、結果的に自分の興味や関心を探るきっかけになった。特に関心を持った分野や教員の講義は、その後の履修計画や研究テーマの選択にも直結し、今後の学びへとつながる授業だと感じている。
③ この授業の魅力
特に印象深かったのは、最後の授業での教員同士のディスカッションである。普段の授業以上に、教員の問題意識や熱意に触れることができた。「スラムは解消すべき問題か」「宗教は紛争の本質的原因ではない」「教育で貧困から脱出できるほど単純ではない」といった議論を通じて、自らの常識を問い直す視点を養った。
④ この授業で学んだことを次にどう繋げたいですか
この授業を通して、近代化がもたらす負の側面についても理解を深めることができた。こうした学びを経て、社会問題は個々の対象に内在するのではなく、それを生み出す社会構造にこそ根本的な要因があると考えるようになった。この視点は、今後の問いの立て方や研究の方向性を考えるうえで重要な基盤となる。
(吉川真由 総合グローバル学部1年生)

① 授業概要
本授業では、世界と地域をつなぐ広い視野で地球規模の課題を考える力を身につけるための、基礎的な知識を学ぶことができます。政治や経済、社会、歴史、文化、ジェンダー、紛争など多様な分野を横断し、学ぶことで、一つの物事を多角的に見る姿勢を身につけることに役立ちます。
② この授業を履修しようと思った理由
入学したての頃、地域研究や国際関係論についての知識がほとんどなく、この学部でどんなことを学ぶことができるのか詳しく知りませんでした。そんな時にグローバル・スタディーズについて初歩的なことから学べるこの授業の存在を知り、受講することに決めました。
③ この授業の魅力
授業ごとに異なる専門の先生の講義を受けることができる点が大きな魅力です。総合グローバル学部に所属する先生方は、それぞれ研究されている地域や文化が大きく異なり、どの先生の授業もとても面白くたくさんのことを学ぶことができます。
④ この授業で学んだことを次にどう繋げたいですか
物事をグローバルな視点とローカルな視点の両方から見ることの重要性を学ぶことができ、大学生活を送るにあたっても大切な視点を得られたと感じています。与えられる情報を享受するだけでなく、自ら学ぶ姿勢をとることを心掛けていきたいと思います。
(関根真帆 総合グローバル学部1年生)