
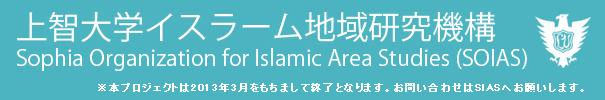

活動報告
文科省公募事業SOIAS
上智公募研究SOIAS「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」第3回研究会
報告者:多和田裕司(大阪市立大学教授)
参加者:16名
明けましておめでとうございます。
このたびイスラーム地域研究上智大学拠点文科省事業公募研究(SOIAS)では、2012年度「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」第3回研究会として、多和田裕司先生(大阪市立大学)にご報告をいただきます。5年にわたり議論を重ねてまいりました世俗化と世俗主義の問題につきまして、最後の研究会にふさわしい大きな問題を提起しているものです。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください。
なお、市ヶ谷キャンパスはセキュリティ管理の都合上、事前に参加者名簿を提出することとなっておりますので、参加されるご予定の方は、お手数ではございますが、所属とお名前を明記の上、1月25日まで、できましたら23日正午までに上智大学イスラーム
地域研究機構(ias-site[at]sophia.ac.jp)宛てにご連絡をお願いいたします。
その際、他の研究会との混同を避けるため「世俗化」の文字をどこかに入れて
いただければ助かります。
記
日時: 2013年1月26日(土曜日)14時-18時
報告者: 多和田裕司(大阪市立大学)
題目: 「世俗化の時代」のマレーシア・イスラーム-イスラーム化/世俗化の二元論を越えて-
「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」総括コメント: 粕谷元(日本大学)
会場:上智大学「市ヶ谷」キャンパス 研究棟共同室601会議室
(JR中央線、東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅 徒歩5分
または東京メトロ有楽町線麹町駅 徒歩5分)
*四谷キャンパスではございませんのでご注意ください。また、エレベーターは5階までとなっておりますので、その先6階へは階段をご利用ください。
*会場の位置・経路の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
【地図】
郵便局は、やや奥まった場所にございますので、ガソリンスタンドと河合塾のある交差点を、それらと反対側にお入りください。
お問い合わせ先:上智大学イスラーム地域研究機構SOIAS(ias-site[at]sophia.ac.jp)
スパムメール対策のため、@を[at]と表示してあります。
レポート:
まず、多和田氏から標記の報告が行われた。本報告は、多民族多宗教国家マレーシアにおけるハラール(合法)食品の認証制度の事例から、イスラームとその外部(現代的価値など)の問題について考察したものである。同氏はまず、カサノヴァの世俗化の3命題をひき、世俗的領域の機能分化は構造的趨勢であるが、宗教意識の衰退および私事化は現代の特にイスラーム世界にはあてはまらないとした。
マレーシアでも、「イスラームの商品化」と呼ばれるような事態が起こっており、食品をめぐっても、1974年以降、国家がハラール認証を行うようになり、マレー系の消費者に向けてハラールのロゴマークを明示して提供する店が増えているほか、国際的にもハラールビジネスをマレーシア国家として戦略的に推進しているという。
ハラールは、イスラーム的な行為として好まれる一方、非ムスリムの企業もマレー系の住民を相手にするためハラール認証を選択する傾向にあり、ブミプトラ(マレー系)企業は3割を占めるにすぎず、認証の売買や偽造まで行われており、ハラール認証を受けた理由について数人の証言が紹介された。
このように、ハラールの拡大はイスラーム化のあらわれという宗教の論理である一方、非マレー系も含め利益という経済の論理によるものでもあり、そしてその際には、収益の他にも法手続きや物流、技術、国際競争力などイスラームの「外部」が強く関与しているという。
次に、多和田氏の報告を受けて、質疑が行われた。まず、マレーシアという国家におけるウラマーやムフティー・担当部署の役人の資格や役割について複数の質問が寄せられた。これに対しては、マレーシアは連邦国家であり、資格としてのウラマーはないが、それぞれの州の王がファトワを出すムフティーの任命権を持っており、担当する役人はイスラーム教育を受けた者が多いこと、マレーシア国家がハラール認証を一元化するため民間団体を制限しているという回答があった。さらに、ハラールの強調は、ムスリム内部での立場を良くするための差異化に必要で、非ムスリムが多く様々な食品が流通するマレーシアならではの認証の必要性によるものであるといった指摘がなされ、報告者も村ではイスラームの知識を持つものが尊敬されることが多いと同意した。また、ハラールをめぐる宗教の論理と経済の論理との関係については、やはり経済的動機が大きいのではないかという意見やムスリムと非ムスリムで分ける必要があるのかという質問がなされたが、カンファレンスではイスラームを守ろうという発言も同時になされているなど実態は複合的であり、シンボルの観察しかできないという限界もあることが示された。
つづいて、本事業の研究代表の粕谷氏から、多和田氏の報告へのコメントと、これまでの5年間の活動についての総括が行われた。
まず、多和田氏に対しては、本報告は教義と現代的価値の調和による世俗化という重要な問題を提起していると評価した。
粕谷氏によれば、本事業は、当初SIASによるイスラーム運動の研究を補完する事業として計画されたが、まずトルコ以外の研究が少なく、世俗化・世俗主義の定義という段階で大きな問題に直面したという。特に政教分離と異なり、世俗主義(Secularism)という語を用いるのはトルコとインドの研究者のみで、しかも1964年のベルケスの著書以降であるため、比較研究を行う場合には世俗化と政教分離とする方が適切であるという。
そこで、政/教の中身について考えていくと、イスラームは政教一致・政教一元であるとする議論も根強いが、歴史研究およびイスラーム法学の立場からは、イバーダート(儀礼的規範)とムアーマラート(法的規範)の区別はもともとあるものであり、後者を国家が管理すべきという議論がオスマン朝の末期に行われてきたことを指摘した。今後は、このように「世俗主義」という言葉で考えるだけでよいのかということも含めて考えていく必要があり、世俗化の問題のほか、内在的な神学的法学的議論も求められるとした。
最後に、世俗化と世俗主義の全体の問題について、広く議論が行われた。概念をめぐっては、世俗化と世俗主義の反対の概念は「聖」ではないかという指摘、特殊トルコ的なものではないかという主張、インドネシアでは世俗化はよいが世俗主義は危険視されているという指摘、単なる政教分離から無神論まで様々な考えがあるという議論、西洋でも世俗主義と言えるのはフランス一国であるという指摘もなされた。一方で、歴史学と宗教学の立場からは、そもそもイスラームは世俗的なものではないのかという主張や、そういった宗教的な主張も歴史の中で議論されるものであり、その文脈を注意深く見ておく必要があるという指摘もなされた。これに対し、オスマン時代末期にはシャリーア裁判所の法源・管轄問題の問題があり、現代はモスク管理やヴェールの問題が存在するので、そのような問題を丁寧に分析していくことが重要ではないかという応答がみられた。
本報告は、世俗主義/イスラーム主義という単純な二分法では、現代的価値と直面する現実のイスラーム社会を考える際に取りこぼす問題もあるという危険性が指摘され、たいへん考えされられた。これは、この文科省公募事業「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」の5年間を締めくくるにふさわしい重要な問題を提起したものであり、世俗化と政教関係をめぐる本質的な問題について活発な議論が行われたと評価できる。
文責:荒井康一(上智大学イスラーム地域研究機構 研究補助員)