
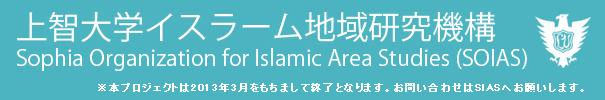

活動報告
文科省公募事業SOIAS
上智公募研究SOIAS「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」第二回研究会のお知らせ
報告者:粕谷元(日本大学文理学部准教授)
参加者:15名
このたびイスラーム地域研究上智大学拠点文科省事業公募研究(SOIAS)では、
2012年度「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」第二回研究会として、本公募研究の代表の粕谷元(日本大学)が報告を行います。イスラーム社会における政教分離の概念について、トルコを事例に再検討を行う予定です。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください。
なお、市ヶ谷キャンパスはセキュリティ管理の都合上、事前に参加者名簿を提
出することとなっておりますので、参加されるご予定の方は、お手数ではござい
ますが、所属とお名前を明記の上、11月16日午前中までに上智大学イスラーム
地域研究機構(ias-site[at]sophia.ac.jp)宛てにご連絡をお願いいたします。
その際、他の研究会との混同を避けるため「世俗化」の文字をどこかに入れて
いただければ助かります。
記
日時: 2012年11月18日(日曜日)15時-18時
報告者: 粕谷元(日本大学)
題目: 「二つの政教分離-1924年3月にトルコ大国民議会が制定した『世俗化』3法の再検討」
会場:上智大学「市ヶ谷」キャンパス 研究棟共同室601会議室
(JR中央線、東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅 徒歩5分
または東京メトロ有楽町線麹町駅 徒歩5分)
*四谷キャンパスではございませんのでご注意ください。また、エレベーターは5階までとなっておりますので、その先6階へは階段をご利用ください。
*会場の位置・経路の詳細については、以下をご参照ください。
【地図】
郵便局は、やや奥まった場所にございますので、ガソリンスタンドと河合塾のある交差点を、それらと反対側にお入りください。
レポート:
2012年11月18日、上智大学において、本公募研究代表の粕谷元氏(日本大学)による報告がなされた。「二つの「政教分離」」と題された粕谷氏の報告は、トルコ共和国(1923-)建国の翌年である1924年の同じ日(3月3日)に制定された、「世俗化」に関する三つの法の法案審議を検討することにより、共和国政府の公式定義に見られる政教分離論と、イスラーム法学上の政教分離論は、表裏一体の関係にあったことを明らかにしたものであった。
まず粕谷氏は、本報告において検討する三つの法、すなわち、①シャリーア・ワクフ省及び参謀省の廃止に関する法律(法律第429号)、②教育統一法(法律430号)、③カリフ制の廃止及びオスマン王家のトルコ共和国国外への追放に関する法律(法律431号)について簡潔に紹介された。そのうえで、「世俗化」を論じる際には、それを定義したうえで使用する必要があるが、「政教分離」についても同様に、「政」と「教」が意味するものを明確にすること、さらに言えば、そもそも何と何の、何の何からの分離であるのかを整理することが必要であると指摘された。
考察の前提がこのように整理された後、1924年に実際に審議がなされた順に、三法の審議過程における議論が具体的に検討された。まず扱われたのは、③カリフ制の廃止に関する法であった。すでに1922年11月の段階で、トルコ大国民議会は、スルタン・カリフ制をスルタン制とカリフ制に分割し、前者を廃止していたが、それにより、残されたカリフの職責と権能が、国政上の争点として浮上することとなった。そこで登場したのが、政府の公式見解である「精神的カリフ論」「象徴カリフ論」である。これは、スルタンは俗権であるが、カリフは全ムスリムにとっての「象徴」であり、統治権・主権を有さない単なる精神的・宗教的権威であるとする、一種の政教分離論であった。そしてこうした「精神的カリフ論」「象徴カリフ論」は、ズィヤ・ギョカルプなど当時の論客によっても定式化されたのであった。
しかしながら、こうした議論は、カリフ制の存在自体を前提としているため、それを以ってカリフ制の廃止を正当化することは、論理的に困難であった。そこでその論理を転回させる必要が生じたのであるが、それを実行したのが、時の法務大臣セイイド・ベイであった。彼は、トルコ大国民議会における演説において、以下のような論理を展開することにより、カリフを俗権と定義した。すなわちセイイド・ベイは、カリフ制は、実は『クルアーン』にもハディースにもまったく言及のない、そもそもイスラームの教義ともシャリーアとも無関係な便宜的な制度であると指摘したうえで、イスラームは宗教と政治の両面を併せ持つ教えであり、ムハンマドはその両方の指導者であったが、カリフは政治的な指導のみを担う存在であり、したがってカリフ制は純粋に非宗教的な政治制度であると論じたのであった。さらに彼は、イスラーム法には、統治者は個人でなければならないとする規定も、議会が国民を代表し最高統治者になることを禁じた規定も存在せず、しかも、選挙を通じた統治権の委任行為こそカリフ制の本質であるとして、議会や政府がムスリム共同体を統治することは合法であり、今日ではそれらがカリフの職責を体現し得ると結論づけたのであった。セイイド・ベイのカリフ論は、このようにカリフを俗権と定義し、まさにその点において「精神的カリフ論」「象徴カリフ論」とは正反対の立場をとっていた。そしてこれが、カリフ制廃止の根拠として機能することとなった。
次いで審議されたのは、①シャリーア・ワクフ省の廃止と、それに伴う宗務局の新設に関する法であった。まず粕谷氏は、当時の公的な政教分離論を紹介し、それが、政治siyâsetから信仰i‘tikâdât及び良心vicdâniyyâtを分離すること、あるいは国家devlet及び現世/世俗dünyâの問題並びに政治siyâsetから宗教的思想dîn fikirleriを分離するというものであったことを確認された。そのうえで、1924年3月2日に開催された、同法の人民党議員総会における法案審議を検討された。そこでは、かつてシャリーア・ワクフ大臣を務めていた人物二人が同省の廃止に反対したが、人民党書記長レジェプ・ベイは彼らに反論し、シャリーア・ワクフ省が閣内に留まれば、絶えず政治siyâsetの風向きと政治politikaの流れに晒されてしまうと論じ、同省の廃止と宗務局の新設を支持した。
同法案は逐条的に採決され、トルコ大国民議会本会議に送付されたが、票決の直前、トゥナル・ヒルミ・ベイが、宗務umûr-ı diyâniyyeとはいかなる意味なのかと、dînとの対比でdiyâniyyeの意味を問うた。しかし議長はこの質問に取り合わず、採決に至ったのであるが、翌3月3日に開かれたトルコ大国民議会本会議では、まさにこの点が争点となった。そのとき、言語学者であり、後にトルコ言語協会の初代会長となるサーミフ・リファト・ベイは以下のように説明し、その後に行われた挙手投票の結果、宗務局の名称としてDiyânet İşleri Reisliğiが採択されたのだが、その説明は、「dînとdiyânetとの間には、法学(フィクフ)上の相違がある。dînは、判決、法学意見(ファトワー)に係わるような人間関係(ムアーマラート)に関するあらゆるもの、儀礼的規範(イバーダート)、道徳、信仰を包含する。他方、司法的問題(カザー)に含まれない道徳、法学意見、儀礼的規範、信仰を、個人の解釈や理解のもとに取りまとめた法学用語がある。それがdiyânetである」というものであった。つまりサーミフ・リファト・ベイによると、diyânetは、dînから司法的問題を除外したものということになるが、粕谷氏は、これを、単なる言葉遊びではなく、政治的目的を帯びた真剣な議論であったと評価された。
以上の二法案の審議の後、人民党議員総会においても、翌日のトルコ大国民議会本会議においても、メドレセの廃止を定めた②教育統一法が審議されたが、いずれにおいても、ほとんど議論がなされないまま可決された。これは、おそらく、タンズィマート期以来の新式学校の普及により、その路線の継続は当然視されたのではなかろうかと粕谷氏は推察された。
こうした考察から、粕谷氏は、結論として、政府の公式見解に見られる政教分離論と、イスラーム法学上の政教分離論は、表裏一体の関係にあったこと、「分離」には、現世/世俗dünyâ及び政治siyâsetからの宗教dînの分離と、dînとdiyânetの区別という二つの文脈が存在したこと、そしてdînとdiyânetを区別したことにより、結果的にdînが国家から分離される一方で、diyânetが国家の宗務としてその管理下に置かれたことを指摘された。

報告後になされた討論においては、他国の事例も踏まえたうえで政教分離を類型化することは、どの程度可能であるのか、三法案を作成したのはどのような人物たちで、彼らの知的背景はどのようなものであったのか、オスマン時代にもこれに類似した議論は行われていたが、そうした議論と今回扱われた問題群は、どのように接続するのか、カリフ制はトルコ一国の問題ではなく、その廃止は世界中のムスリムに影響を与えることになるが、それをあらかじめ考慮した審議はなされなかったのか、といった重要な論点が話し合われた。そのうち、たとえば最後の問題について、粕谷氏は、他国への影響を配慮した議論もなされないわけではないが、結局のところは自国の問題として処理する以外に現実的な方法がなかったと応答された。また、スルタン制の廃止により、カリフ位のみが与えられていた当時のカリフは、他ならぬ大国民議会によってその位に任命されていたことも、カリフ制の廃止を国内の問題として処理することを可能にしたと論じられた。
本公募研究の代表による、理論と実証を兼ね備えた報告から、参加した十数名が大いに知的刺激を受けたことは、報告後の討論が極めて活発であったことからも明らかであった。最終年度に相応しい、充実した研究会であった。
(文責:長谷部圭彦、東京大学大学院人文社会系研究科附属次世代人文学開発センター客員研究員)