
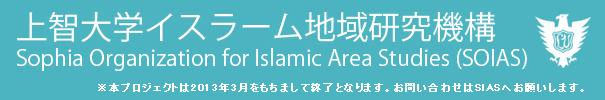

活動報告
拠点強化事業「イスラームをめぐる諸宗教間の関係の歴史と現状」
2012年度講演会 報告(2012年11月11日/上智大学)
日時:日時:2012年11月11日(日) 15:00‐17:30
場所:上智大学市ヶ谷キャンパス研究棟6階 601号室
参加者:19名
講演1: FransiscoAnto(上智大学)
"Muslims and Christians in Indonesia in the Reformation Era (1999-now)"
講演2: Dr. JamhariMakruf(State Islamic University in Jakarta)
"Islam in Post 2001Indonesia"
講演3: Dr. Ismail LutfiJapakiya(Rector of Yala Islamic University, Pattani.)
"Islam in Southern Thailand"
Fransisco Anto氏による第1講演「改革期以降のインドネシアにおけるムスリムとキリスト教徒」は、Ⅰ.インドネシアにおけるムスリムとキリスト教徒の人口、Ⅱ.改革期(1999-現在)における両者の関係、Ⅲ.両者の関係の明暗、Ⅳ.より良い相互関係のための指導者たち、という順番で展開し、インドネシアの宗教分布の現状と問題、また異宗教間の共存のための努力について明解に説明がなされた。Ⅰでは、インドネシアの総人口中ムスリムが87%以上、プロテスタントが約7%、カトリックが約3%を占めている人口比率や礼拝所の数の紹介した上で、特にカトリック教会に焦点を当て、カトリック人口が集中している東南島嶼部や大都市とそこを指導する司教について説明がなされた。Ⅱでは、改革期におけるムスリム-キリスト教徒関係について、1.「日常生活における対話」では、両者が一つの地域共同体の中で共生し、隣人として慣習も共有していること、異宗教の隣人を認める多元的共存を支持する人が77%を超えることなどが指摘された。2.「行動面での対話」では、ムスリムとキリスト教徒が社会問題の解決や正義と平和の推進のための協働を改革期の当初から行ってきたことが紹介された。3.「宗教体験に関する対話」では異宗教の信徒間の信仰や儀礼面での交流が、ICRP(インドネシア宗教・平和協議会)の活動を中心に紹介された。4.「神学論争における対話」では、相互の神学理解のための対話は極めて稀であり、この「対話」のためには謙譲さと開放性が必要であると指摘された。Ⅲでは、1999年1月に勃発したアンボン紛争を事例として、ムスリムの中にはキリスト教化に関する恐怖があり、キリスト教徒はインドネシアのイスラーム国家化への恐怖があるという暗の面が指摘された上で、草の根運動のレベルで和解推進運動と多元的共存推進運動が展開している状況が解説された。Ⅳでは、ムスリムとキリスト教徒のより良い関係を主導する優れた指導者を養成するための双方の教育機関(全寮制学校)の紹介がなされた。
第2講演は、ジャカルタ州立イスラーム大学の副学長Jamhari Makruf氏による「皮肉な情況:2001年以後のインドネシアにおけるイスラーム」であった。東南アジアにおけるイスラームの新潮流として、インドネシアにおけるイスラーム主義の高揚と急進派ジハーディー運動について具体的なデータを提示して報告がなされた。同国では20世紀末の深刻な社会・経済的危機を乗り越えた後、独裁政権が崩壊して民主化が進んだ。公的領域においてイスラームを圧迫していた独裁政権が倒壊した結果、イスラームを思想的根拠とした社会運動が芽生え、民主主義とイスラームの共存が図られる一方で、皮肉なことに表現の自由の名の下に急進的な宗教運動が出現した。その中でも暴力的手段を肯定しているのがジハーディー派の運動である。ジャムハリ氏は「急進的イスラーム」を精密に定義づけた上で、ラディカリズムには暴力行為を行う行動派とそれを支持・容認する態度派があると指摘し、2010年にインドネシア調査サークルと平和活動家ラズアルディ・ビッル氏が行った調査に基づいて、テロ活動に関する国民の意識を分析した。その結果、急進的な暴力行為に賛同するムスリムは少数であるが、国民の中には急進派の行為を支持し同意する相当数の人々がいること、状況によっては潜在的に急進派となり得る人々もかなり存在することを提示した。また2011年のジャカルタ州立イスラーム大学による他宗教に対する不寛容さに関する意識調査の結果から、政治・社会的問題についてムスリムの寛容性は高いが、非ムスリムの儀礼や礼拝堂建設等のような宗教的問題に関する寛容性は低いことが提示された。さらに、不寛容さは非主流派ムスリムにも向けられる可能性もあること、クルアーンや使徒ムハンマドなどイスラーム的アイデンティティへの攻撃はムスリム大衆に大きな衝撃を与えることが指摘された。結論として、急進的イスラーム主義者は少数派ではあるが、社会的に大きな影響力を持つため解決が急がれること、ムスリムとしての連帯意識を刺激するような国際問題や欧米の国際政策が引き金となって、インドネシアには急進的イスラームの興隆を導くような状況が存在することが指摘された。最後にジャムハリ氏は、世界を白黒2分法的に見るある種のイスラーム理解が急進派の暴力の高揚に寄与していること、不寛容はイスラームへの攻撃によって惹起され、国際的に広がる急進派イスラームに対処するには国際的な協力が必要であると主張した。
パッタニのヤラ・イスラーム大学の学長Ismail Lutfi氏による第3講演「タイ南部におけるイスラーム」は、氏の著書「イスラーム:世界における平和の宗教」に関連した講演であった。同書において氏はタイ南部における宗教紛争について論じたが、氏をイスラームの教えを誤用していると非難する人もいる。氏はIRC(平和のための宗教間評議会)の座長であり、この会議はタイ南部におけるあらゆる抗争を平和的に解決し、そのためにタイ住民の宗教的帰属意識を高め、さらにタイ南部の抗争への注目を喚起し、同地方の住民への理解と共感を打ち立てるのを目的としている。7つの宗教(仏教、ヒンドゥー教、イスラーム等)の代表で構成されるIRCは、セミナー、巡礼(参詣)、宗教間会議を含むいくつかのプログラムを推進している。氏の見解ではあらゆる宗教紛争は歴史的・政治的原因によって生み出されたもので、解決策として氏は以下のことを主張した。「宗教は諸問題の原因ではないが、宗教を通して以外に問題解決の最善の方法はない。イスラームは他の宗教と対立しない平和の宗教であるから、この際にイスラームが問題解決の最善策を提供する。」さらに氏は、全人類は7つの共通要素を持つと主張し、その考え(哲学)はタイ南部の人々のマジョリティに受け入れられるものであり、タイの全ての問題を解決するためにあらゆる宗教が同一の視点(この哲学)を共有することを望んでいると纏めた。
それぞれの講演に対して参加者、特に東南アジア研究者から多くの質問が寄せられ、活発な議論が展開し、講演会は盛会に終わった。
文責:太田敬子(北海道大学大学院文学研究科・教授)