
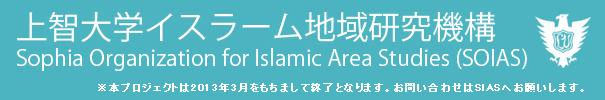

活動報告
拠点強化事業「イスラームをめぐる諸宗教間の関係の歴史と現状」
2012年度第一回研究会 報告 (2012年6月30日/上智大学)
参加者:13 名
日時:2012年6月30日(土) 14 :00‐17 :00
場所:上智大学市ヶ谷キャンパス研究棟6階 601号室
発表者:
発表①:辻 明日香(高崎経済大学)
「13世紀後半エジプト・デルタ地方におけるコプト聖人の活動」
コメンテーター 太田 敬子(北海道大学)
発表②:中村 妙子(早稲田大学)
「初期十字軍とジハード」
コメンテーター 黒田 祐我(日本学術振興会特別研究員・上智大学)
<辻氏報告レポート>
辻明日香氏の発表題目は、「『ハディード伝』に描かれた13世紀後半下エジプトにおけるコプト社会」である。13世紀に生きたコプト教会の聖人、ハディードの聖人伝から、当時のエジプトにおけるキリスト教徒の実態を読み解き、コプト聖人が果たしていた社会的役割を検討しようというのが、その目的である。
13世紀、エジプトではすでにイスラーム化が進んでいたものの、いまだ人口の約50%はコプトが占めていた。しかしながらこの時期、下エジプトからコプト社会は急速に消滅しており、残された資料があまりに少ないため、その理由はあきらかになっていない。辻氏は主教名簿選集や当時の記録を読み込み、下エジプトでも主教座数の変遷に地域差があったことを検証した。十字軍の侵攻や飢饉、住民の強制移住などが影響をおよぼしたことが考えられる。
ハディードはナイル川ラシード分流沿いの町、ヌトゥビス・アッルンマーンの教会司祭をつとめた人物であり、生涯を通じてラシード分流沿いで活動した。列聖されたのかどうかは不明であるが、奇蹟を多く起こしたことが、単独の聖人伝である『ハディード伝』に記されている。ただし、聖人伝が執筆されたことが、列聖とどのようなかかわりがあるのかは不明である。
『ハディード伝』からは、マムルーク朝バイバルス期のキリスト教徒に対する圧政の下、重税を課されたキリスト教徒がどのように暮らしていたのかを、ある程度忠実に読み取ることができる。また、助言や治癒を求めてハディードを訪問した人びとの出身地などから、アレキサンドリアやフスタートとも交易がさかんであったラシード流域の地域性や、コプト語からアラビア語へと使用言語が移行しつつあり、教会破壊とともに再建が進んでいた時代背景、政治問題とのかかわりなども浮かびあがってくる。ただし、『ハディード伝』は手稿が三部現存するのみで、聖職者以外の閲覧は禁じられており、研究にあたってはその内容を直接読むことができないという問題点も存在する。
質疑応答では、貴重な聖人伝の解析をおこなった辻氏の研究への評価とともに、ラシード分流とダミエッタ分流の比較研究の必要性や、『ハディード伝』そのものの真贋に言及するコメントも出た。
<中村氏報告レポート>
中村妙子氏の発表題目は、「初期十字軍とジハード」である。中村氏は常々、十字軍初期のジハード概念のとらえどころのなさに関心を抱いていたため、11世紀末から12世紀末に至るまでの、ジハードの法解釈をまとめ、その変遷を追ったのが、今回の発表であった。
11世紀末から13世紀にかけての時期が、シリアにおける十字軍時代に相当する。このうち後期にあたる13世紀には、サラディンの登場によってジハードが声高に唱えられるようになり、聖地においてはその死守、聖地以外では領土確保・拡大がその目的として明確に設定されるようになった。
しかしながら、初期十字軍において、ジハード意識はむしろ低い。シリア諸都市と十字軍の間では、何度も協定が締結されており、あたかも十字軍もシリアの地方政権として認められているかのような扱いである。また、両者間に戦闘はみられても、農閑期に限られており、休戦協定が結ばれる農繁期には金品や馬の取引があった。アラブ小都市の領主が両者の仲介役をつとめ、報酬を得るという事例もみられる。ただしこのような状況も、イマード・アッディーン・ザンギーの登場によって勢力均衡がシリアの北部と西部で差異が生じると変化し、それに伴い、ジハードの法解釈も変わっていった。
ジハードはそもそも、軍事行動を必ずしも伴うものではなかったが、政治的背景に左右され、次第にその要素を色濃くしていった。ところが、8世紀から11世紀末にかけてカリフの権力が衰退すると、無理なジハードをおこなう必要はないという解釈が主流となってゆく。12世紀後半には、「防衛のジハード」、すなわちムスリムを圧迫する十字軍に対する防衛という認識が生じ、現在に至っている。
中村氏は「防衛のジハード」認識が生まれる前、12世紀前半のジハードを史料から読み解いている。
文責:菅瀬晶子(国立民族学博物館・助教)