
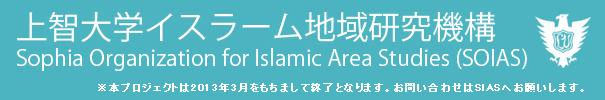

活動報告
文科省公募事業SOIAS
上智公募研究SOIAS主催「ドゥルムシュ・ボズトゥー氏講演会『イスラームと科学』」 報告
日時:2012年2月22日(水曜日)15-18時
会場:上智大学「市谷」キャンパス 研究棟601会議室
講演者:Prof. Dr. Durmus Boztug トゥンジェリ大学学長
題目:イスラームと科学
参加者:11名
要旨:
本会においてボズトゥー氏は、現代トルコの発展過程と重ねながらトルコにおける「イスラームと科学」について講演を行った。

宗教に関しては、ボズトゥー氏はインテリジェントと非インテリジェントをつなぐものであると述べ、すべきこと/してはならないこと、正しいこと/悪いこと、役立つこと/役に立たないことを教えるものであるとした。一方科学は、周囲で起こる事象を説明するものであると述べた。このような観点に立つと、クルアーンでは科学に言及した箇所が多く見られ、イスラームにおいて考えることが重視されていることが分かる。また、イスラームは常に科学の進歩を推奨するものであり、科学はアッラーが創造した世界に光をもたらすものであると指摘した。これは、科学が国家の支援を受け、9~14世紀にイスラーム圏が西洋に比べより発展していたことにもよく表れている。
このようなイスラームと科学の両立性は、アレヴィーと密接な関係を持つハッジ・ベクターシ・ヴェリー(1209~1271年)の教えにも色濃く表れていると指摘した。ライオンと鹿を抱えたハッジ・ベクターシ・ヴェリーの有名な肖像は、双方の互いの尊重を示し、「科学のない道行はすべて暗闇である」という彼の姿勢を表しているものである。ボズトゥー氏は、ハッジ・ベクターシ・ヴェリーの思想は、科学や愛、平等、寛容、平和などに基づいており、現代にも広く通じるものであると説明した。
講演後の質疑応答では、出席者から様々な質問がなされた。現在のトルコにおけるハッジ・ベクターシ・ヴェリーの扱いに関する質問については、冷戦後に多様性が認められるようになったことで幅広く言及されるようになったこと、また、あくまでもアレヴィーはイスラームの範疇として考えられるべきであるとの指摘がされた。また、科学は宗教に影響されないのではとの質問については、宗教によってアプローチや発展方法が異なるとの説明がなされた。ダーウィンの進化論に関しても、尊重されるべきだが支持するか否かは個人の問題であり、表現の自由の範囲内の問題であるとの見解を示した。
(文責:岩坂将充/日本学術振興会特別研究員)