
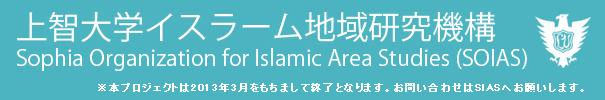

活動報告
拠点強化事業「イスラームをめぐる諸宗教間の関係の歴史と現状」
2011年度第二回研究会 報告(2011年12月12日/上智大学)
タイトル:“The Maronite Christians of Lebanon and Their National Identity”
報告者: Prof. Dr. Khalil Karam(Saint-Joseph University, Beirut)
日時:2011年12月12日(月) 17 :00‐19 :00
場所:上智大学市ヶ谷キャンパス研究棟6階 601号室
コメンテーター:三尾 真琴(帝京科学大学)
参加者数:19名
概要:
第二回研究会は、サン・ジョゼフ大学のハリール・カラム教授を発表者に迎えた。演題は、彼自身が属するマロン派カトリック成立の歴史と、信徒たちが持つナショナル・アイデンティティについてであった。
カラム教授は、隠遁の修行者聖マロンにさかのぼるマロン派の起源から、今日に至るまでの歴史の解説に多くの時間を割いた。聖マロンとその追随者たちの活動の場はシリア北西部であったが、イスラーム勢力の流入によって、レバノン北部のカディーシャ渓谷に拠点を移したことで、マロン派は「レバノン北部山岳地方のキリスト教」として、独自性を保つこととなった。つまり、ローマ・カトリックに属しながらも、地元出身の総大司教を首長と仰ぎ、教会組織と信徒は彼のもとに結束しているのである。また、マロン派は同時にアラブ人としてのアイデンティティを強く持っており、そのことは19世紀にレバノンなどでおこったアラビア語復興運動において、マロン派信徒が果たした役割の大きさにあらわれている。なお、マロン派によるアラビア語復興運動への貢献は、イエズス会との密接なかかわりを通して学んだ印刷技術や、マロン派の修道院に数多く保存されていた、アラビア語の古文書の存在によるところが大きい。
質疑応答では、コメンテーターの三尾真琴教授(帝京科学大学)を中心に、マロン派による教育のありかたやその影響力、他教派のキリスト教徒やドルーズ、ムスリムとのかかわり、一部のマロン派が80年代に掲げたナショナリズム「新フェニキア主義」に対する見解などについて、活発な議論が交わされた。