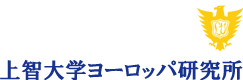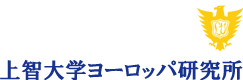『上智ヨーロッパ研究』第1号(2008年)
特集「ヨーロッパ言語とアジア圏」
The Nitobe Process in the Asian Context / Humphrey Tonkin
Esperanto, an Asian Language?: Growth-promoting and Growth-limiting Factors
in an Evolving Interlingual Ecosystem / Mark Fettes
The Meaning of 'European': The Challenge of High-Contact Varieties for
Linguistic Taxonomy / Hugo Cardoso
論文
メルケル政権下におけるドイツ・東方関係の展開とEU の対露戦略:エネルギーの安定確保をめぐって / フアマン・ミヒャエル
EU加盟プロセスにおけるトルコの政軍関係:軍による民主化改革の受容とアタテュルク主義 / 岩坂将充
ポルトガルの移民政策についての一考察:大西洋と欧州の間で(上) / 西脇靖洋
資料紹介・解説
DIE „DAIDOUJI“ - URKUNDE(2) / Jörg Mauz
『ドイツ語圏研究(Studien)』第25号(2007年)
語彙的不完全指定と意味強制:ドイツ語における事象名詞 / ヴェロニカ・エーリッヒ
到達動詞と「瞬時性」に関する予備的考察 / 高橋亮介
フランツ・ヨーゼフ・デーゲンハルトの歌からみた西ドイツの社会と時代思潮 / ライノルト・オプヒュルス鹿島
フリードリヒ・デュレンマットと方法論的合理主義 / 浅見昇吾
「なまはげ」俳句 / ユェルグ・マウツ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第24号(2006年)
シンポジウム「ドイツにおける日本像の過去と現在」
はじめに/ 木村護郎クリストフ
マルコ・ポーロ(1254-1324)の「日本についての報告」:日独関係の出発点 / ユェルグ・マウツ
天国と地獄の間で:初期ヨーロッパの日本受容 / 永田ザビーネ
1910~20年代のドイツ文学における日本とエキゾチズム / ゲアハート・シェーパース
英雄とサムライ:日本とナチス・ドイツのイデオロギー的関係 / トーマス・ペーカー
「彼がめざすのは勝利のみ」:日本の集団表象の例としての相撲力士 / ライノルト・オプヒュルス鹿島
Writing Back?:ブルーノ・タウト、坂口安吾と日本文化 / 吉田治代
アーダルベルト・シュティフターと同時代人における1848年 / アリーセ・ボルテラウアー
「35歳以下」の若者語批判:カトリン・レグラ『Irres Wetter』について / クリスティアン・ツェムザウアー
『ドイツ語圏研究(Studien)』第23号(2005年)
アルトゥール・シュニッツラー『グストル少尉』と世紀転換期ウィーンの政治・社会・文化史的文脈 / ディートマー・ゴルトシュニック
『大道寺』裁許状 / ユェルグ・マウツ
統一ドイツの政党制:東西市域の差異を中心に / 河崎健
『ドイツ語圏研究(Studien)』第22号:シンポジウム「ヨーロッパ文化の原点としての中世」特集号(2004年)
15世紀のパレスチナ旅行記に見る異郷の経験 / アントン・シュヴォープ
啓蒙主義から現代に至る「中世」の評価 / 有泉泰男
中世から現代に至る聖地と療養所としての泉 / 四反田想
近代の多様な受容に見るハルトマンの『哀れなハインリヒ』 / ベルンハルト・エーリンガー
ヨーロッパ中世における宮廷文化の伝播をめぐって / ダグマー・オスヴァルト
『ドイツ語圏研究(Studien)』第21号(2003年)
フリードリヒ・デュレンマットの悲喜劇"Achterloo"における戦争と平和のユートピア/ ディートマー・ゴルトシュニック
説教者修道会福者ハインリッヒ・ゾイゼ(1295(?)-1366)概略 / ユェルグ・マウツ
癒しと和解:心理療法を超えて / クリスティアネ・ランガー
『ドイツ語圏研究(Studien)』第20号(2002年)
ドイツ連邦共和国の1960年代:社会変化・政治計画・社会参加 / マティアス・フレーゼ
ゴットフリート・フォン・シュトラースグルグ『トリスタン』にみられるメディア変革期における演出 / ダグマー・オズワルド
ドイツ声楽曲の音韻論的分析 / 新倉真矢子
『ニーベルングの指輪』におけるワーグナーの世界観 / アンゲリカ・トール-マキノ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第19号(2001年)
皇帝と美術:カロリング朝と神聖ローマ帝国におけるローマ美術の復興 / 佐藤直樹
ハイデッガー:マールブルクとフライブルクの間で / ベルント・マルティン
西洋から市民社会へ:ドイツ連邦共和国の自由化過程 1945-1980年 / ウルリヒ・ヘルベルト
オーストリアの文学領域 / ヴェレーナ・ホラー
『ドイツ語圏研究(Studien)』第18号:ゲーテ生誕250周年記念シンポジウム「現代におけるゲーテの影響」特集号(2000年)
「教養」をめぐる対立:ゲーテ・イヤーにおける歴史的観点での教養論争 / ヴィルヘルム・フォスカンプ
ゲーテと中国古典 / 張玉書
ゲーテの『ファウスト』:近代的性急さの悲劇 / マンフレート・オステン
韓国文化の中のゲーテ:ゲーテ受容の社会・文化的考察 / 金鍾大
ゲーテとアメリカ / ワルター・ヒンデラー
韓国における『ファウスト』上演:韓国における受容の諸問題 / 李源洋
ゲーテのスイス旅行 / アドルフ・ムシュク
中国におけるゲーテ受容:『ヴェルテル』熱から『ヴェルテル』翻訳熱へ / 楊武能
オーストリアにおけるゲーテ / ヴェルナー・M・バウアー
世界文学としてのイギリス文学 / T・J・リード
ゲーテと日本人のメンタリティー / 木村直司
知られざるゲーテ:ドイツ人とその詩人 / ロータール・エールリヒ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第17号(1999年)
キリスト教諸宗派の影響下における16世紀から17世紀に至るドイツ文章語の発展 / ペーター・ヴィージンガー
ヨーロッパの再生 / ヘルムート・ロイスカンドル
世界文化としての世界文学 / 木村直司
ベルリンの壁崩壊後10年のドイツ:「頭の中の壁」を超えて / クリスティアネ・ランガー=カネコ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第16号(1998年)
神経症・過激症:世紀転換期以降の若者たちの文学 / フリートベルト・アスペツベルガー
不和の種オーストリア文学:ある概念をめぐる論争 / ヴェレーナ・ホラー
ウィーンにおけるゲーテ文献学の草創期 / 木村直司
ドイツ情報誌の日本に関する報道:『シュピーゲル』(1947-1988年) / 永田ザビーネ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第15号(1997年)
統一7年後のドイツ:心理状況とメンタリティー / クリスティアネ・ランガー=カネコ
詞華集 / ユェルグ・マウツ
さようなら日本!/ バルバラ・ユルタッシュ
[コロキウム] スイス 誰も知らなかった国 / 飯塚重男・関根照彦・東郷公徳・渡辺有子・八幡康貞
『ドイツ語圏研究(Studien)』第14号(1996年)
教会の抗争と変革:ある回想 / フリードリヒ・ショルレマー
ドイツ家庭の社会史 / ハンス=ユルゲン・トイテベルク
1900年~1945年の日本におけるドイツの文化政策 / ロルフ=ハラルド・ヴィッピヒ
統一ドイツにおける社会と民主主義:社会学的考察 / ヴォルフガング・ツァプフ
<書評>
イ・ファン著『1871年~1918年の中国の教育発展に及ぼしたドイツの影響』 / ロルフ=ハラルド・ヴィッピヒ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第13号(1995年)
政治的ナイーヴさの喪失:A.デブリン著『1918年11月』における女性の姿形 / クリスティーナ・アルテン
ヒンデンブルク元帥と匕首伝説 / クリスティーナ・アルテン
詞華集 / ユェルグ・マウツ
オトフリート・ニッポルトと第一次世界大戦 / 中井晶夫
外国語としてのドイツ語 / ペーター・ヴァッサートイラー
舞台演劇におけるヒトラー:悪の大衆化 / ロルフ=ハラルド・ヴィッピヒ
<書評>
ゴトフリート・ムラーツ著『オーストリアと帝国1804-1806:終焉と完結』 / ユェルグ・マウツ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第12号(1994年)
アルフレッド・デルプ神父とドイツ抵抗運動:50周年を記念して / ペーター・ハメリヒ
ドイツ語教育苦労物語 / ジャン=クロード・オロリッシュ
スイスから見たドイツの20世紀 / トーマス・インモース
ポスト・モダニズムはひとつの歴史主義か:歴史の絶対性と歴史性に関して / ペーター・コスロフスキー
ゲルマンとは何か / ペーター・ヴァッサートイラー
1871年-1945年のドイツの日本政策 / ロルフ=ハラルド・ヴィッピヒ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第11号(1993年)
ゲーテとメーリケ:二つの詩における比較論 / ガブリエーレ・アンドレーエ
日本人のドイツ観への疑問・訂正・提言 / フランツ=ヨーゼフ・モール
ヨハネス・パウリにみられる語りの展開形式 / 高橋由美子
第三帝国における「テイング運動」 / ペーター・ヴァサートイラー
マックス・フォン・ブラントとOAGの創設 / ロルフ=ハラルド・ヴィッピヒ
<書評>
ユェルク・マウツ著『ウルリッヒ・モリトーリス』 / 菅野カーリン
『ドイツ語圏研究(Studien)』第10号:1992年度シンポジウム「大ハプスブルク帝国-その光と影-」特集号(1992年)
はじめに / ルードヴィッヒ・アルムブルスター
ハプスブルク家最後の栄光:1848~1918 / マリアンネ・ラウヒェンシュタイナー
19世紀オーストリア宮廷の制服とモード / ゲオルク・J・クーグラー
ハプスブルク家の奇跡:宿敵オスマントルコからのヨーロッパの解放 / ハンス・ブライテンシュタイン
切支丹に見るPietas Austriaca:イエズス会演劇を通しての一考察 / マルグレート・ディートリッヒ
江戸時代の古地図における「ハプスブルク帝国」 / コーネル・ツェーリッチ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第9号(1991年)
今日の独ソ関係:1945年-1991年 / ハンス=アドルフ・ヤコブセン
邦訳ファウストの変容 / 木村直司
ペーター・ヴストの哲学的人間論についての一考察 / 本間英世
中世都市における世帯構成:15世紀中葉バーゼルを例に / 佐藤るみ子
『ドイツ語圏研究(Studien)』第8号:1990年度シンポジウム「東西におけるゲーテの『ファウスト』」特集号(1990年)
はじめに / ハインツ・ハム
ドイツにおけるファウスト像の変遷 / カール・ローベルト・マンデルコウ
韓国におけるファウスト受容の諸相 / 郭福禄
中国におけるファウスト受容について / 夏瑞春
日本における仏教的『ファウスト』受容 / 芦津丈夫
ドイツのファウスト伝説素描 / クリストフ・ペーレルス
昔の中国にファウスト伝説の素地があったか? / 張玉書
韓国になぜファウスト伝説がないのか? / 池明烈
ファウストの居る場所は何処か?:ささやかな反問 / 柴田翔
<書評>
噺家に冠を / ユェルグ・マウツ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第7号(1990年)
巻頭言 / ハインツ・ハム
公証人職に関する法律意見書:コンスタンツ司教総代理の要求(1492/93)に対するウルリッヒ・モリトーリスの態度表明 / ユェルグ・マウツ
第二次世界大戦前の日本:日本人のナチス解釈をめぐって / 中井晶夫
フランス人の視点から見たドイツ連邦共和国の40年 / アンリ・メヌディエール
ドイツ連邦共和国の政党構造の変化について / エルヴィン・K.ショイヒ
所有権と責任 / ルーペルト・エンデルレ
<書評>
フランス革命に関するドイツ語の出版物 / ハインツ・ハム
『ドイツ語圏研究(Studien)』第6号:上智大学創立75周年記念号(1988年)
巻頭言 / ハインツ・ハム
ヤーコプ・ブルクハルトとイエズス会:学者はいかに大衆の偏見に取り組んだか / ハンス・ブライテンシュタイン
ゲオルク・ミハエリスと日本(1885-1922) / 中井晶夫
世紀末のウィーンの文化における「ロゴス」と「イマゴ」:知識社会学的考察 / 八幡康貞
日本の近代化への道と模範としてのドイツ:二つの遅れた国の共通点(1860-1960) / ベルント・マルティン
<研究ノート>
フランツ・フォン・バーダーの言語論(序説):エクリチュール / 高橋明彦
ドイツ・ジャコバン派の発見 / 室井俊通
<書評>
帝政時代とワイマール共和国時代 / ハインツ・ハム
『ドイツ語圏研究(Studien)』第5号(1987年)
1930年代の歪められた人間像:テオドール・ヘッカーの時代診断 / 木村直司
日本とドイツ:二つの文化の出会い / ハンス・J.トイテベルク
ヨーロッパ安定への寄与としてのオーストリアの中立 / ミヒャエル・ツィンマーマン
『ドイツ語圏研究(Studien)』第4号(1986年)
フェミニズムと宗教 / ガブリエール・アンドレエ
危機の時代のなかの「もし」と「しかし」:日独関係1935-1941 / ユェルグ・マウツ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第3号(1985年)
ドイツの大学における新たな多様化:最近の高等教育改革の動向を通して / クラウス・ルーメル
ナチズムの精神史的症候群:テオドール・ヘッカーの反時代的考察 / 木村直司
『ドイツ語圏研究(Studien)』第2号(1984年)
ヘーゲルの近代国家観 / 本間英世
Franz Kafka: Drama ohne Katharsis / ハインツ・ハム
Kafka: Fahrt durch die Winternacht / トーマス・インモース
Nachruf: Dominicus Kenji Ozaki / ユェルグ・マウツ
『ドイツ語圏研究(Studien)』第1号(1983年)
発刊の辞 / 尾崎鑒治
オーストリーの非武装中立論 / 小林宏晨
1849年ドレスデンの五月蜂起におけるワーグナー、バクーニンとW.ハイネ / 中井晶夫
※上記の既刊出版物は、本研究所ヨーロッパ文庫にて閲覧可能です(貸出は行っておりません)。
|