「湾岸紛争」における米国世論と対日イメージ
(American Public Opinion
during the “Persian Gulf Conflict” and its Image of Japan)
Toshiki Gomi*
SUMMARY IN
ENGLISH:The so-called “Persian Gulf Conflict” broke
out on August 2 of 1990 and actually ended on March 2 of 1991. During that
period the Bush administration had consistently shown a firm attitude toward
the Iraqi invasion of Kuwait and taken decisive measures in responding to
changing situations in the conflict. What made President Bush commit himself in
the affair? A “legalistic-moralistic” sentiment seems to have driven him into
the Gulf region.
A large number of U.S. congressmen strongly gave moral
support to the administration policy in the early stage. As the probability of
a military clash between Iraq and the so-called “multinational forces”
increased, however, the attitude of the congressmen split into two. The
interesting point is that they chose a position of either for or against based
on domestic political considerations like the presidential election of 1992.
Looking at the opinions of various newspapers all over
the country, one could see almost the same trends in views as those of the
congressmen during the period. There were pros and cons among the editorials
with regard to how to solve the problem. But one found shared attitude in favor
of the cause President Bush pursued.
By contrast, Japan suffered from a bad reputation
regarding her way of dealing with the “Gulf Conflict.” Japan’s contribution was
widely seen within the U.S. as “too little, too late.” Her inability to
articulate a coherent response to the affair resulted from historical domestic
constraints. But U.S. public opinion seems to have had little understanding of
the realities in Japan.
1.はじめに
「クウェートは解放された」という言葉を持って始まるジョージ・ブッシュ米国大統傾の演説によって、いわゆる「湾岸戦争」は事実上終止符が打たれた。1991年2月27日(米国東部時間)のことであった。1990年8月2日のイラクによるクウェート侵攻から約7ヵ月、米国主導の「多国籍軍」がイラク空爆を開始してから約6週間、そして地上戦に突入してからほぼ100時間という「紛争」を経ての出来事であった。〔本稿では、イラク軍と「多国籍軍」との武力衝突開始以前および以後の期間にわたって、「湾岸紛争」という言葉を使用する。〕
ところで、米国のブッシュ政権はイラクがクウェートヘの軍事占領を開始したその日から「反イラク」の立場を鮮明に打ち出し、「湾岸戦争」終結時までその姿勢を一貫して堅持した。しかも、「反イラク」側に与した他のいかなる国よりも積極的に介入し、中心的な役割を担った。それゆえ、紛争の構図は「イラク対米国」ないしは「サダム・フセイン対ジョージ・ブッシュ」の様相を呈するほどであった。
では、ブッシュ大統領が「危機」発生の初日からきわめて迅速な対抗措置をとり、その後、強硬姿勢を崩さなかった理由はどこにあったのだろうか。この問いに対する根本的答を提示するためには、「湾岸危機」および「湾岸戦争」の全貌を明らかにしなくてはならない。しかし、現在の時点においてそれを行うには、秘密のヴェールに包まれている部分が大きすぎるため、推測の域を脱しきれず困難である[1]。もっとも、ブッシュ政権が「湾岸紛争」に深く関与したこと、および米国国民が米国の介入に対して賛否両論に分裂しながらも、結果として、ブッシュ大統領の政策を許したことは紛れもない事実である。
そこで本稿では、ブッシュ政権が「湾岸紛争」に対し積極介入を行った全体像を描くことはひとまず措き、米国国民が「湾岸紛争」をどのように捉え、また、ブッシュ政権の政策にいかなる反応を示したかを追求してみたい。こうした分析を行う目的は、米国国民による対外紛争への関わり方のパターンを抽出したいがためである。
ところで、「湾岸紛争」は日米関係にも多大な影響を与えた。「紛争」期間中、米国は日本による「協力」ないしは「貢献」の低さを批判し、湾岸地域に「人的プレゼンス(physical presence)」[具体的には、自衛隊の派遣]を求めるほどであった。日本政府はこの対日要求に応えるため、国連平和協力法の成立を目指した。ところが、自由民主党内からも強い反対意見が出され、同法案は廃案となった。それを補填する方法として、日本政府は総計130億ドルという金銭面での協力によって米国の対日批判を和らげる努力をした。にもかかわらず、米国国民の不満は残り、対日イメージも著しく悪化した。
日米経済摩擦によって、日本に不信を抱く米国国民が増えてきている[2]。「湾岸紛争」における日本の対応は、その傾向に一層拍車をかけた。むろん、米国の政策が正しく、日本のそれが間違っていたというわけではない。ただし、米国の日本への不満が日米関係全体に暗い影を落としたことは確かである。将来の日米関係を明るいものにするためにも、米国における対日不信の構造を解明する必要がある。
そこで本稿でも、「湾岸紛争」に限って米国国民の対日イメージを詳らかにし、何が問題であったかを、「紛争」そのものに対する国民の姿勢に関する分析と併せて検討してみたい。
2.「湾岸紛争」に関する米国の大義と米国外交の伝統
(1)ブッシュ大統領のレトリック
1990年8月2日、イラク軍がクウェート領土内に侵入したその日、ブッシュ大統領は報道陣を前に、こう述べるのだった。すなわち、「アメリカはこの侵略を厳しく非難し、無条件撤退を訴える。今日の世界ではこうした野蛮な行為を認めるわけにはいかない[3]」とイラクを糾弾した。イラク軍によるクウェートヘの侵略行為に対する米国政府の最初の反応は、以上のようにきわめて激しい口調をもって示されるが、それを裏書きするかのように、当日、イラク、クウェートの資産凍結、貿易禁止などの対イラク制裁措置も同時に発表されるのだった。
5日後の8月7日には、サウジアラビアの防衛を目的として、米国空軍のF15戦闘機、F16戦闘爆撃機および陸軍第82空艇師団約4000人が派遣されていく。この時ブッシュはテレビ演説を行い、国民にこう訴えるのだった。すなわち、「国家が存続していく上で、われわれは自分たちが何ものであり、何を信条としているかを再確認する必要に迫られている。いま、私は大統領として、正義を守り、悪を糾弾するために下した決断に対して国民の強い支持を求めたい[4]」とした。
かくして、ブッシュ大統領は「湾岸危機」が発生して以来、1週間も経たないうちに「反イラク」の軍事態勢を整えたことになる。その後、ソ連やフランスなどによる平和的解決のアプローチがとられるが、ブッシュは「イラク軍のクウェートからの全面撤退」が実行されない限り、米国にとって交渉や妥協の余地はありえないとする強硬路線を走るのだった。この「ブッシュ路線」は、1990年11月29日の国連安全保障理事会における「678号決議」によって、反イラク勢力すなわち米国および同盟諸国側の公式路線へと転じ、平和解決への道は狭められた。国連は同決議によって、イラクが1991年1月15日までにクウェートから完全撤退しない場合、加盟国に「必要なあらゆる手段を行使する権利を付与する」のだった。
その後、1月15日まで、様々な外交努力が重ねられるが、サダム・フセイン大統領を翻意させるまでに至らず、軍事的手段が用いられていく。すなわち、1月17日の、いわゆる「多国籍軍」による空爆の開始であった。戦闘は「多国籍軍」の圧倒的優勢で展開するが、1、2週間といった単位で終わることはなかった。
そうした中、ブッシュ大統萌は1月29日、連邦議会において、一般教書演説を行うのであった。演説内容は当然のことながら、「湾岸問題」に集中した。大統傾は米国が「専制と野蛮な侵略」に勝利を収めようとしていることを強調すると共に、「もしわれわれが献身的にはるか遠方の地で善を目ざして悪と闘うなら、われわれは、この米国をあるべき姿にすることができるのだ」と「介入」の意義を自画自賛するのだった[5]。
果たして、「紛争」は2月24日の地上戦突入を経て、ブッシュの予想通りに終わった。イラク軍がクウェートからの撤退を始めると、大統項は3月6日、議会において「戦勝演説」を行った。その初めの部分において、米国および同盟諸国の勝利は「法の支配、正義の勝利である[6]」と高らかに宣言するのだった。
以上が「湾岸紛争」を通して、米国政府がそこに関与していった理由、すなわち行動の大義についてのブッシュによる説明である。それを筆者なりに整理すると、次のようにまとめることができよう。
イラク軍によるクウェート侵攻は国際法違反のために、野蛮な行為であり悪である。米国は国際社会において、そうした蛮行を放置させるわけにはゆかない。米国の使命はそれを矯正することにある。その結果、国際社会に法の支配がもたらされ、正義は成就されることになる。
ブッシュ大統領が「湾岸紛争」に米国を関わらせていった「真意」を客観的に評価できる段階にはない。しかし、少なくともブッシュが公に表明した言葉から判断すると、レトリックや論理の展開において、きわめて伝統的な手法がとられていったことだけは確かである。すなわち、ジョージ・F・ケナンが『アメリカ外交50年』で批判的に指摘しているところの「法律家的=道徳家的アプローチ[7]」であった。
ケナンは国家がそうしたアプローチをとった場合の一つの特徴として、次のようなことを挙げている。「法律を守れと主張する人は誰でも、もちろん法律の違反者に対して憤りを感じるに違いないし、また彼に対して道徳的優越感をもつに違いない。かかる憤激が軍事闘争に投げ込まれる時、無法者を徹底的に屈服―つまり無条件降伏―させないかぎり、その止まるところを知らないのである。[8]」ブッシュの「湾岸紛争」に対するアプローチは、ケナンの描写を文字通り再現したものと言って過言でなかろう。
その意味において、ブッシュ大統領は米国外交の伝統を忠実に遵守したのである。しかも、その手法が成功を収めた時、すなわち、「無法者」とされたサダム・フセイン大統領が軍事的に「屈服」すると、米国国民の大半はブッシュを誉め称えるのだった[9]。
(2)連邦議会の反応
軍事面からみた場合、ブッシュ大統領による「湾岸紛争」への対応は大成功を収めたと言えよう。では、合衆国憲法上、戦争宣言の権能が与えられている連邦議会はいかなる反応を示したのだろうか。およそ7カ月間にわたる「湾岸紛争」において、議員が一貫した姿勢をとったわけでは必ずしもない。情勢の変化によって議員の心も動揺したのだった。たとえば、「紛争」開始および終結の直後においては議員は挙ってブッシュ政権を支持した。しかし、中間期にあっては、決して一枚岩ではなかったのである。
それゆえ、一般論として議会の対応を論じることは困難である。ただし、個々の議決に際しての投票行動を示すことは可能である。議会の対応において、とりわけ重要だったと思われる事例は、1991年1月12日の上下両院決議である。なぜならば、議会はこの決議をもって「湾岸」に派遣されている米国軍の武力行使を正式に認めたからである。つまり、ブッシュ大統領は、国連に続いて米国議会からも、戦闘行動に向けての「御墨付き」を獲得したのだった。
しかし、その票決内容を検証してみると、議員が両手を挙げて賛成したわけではない。また同時に、米国の国内政治の問題としても興味深い現象が表われている。
A表[10]からも判るように、特に上院においては賛成と反対の票差がわずか5票しかなかったのであり、米国を正式に「戦争」へと参加させるには多くの反対と躊躇があったことを如実に示している[11]。
また、その内訳を、政党、人種、宗教、性別といった指標でみていくと、争点は対外問題であっても、議員の投票行動は多分に国内政治的性格を帯びていたことが浮び上がってくる。
A表 米軍の武力行使容認に関する連邦議会決議(1991年1月12日)
|
|
下院 |
上院 |
||||||
|
|
|
賛成 |
反対 |
|
|
賛成 |
反対 |
|
|
総票数 |
|
250 |
183 |
|
|
52 |
47 |
|
|
政 党 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民主党 南 部 北 部 共和党 インディペンデント |
|
86 53 33 164 0 |
179 32 147 3 1 |
|
|
10 7 3 42 |
45 10 35 2 |
|
|
人 種 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
白 人 黒 人 ヒスパニック アジア系 |
|
246 1 3 0 |
150 23 7 3 |
|
|
52 0 |
45 2 |
|
|
宗 教 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロテスタント カトリック ユダヤ モルモン ユニテリアン ギリシア正教 その他 |
|
170 47 16 6 2 4 5 |
77 72 17 2 6 2 7 |
|
|
33 9 3 3 2 0 2 |
25 11 5 0 1 1 4 |
|
|
性 別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男 性 女 性 |
|
239 11 |
166 17 |
|
|
51 1 |
46 1 |
|
まず、政党という尺度で考えてみると、共和党議員が下院、上院ともに圧倒的多数をもって賛成票を投じていた。これはブッシュが共和党であるという極めて当然の結果である。では、なぜ下院において南部選出の民主党議員が過半数も賛成に回ったのだろうか。その理由としては、1988年の大統領選挙における勢力分布と密接な関係があるように思われる。同選挙において、南部は圧倒的にブッシュ支持であったが、そうしたいわゆる「ブッシュ・ディストリクト(Bush-District)」選出の民主党議員が今回の議決において賛成票を投じたのだった[12]。
次に、人種のカテゴリーではいかなる特徴が指摘できるだろうか。黒人を中心としたマイノリティーに属する議員の反対票が印象的である。湾岸に派遣された米軍において、前線の戦闘部隊は多数の非白人兵士によって構成されていた。もし戦闘行動が開始されれば、犠牲者が非白人兵に集中することが予想され、それゆえの反対票であった。戦場にも、国内の人種問題が影を落としていた。
宗教という視点において興味深いのは、カトリックおよびユダヤ教の議員の中に反対票が多かったことである。その理由については必ずしも明確ではない。
ただし、クック(Rhodes Cook)らは、それについて次のような説明をほどこしている[13]。カトリック議員の場合には、ヴェトナム戦争の際、反共主義を掲げて介入に積極的支持を与えた。その反省のもとに、今回は同じ轍を踏まないよう慎重な対応を行ったのではないかとする。ユダヤ系議員の場合、イスラエル擁護の立場から、賛成することがむしろ当然であろう。ところが、実際には過半数の議員が反対票を投じた。その背景として、都市部のユダヤ人によるペンタゴンヘの根強い不信感が議員の投票行動に大きな影響を与えたという。それゆえ、イスラエル支援という命題は決定的要素として考慮されなかったのである。もっとも、こうしたカトリック、ユダヤに関する各々の解釈は、実証的データが与えられておらず、推測の域を出るものでないことも指摘せざるを得ない。
男性と女性においては、どのような差が表われたのだろうか。武力行使と性別との関係をどの程度一般化できるのか、多くの実証的研究を積み上げない限り、断定しがたいところがあろう。ただし、当該事例に限定するならば、相対的に女性議員の方が武力行使に反対であったことは明白である。
ところで、B囲およびC図は上下両院における投票行動を選挙区別に示した分布地図である[14]。ここで注目に値することは、伝統的に「孤 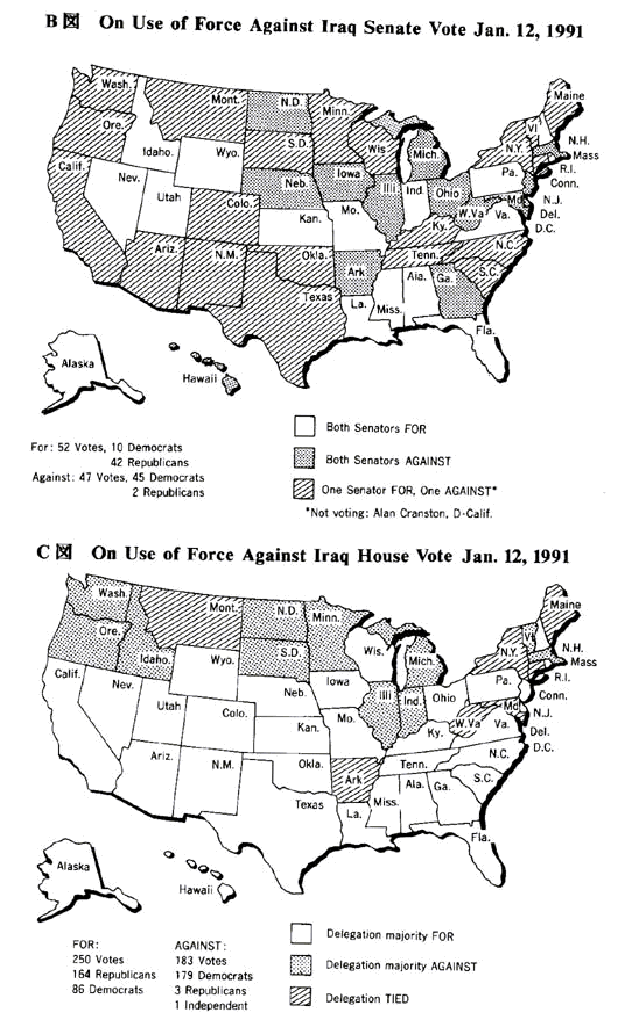 立主義(Isolationism)の傾向が強い地域、特に中西部選出の議員が多数反対した点であろう。対外問題に積極的に介入すべきか否かという点について、少なくとも連邦議会レベルでは概ね従来のパターンが踏襲されたのである[15]。
立主義(Isolationism)の傾向が強い地域、特に中西部選出の議員が多数反対した点であろう。対外問題に積極的に介入すべきか否かという点について、少なくとも連邦議会レベルでは概ね従来のパターンが踏襲されたのである[15]。
最後に、武力行使の是非を問うという点では対外政策的内容であったにもかかわらず、議員の中にはもっぱら内政的文脈において投票したと思われる現象について触れておきたい。たとえば、その代表的人物は、ミズーリ選出のゲッパート(Richard A. Gephardt)下院議員、テキサス選出のベンツェン(Lloyd Bentsen)上院議員、そしてジョージア選出のナン(Sam Nunn)である。彼らは全員反対票を投じた民主党議員であるが、元来、保守的政治家として知られ、特に安全保障問題に関しては強硬な政策を唱えてきたのだった。ところが、今回に限っては従来の立場とは矛盾する行動をとったのである。その理由とは、何だったのだろうか。大物議員としての彼らには1992年の大統領選挙を控え、候補者の可能性ということが脳裏をよぎったものと想像されよう[16]。まさしく、国際間題と国内問題とのリンケージ現象がみられたのである。
3.米国世論の動向
これまでの考察は「湾岸紛争」を通じてのブッシュ政権の対応、そして連邦議会の姿勢に関するものであった。では、米国世論はどのような反応を示したのだろうか。
もっとも、「米国の世論」といっても、何が「世論」であるかは必ずしも明確ではない。分析の技術的問題として、すべての国民を対象とすることはほとんど不可能に近い。そこで本稿では、「世論」の代表的機能をはたし、かつまた政策形成にも多大な影響を与えていると思われる「新聞」にスポット・ライトをあて、「湾岸紛争」にいかなる論調を持って対応していったかを、時系列的に追跡してみたい[17]。
(1)「道義」への賛同
1990年8月2日のイラク軍によるクウェート侵攻は、同日、ブッシュ大統領の非難声明や国連安全保障理事会の即時無条件撤退決議など、直ちに「国際的戒め」を受けた。米国の新聞もこの事件を大々的に報道し、翌日の社説では挙ってイラクを激しく糾弾するのだった。
とりわけ、ニューヨーク・タイムズ紙の論調は、米国世論の最大公約数的内容であったと言っても決して過言ではない。同紙はイラクの行動を紛れもない「むきだしの侵略(Naked Aggression)」であり、国際法(world law)に対する厚かましい挑戦」だと批判した。また「米国はクウェートを支援すべき条約上の義務を負っているわけではない。しかし、湾岸諸国および大部分の国々は(反イラクの)行動を組織化するために依然としてワシントンのリーダーシップと援助を期待している。ブッシュ大統領は国民に断固たる姿勢をとるよう求め、(他国と協調して)集団的外交を推し進めようとしており、適切な対応を行っている。」[カッコ内:引用者注]と論評を加えるのだった[18]。
その基本的認識は、イラクによるクウェート侵攻が「国際法違反」、「野蛮な行為」、「道義に劣る挑戦」と言った表現をもってまとめることができよう。それはブッシュ大統領の発想と軌を一にするものである、同時に、1941年12月7日(米国時間)の日本軍によるパール・ハーバー攻撃に対するフランクリン・ローズヴェルトの非難演説を彷彿させる。すなわち、新聞の最初の反応も「法律家的=道徳家的アプローチ」に依拠していたのである。
さらに、イラクの「侵略性」や「領土的野心」をより鮮明に浮き彫りさせるために使われた手法が、サダム・フセインとアドルフ・ヒトラーを二重写しにすることであった。たとえば、マイアミ・ヘラルド紙[19]は「米国、NATO諸国、ワルシャワ条約機構、良識あるアラブ諸国、および日本は、ヒトラーまがいのイラク指導者によるペルシア湾への支配を阻止するために、徹底かつ協調行動をとる以外にない。」とした。しかも、「ミュンヘンの宥和」という歴史的教訓を踏まえて、ブッシュ大統領および米国の同盟諸国は、チェンバレンではなく、チャーチル的態度をとるべきことを求めたのである。
かくして、米国の新聞はサダム・フセインの「野望」を挫くことに異論をはさむものはなかった。問題は、その方法であった。多くは慎重論を唱え、連携を組んで外交的努力をはかり、同時に経済制裁を課することが正しい選択だと考えた[20]。
しかし、一部にはさらに踏み込んで、積極論もみられた。たとえば「世界にイラクのようなテロリストの国が存在する限り、戦闘行動(hostilities)は不可避である。米国が全世界における国益を守り、世界のすべての国々のために平和維持の貢献をはかる上で、十分な軍事力を保持することは絶対に必要である。[21]」と訴えるのだった。また、ワシントン・ポスト紙[22]のように「必要とあらば、軍事的措置(initiatives)」がとられることも己むをえないとする、多少控え目な論調もあった。
いずれにせよ、米国の新聞は、「危機」発生直後におけるブッシュ政権の迅速な対応を、概ね高く評価し、賛意を表明したのだった。それでは、8月8日にいわゆる「中東派遣軍」の出動命令が出された後においては、どのような社説が書かれたのであろうか。
ここでもまた、ブッシュ大統領に対する支持は驚異的なほどに高かった。すなわち、「ジョージ・ブッシュは(イラクに対し)断固たる姿勢をとっているが、これまでのところ、湾岸危機においてボタンを正しく押してきた。そして、イラクの戦車によるサウジの油田地帯への侵略を阻止し、さらにまたバグダッドの残忍な侵略者たちに対し、世界的規模の制裁を実行するために、米国軍を派遣したのである[23]。」[カッコ内:引用者注]その論調は、あたかもブッシュ政権の報道官が発言するかのような内容で彩られていた。
もっとも、米国の伝統的精神からすれば当然のことであった。なぜならば、サダム・フセインは「イラクの原油輸送用パイプラインが閉鎖された場合、サウジアラビアを攻撃すると言明」(8月6日)し、また「イラク軍のクウェートからの撤退を要求する外国からの圧力を拒否すると言明」(8月7日)して、全面対決の姿勢を打ち出していたからである。米国国民の眼には、フセインが「領土略奪犯」であり、ブッシュが「国際警察官」として映ったと思われる[24]。こうした情景を前にして、「正義の使者」に声援を送るのは、米国人の常であった。
ところが、そうした世論の熱き声援も情勢の変化に伴って、次第に冷めていく。そこには、軍事超大国をせせら笑うかのようなフセインのしたたかな戦術が介在した。8月18日、イラクのサレハ国民議会議長は、イラクに対し「攻撃的な国」の外国人を「人間の盾」として拘束すると発表したのだった。こうした非人道的措置によって、ブッシュは軍事的強硬策がとれなくなった。かくして、膠着状態に陥ると、ブッシュは焦りの色を隠しえず、米国の世論も苛立ちを覚え始めるのだった。
果して、ブッシュ大統領は9月11日、議会の上下両院合同会議および全国向けテレビを通して演説し、米軍のペルシア湾への配備に理解と支持を求めるのだった。
ところが、世論の反応は以前のような熱狂的支持とはならなかった。たしかに、全体として抽象的レベルにおいて同調しながらも、個々の点において大統領の説明に不満が表明されていった。その典型的なものは、米国政府の「計画、政策そして姿勢はこれまで明確に示されてきた」ものの、湾岸での軍事行動が「どのぐらい続き、いかなる犠牲を払おうとしているのか[25]」は不明である、といった類の疑問であった。
(2)「ヴェトナム」の悪夢
その後、フランスのミッテラン大統領、さらにはソ連のゴルバチョフ大統領などを中心にして、和平のための外交努力が続けられていく。しかし、そうした調停工作も空しく、フセインの頑なな態度を切り崩すことさえできない情況であった。
それに業を煮やすかの如くブッシュ大統領は、11月8日、必要となれば、イラクに対する「攻撃的な軍事オプション」がとれるように中東派遣軍の増強を発表した。他方、国連にも働きかけ、11月29日の安全保障理事会における「対イラク武力行使容認決議(678号)」を取り付け、国際的承認のもとでの軍事的解決も辞さない姿勢を鮮明にするのだった。
戦争の可能性を孕んだブッシュの強硬策に、いままで一枚岩に近かった米国世論も亀裂が生じ始めた。そして、大統領に抑制を求める声が高まった。たとえば、軍隊の増派は心理戦に効果を持ちうるかもしれないが、この時点で経済封鎖を放棄するのは時期尚早である。その効果が現れるまで、「しばらくは、じっと忍耐強く待つことが湾岸での最良の政策である[26]。」という社説がそれをよく示している。また、安全保障理事会が武力行使を容認したからといって、「急ぐ」必要はなく、「一年待ってもよいではないか[27]」と、ブッシュの性急なアプローチをたしなめるのだった。
では、ここに至り新聞論調の中になぜ慎重論が急浮上したのだろうか。それは多分に「ヴェトナム」の悪夢であったと思われる。もし戦闘が開始されれば、それが長引かないという保証はどこにもなく、砂漠の戦争における勝算にも不安が残った。ヴェトナム戦争の二の舞だけは演じたくないという気持ちが、ブッシュにアクセルを踏ませまいとする訴えになったのである[28]。
これに対して、戦争を覚悟しなくてはならないという意見も少なからずあった。その認識はこうだった。すなわち「われわれはイラクのサダム・フセインが一部でささやかれている現代のヒトラーかどうかは判らない。しかし、彼が実体を伴わない脅しには動じない人間であることだけは確かである。ペルシア湾における米軍をおよそ倍に増やすというジョージ・ブッシュ大統領の決定は、イラクの独裁者と国際社会との意見の対立に際し、当然かつ必要な措置だと思われる[29]。」また、国連の678決議に関する論評では、ブッシュの努力が国際社会から認められたにもかかわらず、「(国連と)同様、議会からの支持がえられないことはきわめて残念である[30]」[カッコ内:引用者注]といった見解さえみられた。
さて、その後における事態は平和的解決が益々困難な方向へと推移していく。そして、1991年1月9日における米国のベーカー国務長官とイラクのアジズ外相との直接対話も物別れに終わり、軍事衝突の可能性が一段と濃厚になった。こうした情況の中、米国連邦議会は1月12日、イラク軍のクウェート撤退を求めた国連決議を実現するために、ブッシュ大統領に武力行使の権限を付与するのだった。
いよいよ「悪夢」が現実となる日が近づきつつあった。こうした重苦しい雰囲気を反映して、新聞の論調も賛否の違いはあれ、「祈り」のトーンヘと変わっていた。戦争突入を積極的に支持する新聞はなかったものの、来たるべき時への覚悟を訴える社説はみられた。ビリングズ・ガゼット紙は次のように書くのだった。
平和を祈らない米国人がいるだろうか。われわれの兵士を好き好んで外国の地で死なすために派遣するものがいるだろうか。
しかし、戦争をしなくてはならないのであれば、徹底して戦争を始めようではないか。イラクの戦闘意志をできる限り早く削ごうではないか。われわれの男性兵、女性兵を帰還させるために、できる限り早く戦争を終わらせようではないか。
議会は大統領にイラクを攻撃する権限を与えたのだ。議論は終わった。今や、ブッシュ大統領とサウジアラビアのわが軍隊を支援する時である[31]。
他方、たとえ法的手続きに問題はなくても、武力行使を急ぐべきではなく、あくまでも平和的解決の糸口を追求するよう訴える新聞もあった。すなわち、「今晩イラク撤退の期限(1月15日)が戦争の開始である必要はない。外交は明らかに失敗しているが、殺戮、負傷、破壊をもたらす手段以外の手段を用いるべき根拠はまだ残っている[32]。」[カッコ内:引用者注]というのだった。
しかし、そうした願いも空しく、実際には戦争へと突入していく。1月13日のデクエアル国連事務総長によるフセイン大統領との直接会談は不調に終わり、1月15日になってもイラク軍の撤退はなかった。すると、ブッシュは既定の方針通り、1月16日、戦闘命令を発した。「砂漠の嵐」と命名された「クウェート解放作戦」は空爆を中心に「多国籍軍」の圧倒的優勢のうちに進行し、2月24日からの地上線を経て、2月27日のブッシュによる勝利宣言に至るのだった。
その間における米国世論に目を転じると、戦争遂行上の認識の違いや意見の対立は当然存在した。しかし、「イラク軍をクウェート領内から排除する」という戦争目的に意義を唱える新聞は、皆無に等しかった。したがって、その目的を成就するためのキー・ワードは「団結(unity)[33]]であった。実際、そうした意識は新聞以外にもみられ、ABCテレビとワシントン・ポスト紙が地上戦突入翌日の2月24日に行った世論調査によれば、「湾岸戦争」に対するブッシュ大統領の対応について、90パーセントが支持を表明していたのだった。
結局のところ、米国の世論はブッシュが提示した「大義」そのものに異議を差しはさもうとしたわけでなく、「大義」を実現するための方法論について対立したにすぎなかったのである。
4.対日イメージの構造
米国の世論がブッシュ政権に対して、総じて「良好」だったのとは裏腹に、同時期における対日世論は「険悪」そのものだった[34]。その具体的内容を解明するために、ここでも、米国の新聞を用いることにした。その言及に先立ち、対日世論の一般的特徴と思われる事柄について触れておきたい。そこには、主として、三つの特色が指摘されよう。
まず第一に、報道に関する日米間の非対称性である。政府間レベルは別にして、米国の新聞が「湾岸紛争」をめぐって日本の政策などを取り扱った記事ならびに社説は、日本のそれに比較した場合、非常に少ない点である[35]。特に、社説に至っては皆無に等しいと言ってよい。むろん、事柄の性質上、己むをえない側面はある。なぜならば、米国にとっての主たる関心事はイラクによるクウェート占領をいかにして排除するかにあったのであり、日本の対米協力はその目的遂行上の第二次的問題ないしは手段的要素にすぎなかったからである。したがって、日本のジャーナリズムが報じるほどに、米国の世論が日本の対応を必要不可欠な要素として意識したり、位置づけていたわけではない。つまり、日本の存在は、たとえば、ソ連、フランス、イギリスなどに較べると、相対的に小さな国としてしか映っていなかったのである。
第二は、対日批判の論理構造に関係する。しかも、それは「危機」発生から「戦争」の終結まで、ほとんど変化することなく続いたのである。その論理とは、次のようなものであった。すなわち、イラクによるクウェート占拠は中東の石油供給を危うくする。安価な石油で最も恩恵を更けているのは、経済大国=日本である。ところが、日本は正義のために血を流そうとする気概もなく、世界の安定のために積極的な貢献を行おうとする意思もない。結局、日本は自国のことしか考えない利己的な国である。これが、米国の対日イメージであった。
第三には、米国世論の日本に対する理解不足である。そもそも、日本が「湾岸戦争」に対して米国(政府)が求める、いわゆる「人的貢献」に踏み込めなかった背景には、日本国憲法第九条が作用していたことはあきらかである。ところが、こうした日本の国内的制約条件は、多くの米国人には知識の範囲外であった。また、マス・メディアもそうした特殊条件を積極的に取り上げて、大衆に理解を促す努力はしなかった。その結果、対日不信は益々募るばかりだった。
そこで次に、具体的認識に議論を移そう。実際には、当然のことながら、第二および第三の特色を取り扱うことになる。
(1)消極的役割への怒り
先にも指摘したように、米国の新聞は「湾岸紛争」をめぐって、日本と関連する記事や社説に多くの紙面を割いているわけではない。社説の場合、ロサンゼルス・タイムズ紙を除けば、日本の対応はほとんど取り上げられていない。したがって、対日認識の手掛かりを社説以外の一般記事ないしは論説にも求めざるをえない。一般記事については、そこに主張や見解を見出すことは困難である。ところが、各記事の見出しの付け方の中に、当該事象に対するデスクの姿勢をうかがい知ることができるのである。
まず、「危機」勃発直後における日本の対応について、ボストン・グローブ紙は次のような見出しを付けて報じていた[36]。すなわち、「躊躇の後に、日本は対イラク制裁に同意する」であり、「世界的役割に関する日本の優柔不断」となっていたのである。
また、ロサンゼルス・タイムズ紙の社説は日本が憲法上の制約を抱えながらも、「積極的参加の力」を有する国だとして、こう訴えるのだった[37]。「湾岸地域が安定した場合の主要受益国は日本である。もし同地域が混乱に陥ったとき、多大な損害を被るのは米国や英国でなくむしろ日本なのである。日本は資金援助の提供は行えうるのだ。たとえば、国連安全保障理事会による何らかの平和維持努力がなされたとすれば、その費用を負担することである。それはすばらしい政策であり、新しい友を獲得し、多くの人々に影響を与えていくことになろう。」
ところが、日本の「多国籍軍」への協力は米国の期待通りには進まず、対日不満は高まるばかりであった。シカゴ・トリビユーン紙の社説はこう記すのだった[38]。「日本はもはや世界の出来事において傍観者でいることは許されない。それは莫大な資金をもっぱら自分のためにしか使っていないようなものだ。日本は国際的指導国としての地位を獲得するために、実際、その資格を有するのであるから、世界の平和と自由貿易を促進させるために断固、行動を起こさなくてはならないのである。」
こうした認識は1990年11月初旬の国連平和協力法の流産によって不動のものとなり、その後、90億ドルの追加援助が決められても変わることはなかった。その結果、「湾岸紛争」を回顧して、「米国は戦争に対する日本の消極的役割に激怒した[39]」のだった。しかもアマコスト(Michael H. Armacost)米国駐日大使の「通知表」によれば、日本の成績は「すべてC(straight Cs)[40]」評価だったのである。
(2)憲法第九条をめぐる矛盾
確かに、米国の立場からすれば、そうした対日不満も理解できないわけではない。しかし、米国の論理ないしは「大義」を首尾一貫させようとすれば、日本は憲法改正をも含む抜本的態度変更を行わない限り、米国の要求に応えられない困難な立場にあったのである。その点、米国の世論は矛盾を孕んでいた。すなわち、「人的貢献」をも含む積極的な協力を日本に求めつつも、憲法第九条は現状のまま避けて通ったのである。
その背後に潜む心理は、日本の軍事大国化に対する恐れであろう。たとえば、ローウェン(Hobart Rowen)はワシントン・ポスト紙の論説において、その点を指摘している[41]。日本やドイツが第二次世界大戦中にアジアおよびヨーロッパにおいて行った数々の軍事的横暴は余りにも多くの人々の記憶に焼きついている。「もし湾岸戦争における役割分担の必要性が誤って判断され、それが日本やドイツに対し、再軍備化への裏口を提供することになれば、悲劇である。」それゆえ日本やドイツに軍事行動の協力を求めるべきではない、とするのだった。
同様の発想は、自衛隊を湾岸へ派遣することに対する日本人の根強い反対を紹介するという方法をもって示されている。たとえば、ヴァイスマン(Steven R. Weisman)による「日本人の軍国主義への恐れが自衛隊の湾岸派遣への反対の原動力[42]」という見出しで始まる記事は、その典型である。
日本が「湾岸」の対応に苦慮し、「優秀な成績」を米国から獲得できなかった背景には、まさにそうした「歴史的経緯」および「第九条の存在」があったからである。ところが、米国人の視界には日本人の「苦悩」はあまり入らなかったのである。現に、「第九条」を全面的にとりあげて論じているものはきわめて少なかった。唯一の例外と言ってよいのは、サンガー(David E. Sanger)による記事「日本人はなぜ刀をさやから抜くことが困難か[43]」である。しかし、この記事も「第九条」の「拘束」を紹介しつつも、どうすべきかといった政策論にまで踏み込んではいない。
かくして、米国の世論は日本の特殊事情に対する根本的ディレンマには触れず、もっぱら現象面だけを米国的視座から捉え、日本の貢献は「あまりにも少なく、あまりにも遅い[44]」と批判するのだった。
5.おわりに
以上の考察よりわれわれは何を導き出すことができようか。
第一には、ブッシュ政権による「湾岸紛争」への対応が、文字通り米国の伝統的思考に則っていた点であろう。ブッシュ大統領の真の意図がどこにあったかは別にして、少なくとも公にされた「大義」は「専制と野蛮な侵略」を除去し、「法の支配」を確立することであった。それは紛れもなく、法律主義的かつ道徳主義的外交態様として位置づけられるものであった。
第二には、そうしたブッシュ外交に連邦議会もまた支持を与えた点である。むろん、反対意見がなかったわけではない。しかし、それは目的遂行のための手段・方法をめぐる見解の相違にすぎず、目的そのものに疑念を差しはさむものではなかった。
連邦議会に関するもう一つの特徴は、多数の議員が「湾岸戦争」を国内政治の文脈の中で捉え、それに基づいて行動した点である。その結果、議員が対外的問題を国内の政治目的に利用しようとする姿勢が浮き彫りされたことである。
第三には、新聞論調にみられる米国の世論動向であるが、ここでもまた、ブッシュが唱導した米国的「道義」への共鳴が明確になった。もっとも、実際の戦闘行動の可能性が高まるにつれ、「ヴェトナム・シンドローム」にさいなまれ、「共鳴音」が弱まったことも確かである。
第四には、「湾岸紛争」における日本の対米協力は客観的に見て多大なものであったにもかかわらず、多数の米国人の目には正反対のイメージとしか映らなかった点である。その原因は、米国的価値観がストレートに投射されたため、日本が有する特殊条件に理解を示すまでには至らなかったからである。
要するに、米国にとっての「湾岸紛争」は米国の伝統的対外態度が鮮明に示された典型的事例であったと言えよう。