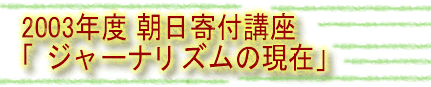
第6回 2003年5月21日(水)
「メディアの変容とジャーナリズム」
井上 実于(HTB北海道テレビ放送)
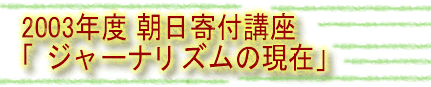
第6回 2003年5月21日(水)
「メディアの変容とジャーナリズム」
井上 実于(HTB北海道テレビ放送)
| 抄 録 |
|
私は、新聞、インターネット、テレビという、3つのメディアを渡り歩いた数少ない一人だと思います。昨年のあるシンポジウムで、音先生から「3つのメディアを経験する中で、視聴者や読者はどのように映ったか」と尋ねられました。ポイントをついた、とてもいい質問だと思いました。 駆け出しのころ、地方記者の時代は、情報の受け手とは、近所のおばさんであったり隣のお店の主人であったりしました。記事を書くと、反応をすぐ間近に感じることができました。つまり、日々の暮らしの中に、私の記者活動があったのだと思います。 6年後には東京本社の政治部に移り、田中派と呼ばれる永田町の政治家軍団を追いかけながら、記事を書きました。読者は私の目の前から姿を隠してしまいました。あえて言うなら、いつも付き合っている政治家や役人の、私の書いた記事に対する反応の仕方が、私にとっての「読者」だったと思います。 そのあと、インターネットのアサヒ・コムの初代編集長を務めました。読者は「ユーザー」と名前を変え、数万人、数十万人という巨大な塊が、パソコンの画面の向こうで情報を見ているという感じでした。ヒット数という、アクセス数を類推させる数字で、記事への反応はたちどころに分かりますが、表情や想いは全く見えない、新聞にはない世界でした。メールも届きましたが、たいていはぞんざいな文章で、一方通行でした。 これに対して、テレビの視聴者というのは「視聴率」という数字、これ以上でもこれ以下でもない、それがすべてです。しかし、この仕組みにはどこかにウソがある。テレビの電源が入っているだけで、本当は見ていないのかもしれない。サンプル数も少ない。それなのに放映の翌朝は、調査会社から届けられる視聴率の数字をながめながら、テレビ局全体が一喜一憂しているという、不思議な光景が繰り広げられる。これがテレビにとっての読者(視聴者)そのものでした。 私はメディアに30年関わってきましたが、振り返ってみると、最初の駆け出し記者のころがいちばんよかったなと思います。自分の書いた記事が、読み手にどのように受け取られているか、具体的な反応がすぐに見える。それを踏まえて新たな記事を書く、そんな繰り返しは、地に足をつけて仕事をしているという充実感にあふれていました。そのあと政治記者になり、インターネットに携わり、テレビ局で働くようになって、情報の受け手はますます遠い存在になっていきました。 インターネットの世界から一時期、最末端の地方取材の現場に、再び舞い戻ってみました。駆け出しのころの充実感をもう一度味わえるに違いないという期待がありました。しかし、みごとに裏切られました。そこには30年前のような、自由奔放で自信にあふれた活動の舞台は、息づいていませんでした。新聞を取り巻く状況が、すっかり様変わりしてしまっていたからです。 30年前は、社会の問題点に切り込み、世論を喚起し、社会をより良い方向に動かしていくという、そんな意味で、新聞記者は「憧れの職業」だったように思います。幸せな時代でした。しかし今では、インターネットの登場をきっかけに、誰でもがマスメディアと対等に情報発信できる時代になり、広く、素早く発信することがマスメディアの特権ではなくなりました。 情報を手に入れる手段は新聞だけではなくなり、読者の眼は格段に厳しさを増しています。しかし、新聞は取材から配達まで、昔のままのやり方で仕事を続けている。周囲が変わっているにもかかわらず、マスメディアは変わらないから、そこに摩擦が起こる。それが新聞批判、テレビ批判、ジャーナリズム批判、メディア批判という形で噴出し、メディアの自信は揺らいでいるように見えます。 相対的に、マスメディアの優位性、権威が薄れてしまった。インターネットのニュースサイトでは速報性を重視していますが、ジャーナリズムにとって速報性がどういう意味を持つのかという考察は十分ではなく、どちらかというと、速報性に付随する広告収入やビジネス性への期待の方が先走っています。 そうした中でも、マスメディアを取り巻く経営環境はますます厳しくなっています。新聞の購読部数は頭打ちです。一方でテレビは、地上デジタル放送への移行を前に、巨額の投資を強いられ、地方では放送局がつぶれたり、放送局間の統廃合が行われたりする時代がやってくるとも言われています。市場経済の厳しい論理が、マスメディアをさらに揺るがすに違いありません。 最近、拉致被害者の曽我ひとみさんが、家族の住所を報道されたというので、朝日新聞に抗議する出来事がありました。紙面に掲載された住所情報を基に起こりうる事態を考えてみれば、記事が配慮に欠けていたことは否定できないと、私も思います。私の経験から想像すると、書いた記者は他紙に出たニュースを追いかけるつもりで、裏付けとなる住所情報を新たに付け加えたうえで出稿したのではないでしょうか。 私も駆け出し記者のころ、デスクや先輩から「抜かれたら、抜き返せ」と教育された一人です。そのために、少しでも新しいデータはないかと、眼を皿のようにして探し回ったものです。しかし、近ごろはそれだけでは済まされない時代になってきました。価値観の多様化とともに、記事にはさまざまな視覚が求められ、記事が及ぼす影響に対する配慮も、従来とは比べものにならないくらい必要になっています。 真実を明らかにしようとするジャーナリズムには、事実を探り当てていく過程で、ある種の「牙」のようなものが必要とされますが、単純な「牙」だけでは、読者はもう納得しません。とくに、紙面づくりのあれこれを判断する役目を任されているデスクには、取材記者以上に繊細な注意が求められていると思います。曽我さんの記事が社内のチェックをすり抜ける形で、最終的に紙面に掲載されてしまったということは、報道に注がれている読者の「眼」の変化に、メディアの側がまだ十分についていけていないことの表れの一つであるようにも感じます。 この例だけではありません。紙面や組織に根強く残る縦割り主義、記者クラブ依存の取材システム、会社人間化した記者集団。こうした批判は、メディアがなおも「身内の論理」「業界内の論理」で仕事を続けているという、情報の受け手たちからの不満の声です。記事は無署名で、社外からのクレームにはたいていは広報セクションが対応し、書いた記者の責任はあいまいになりがちです。これで読者や視聴者が、メディアを開かれた存在と受けとめてくれかどうか、不安です。 そろそろまとめになります。メディアを取り巻く環境が変化する中で、メディアはどうすべきなのでしょうか。私はここで「雑草の文化」「ごちゃまぜの文化」を提唱したいと思います。たとえば、アメリカ社会の強さは、さまざまな出身や考え方の人がいることにあると言われます。日本は金太郎飴のように横並びで均一な社会ですから、誰かがころぶとみんながころんでしまって、元気がありません。 メディアも「モノトーン情報」「モノトーン取材」「モノトーン紙面」から脱出すべきだと思います。フリージャーナリストや地方紙を仲間に加えて、素材を多様化する。新しい情報技術を使って、取材方法を工夫する。アウトプットも多種多様に。新聞だ、テレビだというのは単なる媒体の話で、大切なのは何を発信するかです。「若者の活字離れ」も間違い。携帯画面だって活字なのですから。要は、アウトプットの仕方が若者の流儀に合っていないだけなのです。 記者採用のシステムも、もっといろいろなやり方があっていいと思います。何よりも肝心なのは、記者自身の活動が多様化すること、つまり、会社人間、サラリーマン記者にならないことです。そのためにも、メディアや会社組織の外にある多種多様なエネルギーをもっともっと活用し、記者自身やメディア自身を、絶えずリフレッシュしていったらいいと思います。 私がいま籍を置いている北海道テレビ放送(HTB)は「地域の未来戦略に貢献する」を社是としています。ホームページをご覧いただけばお分かりになりますが、道内の幅広い人たちと手をつなぎながら、新しいメディアのあり方、新しい地域社会のあり方を探っていこうと、日夜努力しています。 中央のメディアは嵐のごとくむしり取り、嵐のごとく去っていきますが、地方のメディアは地域とともに暮らしていますから、絶えず批判にさらされ、逃げ隠れすることができません。その意味でも、自分の方から地域の発信者や情報の受け手たちとかかわっていかざるを得ません。たいへんエネルギーのいる仕事ですが、そうした試みの中から、中央のメディアが失いつつあるものを地域に根付かせ、新しいジャーナリズムの形を育て上げることができるのではないかと信じています。 津田恵香(文・新聞学科3年) |