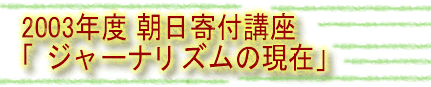
第2回 2003年4月23日(水)
プロの世界で起こっていること
鈴木規雄(朝日新聞社「報道と人権委員会」事務局長)
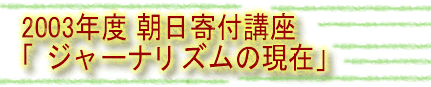
第2回 2003年4月23日(水)
プロの世界で起こっていること
鈴木規雄(朝日新聞社「報道と人権委員会」事務局長)
| 抄 録 |
|
いま、ジャーナリズム環境が大きく変化している。それに対応して「変えるべきもの」と同時に、「変えてはならないもの」がある。根幹は、取材し、伝えること。技術革新で仕事の方法、伝達手段は変わっても、第一発信者としての記者の基本は変わらない。揺らぐ現場から、「報道とは何か」「報道の社会的役割は何か」について、改めて考えたい。 |
| 「変わる」現場 |
|
地殻変動の要因はいくつかある。 (1)まず、高度情報通信社会の出現がある。朝日新聞は「複合メディア体」をめざしているが、IT化で現場の記者たちの仕事も変わってきた。象徴的なできごとが、広島支局での記事盗用だった。朝日新聞2000年6月8日付の主張・解説(オピニオン)面に掲載した核不拡散条約再検討会議についての解説の一部が、中国新聞の記事からの無断引用だったことがわかった。パソコンで記事を書くことで、画面上での切り張りが抵抗なくできるようになったのも原因の1つだ。たとえば、簡単なお知らせ記事を前の同じ催し記事の固有名詞など一部修正するだけで書く。うっかり修正し忘れ、 肝心の期日が昔の記事のまま、載ってしまう。事件が起きても、すぐ現場にとび出さずに、まずパソコンに向かう記者もいる。何よりも大切な現場感覚が薄れつつあるのでは、と心配している。ホームページなど電子媒体によるニュース発信が始まり、記者の仕事は24時間体制になった。通信社化により、時間をかけた深い取材や分析がしづらくなる懸念もある。 (2)読者の変質。若い世代の新聞離れが加速、無読層が増えている。情報収集の手段も多様化し、個人からの発信も可能になった。 (3)この時代、新聞企業として生き残るのための商業主義とジャーナリズム性との相克も深刻になってきた。「書きたい」から「読みたい」記事への変化は、新聞のエンターテイメント化(=インフォテイメント)を促す。アメリカで、調査報道が「金食い虫」として衰退したのも、その1例だろう。 (4)メディアと市民と公権力の位置関係も変わった。公権力による市民の「保護」「擁護」のためのメディア規制3法案は、その表れだ。市民がメディアとでなく、公権力とスクラムを組んでいる。その動きの背後には、厳しい市民のメディア不信がある。 (5)政治社会情勢の変化も、紙面づくりの質的変化につながる。国旗国家法やガイドライン関連法が相次いで成立したのに続き、テロ特措法、有事法制の議論まで、日本の針路の基軸変化の背景には、復古的ナショナリズムの動きもある。そんな中で、新聞の2極化もきわだってきた。たとえば、藤田博司・上智大学教授のレポートからも分かるように、9.11以降の、米国の軍事行動や自衛隊の海外派遣について新聞に掲載された意見を調べると、読売は不支持の意見がゼロで産経は少数であるが、朝日、毎日は支持、不支持、中立の意見が広く紹介されていた。 |
| 「変える」改革への取り組み |
|
これらの変化に対応して、現場が反省し、「変えるべき」点も少なくない。朝日の例で言えば、90年代はじめから、各本社の社会部デスクが集まって月に1回、「事件報道小委員会」を開き、事件報道のあり方について議論している。取材や報道の指針となる「手引き」も、その委員会の論議をもとにつくり、改訂を重ねている。容疑者呼称や、連行写真の掲載をやめるなどの見直しが行われてきた。たとえば精神障害者に対しての匿名・実名の問題。刑法39条の「身神喪失者の行為は罰しない」に基づき、その場合は匿名報道にするが、刑事責任を問えないことがはっきりするまでは実名で、とルールを変えた。匿名では精神障害者一般が「危険だ」との偏見を助長しかねない、という家族関係者の指摘を受けとめたものだ。池田小学校事件では、発生直後の夕刊段階では匿名にしたが、朝刊で実名報道に踏み切った。現場の意見もいろいろ分かれ、決断は大変だった。また報道陣が事件や事故の関係者に殺到する集団的過熱取材(メディアスラム)への対応もとられるようになってきた。被害者・家族取材の基準づくりや記者たちによる勉強会も始まった。 また「紙面審議会」や「報道と人権委員会」(PRC)の取り組みもある。PRCは報道被害の迅速な救済のために新たにつくられた第3者機関だ。朝日新聞では年間300〜400件のお詫び・訂正を載せている。現場と相手側との話し合いで解決しない場合は、PRCに申し立ててもらい、社外の3人の委員が救済策などを議論している。自由な取材・報道のためには法による規制ではなく、こうした自主的な取り組みが重要だ。 |
| 「変わってはならぬ」自由な取材・報道 |
|
しかし、どんなにジャーナリズムをとりまく環境が変わっても、どのような改善策、対応策がとられようが、「変わってはならぬこと」がある。それは、自由な取材と報道である。この問題を考えるとき、私の出発点は、朝日新聞襲撃事件(116号事件)だ。1987年5月3日に朝日新聞社阪神支局内で、小尻知博記者が散弾銃の男に射殺され、記者1人が負傷した事件である。みなさんにとっては、遠いできごと、無関心な事件かもしれないが、116号事件から「新聞の責任」「記者の仕事」が何なのか、いま、私たちがどんな時代、歴史の流れのなかに生きているかが、見えてくる。あの散弾銃の銃口は、つまるところ、市民一人ひとりに向けられたものだと言うことができる。言論表現の自由は民主主義の基盤である。憲法21条は表現の自由を保障しているが、それは「報道機関の自由」を意味しているわけではない。一人ひとりの市民の自由をさしている。その市民の自由が、いまどうなっているのか。実態を追ったのが長期連載「『みる・きく・はなす』はいま」だ。この16年間、この連載にずっと関わってきたが、その仕事からも、自由な市民社会なしには、自由な報道は存在し得ない、と実感させられている。言い換えれば、報道の社会的な責務は、自由な、民主的な市民社会の実現にこそある、そう私は確信している。記者に向けられた銃口は、そのまま、自由を、民主主義をめざす市民にこそ向けられたものなのだ。 犯行声明は「反日朝日は五十年前にかえれ」とある。半世紀前の「もの言わぬ新聞」にかえれ、という。その脅しに屈するわけにはいかない。「もの言う新聞」を、どう実現するか。それを116号事件は記者に、市民に問いかけている。そこに事件の普遍的な意味があると思う。戦争になってしまったら、新聞は実は弱い。「戦争の最初の犠牲者は真実」という言葉もある。だからこそ、その前に、戦争を防ぐ。そこに報道の目的がある。報道の社会的な責任がある。いま、その責任を果たしているかどうか、が問われている。 |
| 「攻めのジャーナリズム」への期待を |
|
新聞の責任を果たすために、事件報道の改善をはじめ、自省とマイナス面をなくす努力は必要だ。しかし、それだけで十分か。失った市民の信頼を回復するためには、メディアと市民の距離縮めるためには、読者と共に考え、共感し、紙面を通じて読者と対話することが必要だと考える。それが、私の言う「共感のジャーナリズム」だ。公権力の監視、隠された不正義の発掘、平和への希求という、本来の社会的義務を果たす「攻めのジャーナリズム」が求められている。そうした報道の有効性、プラスを積み上げることでこそ、市民の報道への信頼感を取り戻すことができる。いまも努力は続いている。情報公開請求をめぐる防衛庁リストや偽装牛肉事件の掘り起こしは、その例だ。 こうした激変の時代だからなおさら、記者としての強靭なこころがほしい。読者との双方向性に努め、テーマ性豊かなメッセージ力を持つ紙面づくりをする必要がある。そのために複眼的な思考、柔軟な発想など、記者として自分で自分を鍛えるべきだ。企業ジャーナリストには違いないけれど、社内で自由に発言する気構えも、また。みなさんは、みんながみんな記者の仕事をめざしているわけではないだろうが、現場の実情を知り、「読む」側としての批判力をもつことが、ふつうの若い人たちにとっても大切だと考えてお話した。同時に揺らぎ、もがきながらも、なんとか自分たちの責任を果たそうとする「記者」たちへの理解と、彼らが取り組んでいる「報道」への期待を、ぜひ持ち続けてほしい。それが、「現場」への力になると信じている。 葛西 諒子(文・新聞学科2年) |