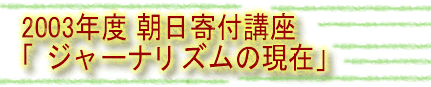
第1回 2003年4月16日(水)
揺らぐ日本マスメディア
清田 治史(朝日新聞総合研究本部)
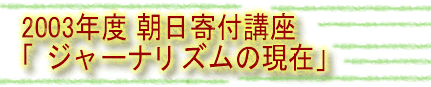
第1回 2003年4月16日(水)
揺らぐ日本マスメディア
清田 治史(朝日新聞総合研究本部)
| 参考文献 |
| * 「ジャーナリズムの原則」ビル・コヴァッチ・トム・ローゼンスティール(日本経済評論者) * 「デジタルメディア社会」水越伸(岩波書店) * 「メディアリテラシー 世界の現場から」菅谷明子(岩波新書) * 「報道は欠陥商品と疑え」鳥越俊太郎(ウエイツ) * 「大統領とメディア」石澤靖治(文春新書) * 「アメリカの報道評議会とマスコミ倫理」朝倉拓也(現代人文社) * 「包囲されたメディア 表現・報道の自由規制3法」飯室勝彦・赤尾光史編集(現代書館) * 「人権か表現の自由か」田島泰彦(日本評論者) * 「新版 現場から見た新聞学」天野勝彦・生田真司編著(学文社) * 「新聞の病理」前沢猛(岩波書店) * 「アメリカの報道評議会とマスコミ倫理」朝倉拓也(現代人文社) * 「検証 事件報道」井上安(宝島社) * 「個人情報は誰のものか」毎日新聞・情報デモクラシー取材班(毎日新聞社) * 「表現の自由が呼吸していた時代1970年代 読売新聞の論説」前沢猛(コスモヒルズ) * 「新聞『第3者機関の背後』」(「総合ジャーナリズム研究」2001・春) * 「メディアと市民・評会議の可能性」(「世界」2000・10月号) * 「朝日新聞の調査報道」山本博(小学館) * 「戦争報道の内幕」フィリップ・ナイトリー(時事通信社‘87) * 「戦争ゲーム」ハルバースタム、筑紫哲也訳(講談社) * 「戦争特派員」ピーター・アーネット(新潮社) * 「BBC イギリス放送協会パブリックサービス放送の伝統」蓑葉信弘(東信堂) * 「戦争記者」武田徹(ちくま新書) * 「戦争広告代理店−情報操作とボスニア紛争」高木徹(講談社) * 「戦場特派員」橋田信介(実業之日本社) * 「ブラックプロパガンダ」山本武利(岩波書店) |
| 抄 録 |
|
イラク戦争は、今でもまだ散発的な攻撃は続いているが、ほぼ終息したと言える。報道も、これからのイラクの暫定政権をどうするのか、復興をどうするのかという方向に主題が移り変わっている。ごく最近のイラク戦争のハイライトは、バクダット陥落だ。巨大なフセイン像を民衆が思いっきり引き倒し、その頭の部分を町中に引きずる映像は、フセイン政権の崩壊を象徴するものとなった。 アメリカのABC放送は、この映像が巧妙にメディアの手によって脚色されたものとなっていたことを検証している。アップに撮影されたフセイン像を倒す映像では、群衆がたくさんいるように見える。しかし、実際にはごく一部の民衆しか集まっておらず閑散としていたのが事実だ。さらに、フセイン像の頭を引き回しているのは、18人中7人がカメラマンだと言う。私たちは、それらの映像を見て、イラクの民衆がフセイン政権から解放されたことをとても喜んでいるように思っていたが、果たしてそうなのだろうか。バクダットの民衆は、米英軍のバクダットへの侵攻を心から喜んでいるのだろうか。「やらせ」とまでは言えないにしても、実態と微妙にずれた報道をしているのは事実である。真実を伝えるのは難しい。それを象徴する出来事であった。 バクダット陥落のころには、日本の記者や報道機関等は現地から撤退していた。この事実は重い。湾岸戦争の時、CNNのピーター・アーネットはひとりで残った。しかし、やはり日本の記者はまったく残っていなかった。現地に残るかどうかは外信部長会議で決められた。湾岸戦争では、ある日を境に全員引き上げた。残りたいと願った記者もいたが、上の指示でそれは無理だった。今回のイラク攻撃では湾岸戦争よりもかなり性能の高いピンポイント爆弾が使われている。しかし、何が起こるかわからないし、安全だという補償はない。ということで結局一斉にではないが、日本は今回も空爆開始前にバクダットからひいてしまった。実際、米、英、そして攻撃に反対しているフランスのメディアは現地に残っており、現地から生の報道をしている。日本のメディアは、フリーランスの記者、NGO、人間の盾、映像集団等々にお願いをして情報を得る形となった。 人の命はもちろん重いし、撤退の判断も理解できる。しかし、仮に日本の報道陣がテレビ中継された映像を直接、見ていたならば、もう少し冷静な判断が出来たかもしれない。キャプションで100人の群集しかいなかったと入れることもできたろう。 |
| 戦争報道の系譜 |
|
クリミア戦争が従軍記者の始まりと言われている。1851年に経済状態を伝えるためにロイターが開設され、同じころ、後のAP通信になる母体も生まれた。要するに、国際ニュースが近代的な形をもって登場してきたのだ。タイムスのW・H・ラッセルが報道した英軍がロシア軍に壊滅させられた記事は有名である。この後、国家間戦争、報道戦争、内戦も含んで戦争が相次ぐ。 欧米のメディアが戦場に勢ぞろいして大々的に報道合戦をしたのが日露戦争(1904〜1905)だ。当時、イギリスでは、ロンドン・タイムスを始めとして怖いくらい日本ひいきの報道がされた。これには、当時の大英帝国がロシアのアジアへの南下を阻止するという戦略的な国家目標が、背景にあった。国家の目標に沿うような形で、イギリスのメディアも戦況を報じたわけである。有名なバルチック艦隊を日本は撃破するわけだが、あの時点で日本軍は、ほとんど補給を使い果たしてしまい、新しい戦闘に向かうゆとりはなかった。しかしイギリスメディアを中心に、日本に対して肯定的な報道が世界を駆け巡り、それに背中を押されるような形で、日露が講和会議に進んでいった。国家の利益、イギリスにとっての対ロシアの国家的戦略の利益に沿った戦争報道が、イギリス・メディアでは行われたことになる。 第一次世界大戦では、報道の乱れは凄まじかった。米・ジョンソン上院議員が戦後「戦争の最初の犠牲者は真実だ」と述べたほどでっちあげ報道が多かったという。大メディアの典型例として挙げられるのが、イギリス、フランス、ベルギーのメディアである。ドイツ軍が暴虐な限りを尽くしているというドイツ批判一色の報道した。例えば、ドイツ軍が赤ん坊の手をたたき切ったとか、それを食べたとか、根の葉もない虚報を流していた。どれも曖昧で情報に信憑性がない。さらに、虚報が虚報を生んで悪循環になってしまった。そうしたものが平気でまかり通ったことは今では信じられないことだが、メディアにとっては大変痛恨な時代だった。 ベトナム戦争では、記者がほとんど自由に戦場にいけた。現地まで一緒にヘリコプターに乗って連れて行ってもらったり、帰りも飛び乗ったりと本当にフリープレスを実感できた。大メディアだけでなく、登録さえすればフリーランスの人々も自由にアクセスできるようにアメリカはしていた。しかし、汚い戦場の場面が流されたことによって反戦運動が盛り上がり、仕舞いにアメリカは撤退に追い込まれていく。アメリカの軍は「メディアのせいで負けた」とよく言っていたが、フリープレスを理想に掲げるアメリカは、ある意味それが理由で自ら敗退に追い込まれたとも言えるだろう。 ベトナム戦争によってアメリカ政府は、メディアを野放しにするのではなく、管理しなくてはいけないという方向に転じる。戦争に勝つには、メディアを誘導していかなくてはならないからだ。戦時、メディアの管理強化が始まる。その最初がグレナダ進攻だった。アメリカのメディアが駆けつけようとしたが、ちょうど手前で止められてしまう。10数人くらいの記者だけが現地に入ることを許された。その現地入りを許可した記者は、許可されなかった記者たちに現状、現地の様子等を教えてもいいことになった。これが、戦争における「プール(代表)取材」の始まりである。 湾岸戦争では、兵士の血が流れる場面はほとんどメディアで流されなかった。サウジの従軍の本部には1600人くらいの記者が殺到したが、同行を許可されたのは100人だけだった。また、戦闘が大体終わり、ほとんど片付けられた残骸がちらほら残るぐらいの頃にしか入れてもらえなかったからだ。そのため残酷な映像は撮れなかった。この戦争の始まりは、ピーター・アーネットが残って報道した、夜空に大器砲艦の玉がダンダンっとあがっていったり、トマホークが夜空に明るい雲をあがらせる、まるで一枚の絵か映画を見るような映像だった。ピンポイント爆撃ばかりが行われたわけではなく市民の被害も出たわけだが、それを裏付ける映像はほとんどなかった。 また、戦争と広告代理店がミックスされた証言が多かったのも事実である。例えば、油まみれの水鳥の写真をイラクの環境テロのせいにしたり、在米イラク大使の娘に正体を隠し、偽りの証言をさせたりした。 |
| 9.11 |
|
9.11は、アメリカ本土がはじめて直接攻撃を受けた事件である。パールハーバーにつぐ衝撃だったと言われている。非常にエモーショナルな空気にアメリカが一瞬で包まれた。9.11の衝撃は、ブッシュ政権の中で「単独主義」派を勢いづかせ、テロリストに対する先制攻撃、予防攻撃を、テロリスト集団、もしくはそれを支援する国家に対し、やられる前にやってしまおうという路線が強くなった。それがアフガン戦争につながるのだが、この戦争は史上最も取材できなかった戦争と言われている。プール同行が許されたのは実際に空爆が始まって3ヶ月以上たったあとだった。アメリカ軍は、「アフガン攻撃は特殊作戦であり、ビンラディンとその中枢のメンバーを捕まえるためには特殊部隊を送り込むしかない。秘密の保持が必要なため、情報管理はやむをえず、メディアに対しても厳しくしたのだ」と説明した。 それに比べ、イラク戦争は事前に動きがだいぶあったため、アメリカのメディアも、ワシントンのナショナルプレスクラブを中心に、去年の早い段階からホワイトハウスに対して、もっとオープンにするべきだと一致結束して要求した。ブッシュ政権も、サダムが西側のメディアを利用してくる可能性があると思い、ならばこちらもメディアを利用していこうという計算がすでにあったのだろう。同行記者をかなり大量に許可した。 フセイン死亡説をメディアで流し、イラク側のリアクションで出方を見たり、フセインやフセインの幹部の居場所を突き止めようとしたり、メディアを使った様々な情報操作が行われた。軍側がメディアを戦局、戦略に利用としたのは明らかである。報道側もそれを分かりながらも、その都度の戦況を24時間連続して流しているものだから、どうしても事実について十分に検証されないままたれ流されてしまう。そうしたものは、事後でもいいから、日本メディアも含め、どの部分が事実でどこが虚構なのかはちゃんと検証しなくてはならない。 メディアそのものも軍事利用されてしまったということもある。例えば、ある司令官が言っているのだが、バグダットに一気に本格突入するかしないか迷っているときに、シーア派住民の多い所で住民たちが騒ぎ、統制が外れているという場面のテレビ映像が流され、バグダットに突入するきっかけ・作戦を作った。いろんなことがあるが、メディアの戦争における危うい利用のされ方はとても残念である。 最後に、戦争報道で一番気をつけなくてはならないと思っているのが、その時々の戦況とか戦争の位置づけをしっかりしなくてはならないということだ。客観的に対応、分析しなくてはならない。それから、その時々の放送も大事だが、それ以上に事後の検証が大事だ。どうしても時間に追われる中で個々のニュースを垂れ流しざるをえない。おかしいと思ったら臆せず、報道の是非を検証しなくてはならない。 戦争というのは、普段想像もつかないような事態が展開していくことであり、安全保障の考え方がそれを境にころっと変わってしまうことが少なくない。例えば、9・11の衝撃を受けるなかで、日本の自衛隊が初めて日本の領海以外に出て行くことにつながった。戦争という、平時ではとても考えつかない大きな物理的な渡り合いがあると、その動きに飲み込まれ、私たちの日常的な感覚が失われがちである。冷静な判断力が希薄になるなかで、思いもよらなかったような方向に流されていってしまうといったことが起きがちである。それも戦争報道の一つの側面として、ジャーナリズムが心がけなければならないことだと思っている。 杉浦友紀(文・新聞学科2年) |