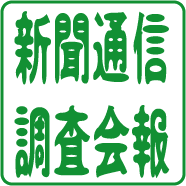 |
新人採用とインターン制
1999年5月号
|
|
|
|
| この原稿が読者の目に触れるころは、来春大学を卒業する学生たちの就職活動が山を越えていることだろう。マスコミ各社を含めて大手の企業はほぼ採用予定者を内定しているはずである。内定をもらった学生たちはひとまず安心し、もらえなかったものは、さらに就職活動を続けなければならない。 これまでも大学四年生の前期は、いわゆる会社訪問やらセミナーやらで、落ち着いて勉強できる雰囲気ではなかった。昨年、就職協定が廃止されてからは、就職活動の時期がさらに早まり、今年はすでに三年生の後期から、一部の民放などで始まっていた。「大学は事実上三年制になりましたね」と、大学の同僚はぼやく。 |
選考、おざなりな印象も
時期だけの問題ではない。選考の方法にしても、現在行われているやり方が最善かどうか、大いに疑問がある。たいていの企業は最初に「エントリー・シート」と称する申し込み書を書かせ、そのあとで筆記試験や面接をさまざまに組み合わせて何回かふるいにかけている。
応募者がそれほど多くなければ、この方法でいい人材を見つけることもできるかもしれない。しかし志望者が多数になると、選考作業はそれほど容易ではあるまい。
NHKや一部の大手民放では今年、一万人をはるかに超える応募があったという。有力新聞社の場合も、数千人単位の志望者が殺到したらしい。選考は「予備面接」や申し込み書の出来の良し悪しで何分の一かに絞り込み、さらに筆記試験と何回かの面接を通して最終的に内定者を決定する形が普通のようだ。
こうした選考の方法は、受験した学生たちに言わせると、あまり評判がよくない。多くの学生が共通して指摘することの一つは、選考の基準が不明確で、少なくとも初期の段階ではおざなりの印象が拭えないということ。わずか数分の「予備面接」では「お茶のみ話」以上のことは聞かれなかった、という声が少なくない。簡単な志望動機を書き込む程度の申し込み書の審査だけで、筆記試験さえ受けさせてもらえない学生が割り切れぬ気持ちになるのも無理はない。要するに、自分たちの能力や適性をきちんと公正に評価してもらえているのだろうか、という不安と不満である。
このことは、採用する側にも分かっているらしい。ある民放で採用試験を担当する立場にある友人の話を聞くと、多数の志望者をふるいにかける初期の選考では、その方法が多少おおざっぱになることもやむを得ないという。能力や適性を反映した結果が常に得られるとは限らないことを認めている。
とすれば問題は、限られた期間に大学新卒予定者を対象にして一斉に実施するという、現在の採用試験の方法そのものに根ざしている、といえるだろう。
期待される記者像は
ジャーナリズムの仕事に就きたいと考えている学生たちが、こうした選考の過程でもう一つ突き当たる悩みがある。実際にいくつかの面接を経験したり、すでに現場で働いている先輩などから話を聞いても、マスコミ側が求めている人材のイメージが絞れないというのである。マスコミが必要とする人材は多様だし、一つの型にはまった人間ばかりでは困るのだが、学生たちにとってみれば、自分たちに何が最も期待されているのか知りたいところではあろう。
しかし実は採用する側にも、企業が求める人材のイメージが必ずしもはっきりしていないのではないか、と思われるフシがある。先だって一部のマスコミ関係者と大学関係者の間でジャーナリスト教育について意見交換した際、期待される「新人記者像」が話題になった。マスコミ側の一人は、忙しい現場では「理屈を言わず、黙って働く人間」がほしいという。別の一人は最近のマスコミ志望者には「志がない」と嘆いた。「志を持ち、黙々と働く人間」が最も望ましい記者像であるようだが、これは多分に矛盾をはらんでいるようにも見える。
現在のマスコミの現場はさまざまな問題を抱えている。そうした問題に直面しても、声を上げず黙って仕事をする記者を現場は求めているのだろうか。多少の「志」がある記者なら、むしろ声を上げるのが当然だろう。それとも臨機応変、時と場合で声を上げたり上げなかったりする器用さを求めているのだろうか。
これはおそらく、マスコミ各社それぞれが自社の人材に矛盾した期待を持っていることの表われのように思われる。一つは、自社の方針や環境に適応し忠実に仕事をこなす有能な「企業内ジャーナリスト」。もう一つは、自分の所属する企業の立場より公共的責任を優先して考える「普遍的ジャーナリスト」である。両者の仕事を矛盾なく遂行できる環境を確保できることが最も望ましいが、現実は必ずしもそうなっていない。
「志」ある若者を
日本の大学では本格的かつ実際的なジャーナリズム教育、ないしジャーナリスト教育といったものは行われていない。理由の一つは、現場がそれを望んでいないからである。いずれの社も記者の教育、訓練は現場で仕事をしながら施すという考え方に立っている。学生時代にジャーナリズムやコミュニケーションの理論など勉強したものは「頭でっかち」で、かえって教育、訓練の邪魔になる、という現場の幹部すらある。
それは長年の伝統と経験を踏まえた考え方なのだろうが、同時に「企業内ジャーナリズム」の立場に好都合な考え方でもある。本来ジャーナリストの仕事は、特定の新聞社や放送局の記者である前に、あるいは少なくともそれと同時に、普遍的な倫理や目的を共有する専門職と考えていいのではないだろうか。一企業の利益のために黙々と働くだけの記者なら、さして特段の「志」など必要としないかもしれない。
マスコミ各社の人材採用が、一般企業と同じように新卒予定者を対象に、一斉に入社試験をするという形で行われてきたのは、それぞれの社風になじんだ記者を育てようとする「企業内ジャーナリズム」的な発想と無関係ではないだろう。しかし今や終身雇用制が崩れ始め、労働市場の流動化が急速に進んでいる。ましてマスコミ各社が「企業内ジャーナリスト」ではなく、「志」のある人材を求めようとするのなら、人材採用の方法をこの辺で根本的に見直す必要があるのではなかろうか。
人材掘り起こす試み
一つ検討に値すると思われるのは、インターン制の導入である。夏休みなどの長い休暇を利用して、新聞社や放送局がジャーナリズムに関心を持つ学生たちを無給のインターンとして積極的に受け入れ、現場を体験させる。学生たちはこの仕事に対する理解を深めることができる。企業側は優秀な人材を掘り起こす機会として活用できる。受け入れ方は、現場の実情に合わせて負担にならないよう調整すればいい。せめて採用予定の一部をこうした方法で選べるなら、企業側も時間をかけて納得のいく人選ができるように思われる。
聞くところによると、いくつかの地方紙ではすでに地元の大学からの要請に応えて、これに近い採用方法を部分的に試みているという。それがより優れた人材を見つけるうえでどれほど有効かは、今しばらく実験の行方を見守らねばならないようだが、少なくともこれまでの入社試験のありようを考え直すきっかけにはなりそうに思われる。
「志」ある若者を採用したいなら、マスコミの側にも、それなりの真剣な取り組みが求められているといっていい。