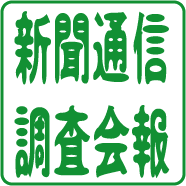 |
「女子アナ」とニュース
1999年4月号
|
|
|
|
| このところ、気のせいか、週刊誌の広告にやたら「女子アナ」の話題が目につく。彼女たちの「好感度」から私生活まで、どこまで信じていいものかわからないような話が、読者や視聴者の関心をそそろうと、手を変え品を変えて書き立てられている。なかには個人の名誉を著しく傷つけかねない類の話もある。 しかし書かれる「女子アナ」や放送局の側から、こうした週刊誌の報道に抗議や訴訟の動きがあったという話はあまり聞かない。彼女たちもそれを「有名税」と考えているのかもしれない。とすれば「女子アナ」自身、記者や編集者と肩を並べて働くジャーナリストとしてよりも「有名人」としての自覚が強いということだろうか。 |
▽「偽りの有名性」
実際問題として、テレビに登場するキャスターやアナウンサーと呼ばれる人たちは、否応なく、有名になる。その上「女子アナ」はえてして、ジャーナリストとしての能力よりは、本人の容姿や話し方、声の質、その人柄などなど、視聴者に与える印象の良し悪しで評価されることが多い。そこに、えげつない週刊誌につけいられる隙があるとも言える。
石田佐恵子(大阪市立大学)は『論座』三月号のなかで、最近の「女子アナ」ブームを「作られたブーム」といい、彼女たちの「有名性」は「偽りの<有名性>を連想させる」と指摘している。石田によれば「テレビに出ること=<有名になること>=成功者であること、という短絡的な図式が彼女たちを<有名人>の場所にかさ上げ」しており、この図式が「一方ではもてはやされ、他方ではバッシングされるという奇妙な場所に彼女たちを連れていくのではないだろうか」という。
ところで、この小文で問題にしたいと考えたのは、テレビの女性アナがタレント化していることではない。彼女たちを興味本位で扱う週刊誌の姿勢でもない。問題にしたいのは、そうした現実を踏まえて放送局の側が彼女たちにどのような役割をさせようとしているのか、である。
▽ニュースと紅白と
昨年末のNHK紅白歌合戦では、夜のニュース番組を担当している若い女性アナが司会者の一人に起用された。司会の出来栄えは問わない。とにかく彼女はお祭り騒ぎの場の雰囲気を盛り上げるために、歌手たちに混じってはしゃいだりはやしたり、懸命だった。しかしその彼女がその後また、以前と同じようにニュースの原稿を読んでいる。そのことに、少なくとも筆者は、少々引っかかるのである。
言うまでもないことだが、ニュースを伝える仕事と歌番組の司会の仕事は、まったく性格の異なるものである。前者に必要なもっとも基本的な要件は、だれにもへつらわず、正直であることである。この要件を貫こうとすれば、歌番組の司会はとうていできない。逆に、芸能番組ではしゃいでいるアナウンサーがニュースを読むと、ニュースそのものの信頼性が乏しいような気がするのは、見る側の偏見だろうか。
一人のアナウンサーがニュース番組と芸能番組の両方に顔を出すのは、なにも今回が初めてではない。女性アナだけでなく、男性アナでも似たようなケースはしばしば見受けられる。もちろんこれは、アナウンサー個人の問題ではない。こうした人の使い方をする組織の考え方の問題である。
もともと娯楽性の高いメディアであるテレビは、娯楽番組とニュース番組の間に明確な一線を画しておかねばならない。本来なら、ニュース制作部門と娯楽番組制作部門は組織的にも人事面でもはっきり分けておくべきだろう。アメリカの三大ネットワークでは、伝統的にニュース部門を他の部門から独立させて、両者の間に一定のけじめをつけている。
▽あいまいな境界線
しかし日本では、この二つの部門の境界がかねてからあいまいにされてきた。とくに民放は、ワイド・ショーやバラエティ・ショーで、アナウンサーにタレントまがいのことをさせたり、タレントに記者まがいのことをさせたりして、ニュースときわもの情報の垣根を取り壊してしまった。挙げ句の果てには、キャスターやアナウンサーのなかに、胃腸薬や調味料のコマーシャルに顔を出す人たちまでが現れている。
NHKの場合、民放ほど露骨ではないが、それでもニュースと娯楽の間の垣根を厳格に守ろうとする意識が次第に希薄になりつつあるのではないか、と心配になる。人気女性アナを紅白の司会者に起用するのはともかくとして、その後も相変わらずニュースを担当させるというのは、筆者の目から見ると無神経すぎる。
もっとも、こうした見方には異論もあるだろう。一つには、もともとアナウンサーは他人の書いた原稿を読むだけの機械みたいなもの、ニュース原稿を読もうと司会の台本を読もうと大した違いはない、という見方。もう一つは、最近のニュース番組そのものが娯楽化していて、キャスターやアナウンサーにジャーナリストとしての基本的要件など期待していない、という意見。いずれも確かに真実の一面を突いてはいる。
しかし、とは言いながら、キャスターやアナウンサーの顔が持つ意味合いや影響力は現実の問題として決して小さくない。仮にイメージだけにせよ、彼ら、彼女らの顔がそれぞれの番組の信頼度や好感度を左右する。ニュース番組の場合、とりわけ信頼度を重視するとすれば、芸能人たちとはしゃぎ回ったアナウンサーの読むニュースに視聴者がどのような反応を見せるか、NHKの責任者は少し考えてみてはどうだろう。
▽報道現場の意志
日本よりもう少しけじめがあるというアメリカでも、ニュースと娯楽の間の垣根が低くなってきていることは、これまでにもしばしば指摘されている。一九八〇年代の半ば以降、軟らかな話題ものを扱ったドキュメンタリー風の「テレビ・マガジン」と称される番組が各局に登場、ニュースと娯楽の中間を行く番組が次々に作られた。さらに日本のワイド・ショーに近い「トーク・ショー」もニュースの娯楽化に拍車をかけた。
かつてNBC放送がタレント(アメリカではテレビ・パースナリティと呼ばれる)のバーバラ・ウォルターズをニュース・キャスターに起用したとき、大きな論議を呼んだ。要するに、ジャーナリストとしての経験のないウォルターズをキャスターにすることへの批判が強かったのである。結局、彼女のキャスターとしての寿命は長くはなかった。
アメリカのテレビで活躍する女性のニュース・キャスターは少なくないが、そのほとんどは現場での取材経験を相当積んだ上で、才能を(そしておそらくは容姿や人柄も)評価されて起用される人たちである。しかしせっかくキャスターに起用されながら、取材経験の乏しさから仕事の圧力に耐えかねて薬物におぼれ、若くして事故死したジェシカ・サビッチのようなケースもある(『ニュース・キャスター』グウェンダ・ブレア著 岸野郁枝訳)。
日本のように、現場での経験がなくても、容姿や明るい性格、視聴者の好感度などだけでキャスターの仕事を与えられるケースはまずない。そこには曲がりなりにもニュースと娯楽の境界線をきちんと守ろうとする、アメリカの報道現場の意志が感じ取れるような気がする。日本のテレビの報道現場にはそうした意志があるのかどうか、ニュースと紅白を掛け持ちする「女子アナ」の姿を見ていると、そんな疑問がわいてくる。