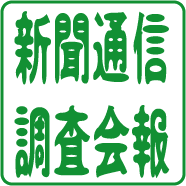 |
メディアの「産学協同」 2001年4月号 |
|
|
|
| 早稲田大学、慶応大学などいくつかの大学で、メディア企業によるいわゆる「寄付講座」が開設されて一年が経つ。早稲田の場合は複数の主要メディア企業が共同で資金と講師を提供して、当面四年間継続する計画で進められている。慶応、青山学院、北海道大学などの講座は『読売新聞』が単独で大学側と提携し、資金提供と講師の派遣を引き受けている。 講座の評価については、『朝日総研レポート』(第一四八号)松浦康彦氏(総合研究センター主任研究員)の論稿「ジャーナリスト教育の改革とその将来」に詳しい。講座に対する学生たちの関心は高いようだが、講義の内容については不満もなくはないという。 |
企業と大学の接点
試みが始まったばかりの今の段階で、成功か失敗かを問うのは適切ではあるまい。むしろ、これまで接点の乏しかったメディア企業と大学の間で、何がしかの関係が作られ始めたことを評価したほうがいい。こうした両者の接点が将来、よりよい関係に発展するよう、双方の側が心配りをすることが大事なことだろう。
その将来の問題について、松浦氏の論稿はいくつか重要な示唆を与えてくれている。一つは、メディア企業が人材採用のあり方を見直し、新卒より経験者の中途採用に重点を移し始めている、ということ。第二は、これまでの企業内の現場教育主義だけでは不十分であることが認識され始めていること、第三に、こうした問題を解消する一つの方法として、大学生のインターン制度導入の検討を促がしていること、である。
中途採用に比重を移す背景には、新卒採用の記者のなかに、入社から数年も経たないうちに辞めるものが少なくない、といった事情があるらしい。それは要するに、採用時のミスマッチを企業側が見抜けなかったということでもある。メディアを志望する学生にかつてのような「志」を持ったものが少なくなった、との指摘もある。
新人記者を地方支局に出して現場で教育する、という方式が必ずしも機能していないということもあるようだ。地方支局の仕事が昔より忙しくなり、デスクや先輩記者が新人教育にまで手が回らなくなったとも言われる。三月九日付『朝日新聞』は、元広島支局員による記事盗作事件を社内で検証した報告の詳細を掲載し、現在の記者教育態勢に不備があることを認めている。
現場中心の教育に限界
これら一連の問題を踏まえて松浦氏はジャーナリズム教育の再構築を呼びかけている。それもこれまでのような企業側の現場中心の教育ではなく、大学における教育の可能性も含めたジャーナリストのための教育・訓練計画を考える必要を訴えているように見える。
早稲田や慶応で始まった「寄付講座」がそうした文脈のなかで生まれたものかどうかは必ずしも判然としない。早稲田の場合は大学側から企業側への働きかけがあったようだし、慶応などでの『読売新聞』単独の試みは新聞のイメージを高めようとの思惑があったともいわれている。しかし本音がどうであれ、ジャーナリズム教育に関して企業と大学の間に具体的な接点が生まれ、人材やカリキュラムなどを通して双方の間の関係が多少とも深まっていくとすれば、歓迎すべきだろう。
問題は今後、この関係をどう発展させていくかにある。現場から人を大学に派遣しての講義も、単なる現場記者の苦労話や手柄話の寄せ集めでは学生にも飽きられる。「寄付講座」も特定の企業がOBを大学に送り込むためのひも付き講座になってしまっては、あまり意味がない。あくまで、将来ジャーナリズムで役に立つ人材を育て、ひいては日本のジャーナリズムの質向上につながるような「産学協同」を目指すべきだろう。
この「産学協同」の形がどのようなものになるか、メディア企業の側が何を求めているのか、いまのところまだはっきりしない。が、いま現場が抱えるさまざまな問題を見ると、これまで主として企業内で行われてきた記者の教育・訓練に限界が見え始めていることは指摘できる。その限界を克服する一つの手立てとして、大学ないし大学院をもっと活用してはどうか、というのが「産学協同」の基本的な考え方である。
専門記者の養成も
記者教育・訓練といっても、新人記者の教育と入社後数年ないし十数年を経た中堅記者の教育・訓練とは分けて考えたほうがいい。新人教育については、これまでもっぱら入社後それぞれの社内で(新聞についていえば、地方支局に配属されたあとで)十分行えると考えられてきた。「産学協同」は、この新人教育の一部を大学に委ねる可能性を考えようというものである。具体策の一つとして、企業と大学が協力して大学生のメディア企業におけるインターン制度を推進することがある。それによって記者の仕事を目指す学生たちに現場の仕事への認識を高めさせ、入社後にミスマッチが表面化することを防ぐことができる。ジャーナリズムの職業倫理などについて学生時代に基礎を身につけさせておくことも有意義だろう。
中堅記者の再教育・訓練、特に専門記者の養成につながるプログラムは、企業内の教育計画としては事実上、ほとんど存在しない。一部の企業で海外での語学研修など制度化されたものもあるが、さまざまな分野で記者が専門性を高める努力はそれぞれの記者個人に任されるにとどまっている。今後、企業が記者のそうした努力を積極的に支援しようとすれば、記者を一定期間、大学や大学院に送り込んで勉強する機会を与えるといった方策が必要になってくると思われる。
さきごろある地方紙を訪ねて、入社五年から十年を経た記者の意見を聴く機会があった。かれらのほとんどは、機会があれば半年なり一年なり、大学や大学院で自分の関心領域の勉強をしてみたい、という。企業としてもそうした記者の希望を無視することはできないだろう。
企業の取り組みがかぎ
しかしこうした「産学協同」を実現するには大きな問題も残っている。一つは大学の側の受け入れ体制が整っているかどうか、である。正直なところ、十分な準備が整っているとはいえそうにない。中堅・専門記者の養成を支援するには、さまざまな分野で短期集中的に記者の研修を受け入れられるような制度が大学なり大学院なりに備わっていなければならない。学部レベルでのジャーナリズム教育にしても、現在の大学で企業側からの要請に十分応えられるカリキュラムやスタッフをそろえた大学はほとんどない。
しかし、企業の側から大学でのジャーナリズム教育に対して明確な要請があれば、大学がそのための受け皿をつくることは不可能ではない。企業側からの資金や人材面での協力が必要になるかもしれない。が、双方の間に継続的な提携関係を築くことができれば、大学側の体制整備はそれほど難しくはない。
より大きな問題は、企業の側が自社のジャーナリストの教育・訓練にどれほど前向きに取り組むか、である。より充実した記者教育や専門記者の養成のためには、それだけの時間もコストもかけねばなるまい。これまでのやり方を根本的に見直す必要も出てくるだろう。企業側にそれをやり通す意思がなければ、大学側の受け皿づくりの努力も意味をなさなくなる。
早稲田をはじめ、いくつかの大学で始まった「寄付講座」の試みが、企業内での記者教育の問題点を補完する機能を直ちに担えるとは思えない。しかしこうした試みを通じてメディア企業と大学の間にこれまで横たわってきた、ジャーナリズム教育をめぐる大きな溝が多少とも埋められるなら、将来の「産学協同」のために有意義な一歩が進められたといえるかもしれない。