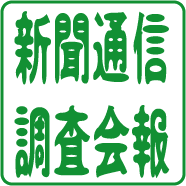 |
「開かれた新聞」に向けて 2001年3月号 |
|
|
|
| 『朝日新聞』がこの一月から、社外の識者三人による「報道と人権委員会」を発足させた。『東京新聞』もやはり一月、「新聞報道のあり方委員会」の創設を発表した。昨年十月に「『開かれた新聞』委員会」を新設した『毎日新聞』を含めて、この種の委員会を設けた有力紙はこれで三紙になる。地方紙のなかにも『下野新聞』や『新潟日報』など、同様の組織を設置するところが出てきている。 これらの「委員会」の機能は新聞によって異なるようだが、いずれにも共通しているのは、委員を委嘱された人たちがすべて社外の識者である点。これが、外部からの批判や注文にも耳を傾けようという、「開かれた新聞」に向けての姿勢の変化を示唆しているのなら歓迎すべきだろう。とかく傲慢と批判されることの多い新聞だけに、これからの対応を注目したい。 |
背景に批判の高まり
『毎日』の「委員会」は、報道による人権侵害などに関して当事者から寄せられた苦情や意見に「第三者」としての委員の意見を反映させるほか、新聞の報道について随時意見を表明できることになっている。『朝日』の「委員会」は、報道による人権侵害などの被害に関して、「委員会」独自で調査、審理し、意見を述べることを目的としており、『毎日』よりやや役割が限られている。『東京』は報道被害の問題なども含め「よりよき新聞づくりに関し自由に意見を交換してもらい、具体的事例についても参考意見を求める」と、前の二社より広範な機能を持たせている。
三社とも、「委員会」の意見や議論の内容は新聞紙面で公表する方針という。これまで新聞は、読者からの苦情やこれに対する新聞側の対応などを社外に明らかにすることがほとんどなかった。今後、そうしたやり取りや「委員会」の率直な意見が紙面でどんどん伝えられるようになれば、読者と新聞の間の風通しが少しはよくなるだろう。
いまの時期に各社が相次いでこうした「委員会」を設けるに至ったのは、明らかにメディアに対する市民の批判が強まり、それに乗じたような形で権力の側にメディアを規制しようとする動きが高まってきたからである。動きの一つは、法務省の人権擁護推進審議会が昨年、公表した「中間とりまとめ」のなかで、メディアによる報道被害も「人権救済」の対象とする考え方を示したこと。これに呼応するかのように日本弁護士連合会が「人権機関」の設置を提案、メディアの報道活動も調査の対象に加えることを主張したこと、などもそれにあたる。
法務省の審議会や日弁連の考え方には、メディアによる人権侵害に対しても強制調査で対処することを可能にしようという方針が含まれている。これは明らかに、権力がメディアによる報道活動に干渉する道を開き、報道の自由を脅かす危険をはらんでいる(本誌二〇〇〇年十月号本欄)。メディア側がこうした動きに危惧を抱き、その方針に反対を表明しているのは当然と言える。
外の世界とのつながり
ただ一方で、メディアの報道のなかに、報道される側の名誉を傷つけ人権を侵すような事例が後を絶たない現実もある。そうした事例の多くはテレビのワイドショーや週刊誌によるものだが、新聞もわれ関せずではいられない。市民の間にメディア批判が強まっているのはそのためだし、法務省審議会や日弁連の動きは、そうした批判の高まりを背景にしたものと言える。
日本民間放送連盟とNHKは九七年に、放送による人権侵害などを審理する「放送と人権等権利に関する委員会(BRC)を、自主的な第三者機関として発足させた。九〇年代半ば、放送に対する市民の批判が強まったあと、いわば泥縄式につくられた。しかし新聞界はいまのところ、業界全体としてこの種の機構や組織をつくる動きは見せていない。おそらく、新聞界としてはまだその必要を認めていないからだろう。
ただ『毎日』などいくつかの新聞が「委員会」を創設したのは、少なくとも個々の社のレベルでは、メディアを取り巻く環境の厳しさへの認識が深まってきた結果と思われる。メディアが読者や視聴者の持つ不満に鈍感であることや、メディアをめぐるさまざまな状況について危機感が乏しいことは、かねてから繰り返し指摘されてきた。そうした鈍感さや危機感の欠如が十分に改善されたとは思えない。しかし『毎日』などの動きには、いわば外部から新聞に向けられる厳しい眼差しを、ようやく意識し始めた兆しが読み取れるような気がする。
独立性と透明性
しかし問題は、この先、新設された「委員会」がそれぞれの新聞で実際にどのような機能を果たすか、にある。機関を設けることと、その機関が目的どおりの機能を果たすこととは別問題である。それぞれの新聞が「委員会」を十分に活用する意思を持たなければ、折角の「委員会」も外からの批判をかわすための隠れみのに使われてしまう危険がある。
いずれの社の「委員会」についてもいえることだが、これが十分機能するためにはいくつかの条件がある。一つは「委員会」の独立性を確保することである。『毎日』の「委員会」は主筆の直属、『朝日』の「委員会」は社長直属とされ、いずれも編集局から独立しているという。これまでの記事審査委員会などのように、社内の機構の一部にとどまっては、率直な批判や議論が交わせない。新「委員会」のもとでは、社内事情などへの配慮は抜きに、読者、市民の立場に立って自由に意見を表明できる環境が保証されなければならない。
もう一つの条件は透明性の確保である。各社とも「委員会」からの意見や提言は紙上で公表することを約束している。ただ限られた紙面で、議論の詳細がすべて公表される保証はない。仮に、新聞にとって不都合な意見や指摘が伝えられないようなことがあれば、「委員会」や新聞に対する期待は裏切られることになる。新聞としては極力、新聞にとって不利、不都合な情報も含めて読者に開示する誠実さを持たねばならない。
信頼回復のために
『毎日』や『朝日』『東京』などの試みは、新聞に対する市民の信頼を回復するための切り札になるわけではない。むしろこれ以上、信頼が失われることを防ぐための足がかり、と考えるべきだろう。この試みが成功したとしても、これに同調しない新聞や他のメディアが数多く残っている限り、メディア全体の信頼が回復できるとは思えない。
必要なことは、まずこの種の試みをより多くの新聞が取り入れることだろう。できればさらに「委員会」を各社ごとのものから新聞全体、さらには雑誌も含めたメディアの大半に受け入れられる第三者機関に発展させることである。
それが北欧諸国や英国にある「報道評議会」や「苦情処理委員会」に近い性格を持つか、それとも日本独自の新しい機関になるか、わからない。あるいは米国での例のように、外部からの干渉を嫌う有力メディアの反発にあって、最終的には失敗に終わるかもしれない。しかしこれまでその種の機関がなかった日本の新聞界に、それをつくる土壌がようやく生まれようとしているかに見える。それを試みるだけの価値はある。
報道の自由を守るためには、報道する側もその責任を果たさねばならない。それには、メディアが自分たちの行動を自分たちで律する仕組みが欠かせない。政府による規制や圧力を受けて責任を全うするのではなく、自分たちの意思で全うするような仕組みを備える必要がある。
『毎日』などの新しい「委員会」の試みは、そうした仕組みづくりへの第一歩と考えられる。その歩みを着実に前進させないと、権力を持つものが力ずくでメディアに規制や圧力をかけてくる事態が、すぐそこまで迫っている。