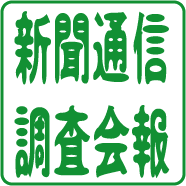 |
内側からのメディア批判を 2001年1月号 |
|
|
|
| 数年前から月一、二回の割合である雑誌に書いてきたメディア批評欄が先ごろ、廃止された。雑誌の「衣替えのため」というのが、編集部から受けた理由の説明だった。なくなったことを惜しむ声があったとも聞かないから、編集部の判断は正しかったのかもしれない。 雑誌が小さいせいか、批評が迫力を欠いていたせいか、読者から反響らしい反響が届いたことがほとんどない。一度、ある新聞社の編集局長さんから編集者を通して「同感だ。コピーを編集局に回覧させている」とのお手紙をいただいたことはあるが、これは例外に属する。たいていはのれんに腕押し、闇夜に鉄砲だった。 |
無視される?批判
メディア批評を書く側からすると、一般の読者もさることながら、ジャーナリズムの現場で働く人たちに読んでもらいたい、できればなんらかの反応を得られれば、と期待する。しかし現実は、ほぼ完全に無視されている(ように思われる)。
メディア批評に限らず、批評あるいは批判と呼ばれる作業は、あまり建設的な作業と評価されていないフシがある。人さまの仕事にけちをつけることが役回りみたいな部分もあるから、仕方がないのかもしれない。が、メディア批評がとかく無視されがちなのは、ほかにもわけがありそうに思われる。メディアの内側で働く人たちが、外部からの批評に耳を傾ける姿勢を、はなから持っていないためではなかろうか。
理由はいくつか考えられる。一つは、日本の新聞や雑誌でメディア批評をしている人たちの多くが、メディアの外側の人たちであることだ。メディアの内側の人間からすると、かれらはジャーナリズムの現場を知らない。そうした人たちに、自分たちの仕事を理解してもらえるはずがない、という思いがあるのではないか。その背景には、この仕事が、高い公共性を求められる特殊な仕事だとの思い込みがあるように思われる。
もう一つ、ジャーナリズムの仕事が外部からの声に左右されるようでは、報道の自由が守れないという意識もあるだろう。そうした思いや意識が、外部からの批評や批判を受け付けたがらない、という形で表れているのではないか。確かに、外部からの不当な圧力でその仕事の結果が影響されるようでは困る。しかし正当な批評や批判まで拒むことになれば、それはただの傲慢と思い上がりに過ぎない。
内側からの声
ジャーナリズムが批判を嫌がる傾向は、なにも日本だけのことではない。米国のように比較的開かれた体質の社会でさえ、メディアはやはり批判に耳を傾けたがらないという。『ニューズウィーク』でメディア・政治問題のコラムを担当しているジョナサン・オルターのようなコラムニストでさえ、メディア批判の持つ影響力はそれほど大きくはない、と筆者とのインタビューで控え目な評価をしていた。「(自分の仕事に)けちをつけられたくないという気持ちは同じですよ」。
ただひと口にメディア批評といっても、日本と米国のそれには大きな違いがある。その一つは、批評の仕事を担っている人たちの多くが、メディアの内側の人間であることだ。かれらは日常的に新聞や雑誌で意見を表明する場を持っており、その影響力も日本に比べると、はるかに大きい。
『ワシントン・ポスト』のハワード・カーツ、『ロサンゼルス・タイムズ』のデービッド・ショウ、『ニューヨーク・タイムズ』のフェリシティ・バリンジャー、『ボストン・グローブ』のマーク・ジャーコウィッツといった人たち、『タイム』『ニューズウィーク』などの週刊誌もオルターのようなコラムニストや記者を擁している。
かれらは、日常的なメディア関連のニュースを伝えるだけではない。定期的なコラムでメディアやジャーナリズムのさまざまな問題を批評する。そしてたとえ自社に非がある問題でも、批判すべき点は徹底的に批判する。
一九九九年秋、『ロサンゼルス・タイムズ』の首脳が関わった不祥事に関して、ショウ記者は、社長や編集局長の責任を追及する調査結果を自社の紙面で詳細に報告した(本誌二〇〇〇年一月号本欄)。『ボストン・グローブ』の例のように、盗作の疑いをかけられて処分されたコラムニストと、処分した社側幹部の双方の言い分を、同じ新聞のメディア担当記者が取材して報じたりもする。
うやむやの「指南書」
こうした風土のなかなら、昨年夏、日本の内閣記者会で起きた、森首相に対するいわゆる「指南書」問題がうやむやにされてしまうようなことは、まずあり得ない。あれが米国での出来事なら、たちまちのうちに仲間の記者の手で真相が究明され、責任の所在が明らかにされたに違いない。
日本のジャーナリズムにそれができなかったのは、「指南書」の存在を問題にし、責任を追及しようという声がメディアの内側で大きな力にならなかったからだ。この問題を最初に伝えた『西日本新聞』の記者のように、これをジャーナリストの倫理の根幹に触れる問題として取り上げたものもいるにはいた。が、かれらの声は多数派の力にあっさり押しつぶされてしまった。それはおそらく、現場の記者の多くが「企業ジャーナリスト」のわくを超えて行動できなかったからだろう。あるいは政治記者の多くが、最も基本的な倫理意識さえも欠いていたからではないか。
九〇年代に主だった新聞各紙は「メディア欄」を設け、メディア関連のニュースを担当する記者を置いた。それによって一見、以前にはタブーだった同業者に関するニュースも報じられるようになった。が、「指南書」問題のように、本当にジャーナリズムの根幹に関わるような問題は取り上げられないし、他社の問題を正面から批判するような報道にもめったにお目にかかれない。
いま日本のメディアにとって必要なのは、メディアの事情に通じた内部の人間による批評、批判だ。むろん外部の有識者らによる批評、批判は必要だし、メディアにはそれに耳を傾ける謙虚さもほしい。しかしメディアの内側に、自分たちの仕事をもっと自由に批評し、批判する空気が生まれてこないと、本当に有効なジャーナリズム改革の道筋は見えてこない。
メディアの自浄作用
残念ながら、日本の現状では、内部からのメディア批判が活発に展開される兆しはあまりない。それを妨げているのは企業のくびきだ。多くの記者にとっては依然、企業の中での自分の位置を確保することが、ジャーナリズムの普遍的な価値を守ることより重視されているように見える。現場の記者たちが自分の所属する企業のしがらみにとらわれている間は、メディアを活性化するようなメディア批判は期待できそうにない。
役所や大企業で不祥事が起きると、メディアはそれぞれの説明責任や情報の透明性を要求する。不祥事が繰り返されると、自浄作用の欠如を嘆く。であれば、メディアに問題が生じたとき、当然のことながらメディアも事実を公表し、責任の所在を明らかにしなければならない。それも、外から問題を指摘されてそうするのではなく、自分たちの手でそうすべきだろう。そのためにこそ、自分たちの仕事について内側から絶えず批判の声をあげる必要がある。そうすることがメディアの自浄作用を促がし、ジャーナリズムの質を高めることにつながる。
外部の有識者らによる紙面批評や番組批評を申し訳程度に設けるのではなく、ニュースの現場を知り尽くしたジャーナリストに自由にメディア批判をさせる仕組みを作るべき時期にきている。傲慢や思い上がりを捨てて、自分たちの手で自分たちの仕事を厳しく問い直す謙虚さが求められている。