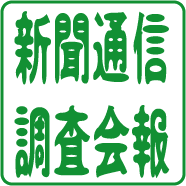 |
新聞の問題意識 2000年12月号 |
|
|
|
| 十月に横浜市で開かれた今年の「新聞大会」は、「表現の自由を脅かすあらゆる動きに反対する」大会決議を採択、同時に再販制度および戸別配達制度の堅持をうたった「特別宣言」を発表した。宣言は戸別配達制度が日本の「文化水準を高め、民主主義社会の維持・発展に寄与してきた」とし、戸別配達を維持するために「再販制度が不可欠である」と述べている。 公正取引委員会が再販制度の扱いについて来年三月に一応の結論を出すことになっているとき、新聞界が「特別宣言」を出したこともうなずける。個人情報保護法制定や独立の人権機関設置をめぐる動きに、表現の自由の将来を懸念するのももっともだ。しかし宣言や決議は別にして、新聞界が自分たちの直面している問題をどう認識し、それにどう取り組もうとしているのかとなると、必ずしも定かには見えてこない。 |
特集紙面の分析
新聞大会が開かれる毎年この時期、新聞は「新聞週間」を記念して特集紙面を組んでいる。各紙が知恵を絞って制作する(と思われる)紙面には、それぞれの新聞の問題意識が表れるのではないか。事前にそう考えて、ゼミの学生たちに、今年の特集紙面を分析する課題を出してみた。新聞界の現状を見ると、深刻な危機意識が読み取れるかもしれない、という予感も正直なところあった。
しかし結論を先に言ってしまえば、そんな予感は当たらなかった。危機意識と呼べそうなものは感じられないだけでなく、むしろ新聞の将来を楽観視するような空気さえ、一部の特集からは読み取れた。これを意外と思うか、現実はそんなものと受け取るか、人によって評価は異なるだろうが、いずれにしても気にかかる。
学生たちが別々に調べた結果を持ち寄って話し合ったところ、おおむね次のような点で意見が一致した。第一。『朝日』と『毎日』は、それぞれ新聞報道のありように問題があることを認め、それを是正する意思を示している。第二。『読売』は、新聞に対する読者の信頼度が依然として高いことに自信をのぞかせ、新聞の将来を楽観視しているようだ。第三。『産経』は他社と自社の社説の違いを比較して、自社の立場の正しさを主張する態度がにじんでいる。
日本の新聞が置かれた現状について、各社それぞれに認識が異なったとしてもおかしくはない。しかし読者の新聞離れが進み、電子メディアが日々、勢いを増すなかで、新聞の将来に対する懸念は業界共通の深刻な問題でもあるはず。しかし新聞週間の特集記事を見る限り、そんな気配はあまり感じ取れなかった。
社外のご意見番
学生たちの分析によると、新聞が抱える問題を部分的ながら正面から取り上げていたのは『朝日』と『毎日』だった。『朝日』は先に支局の若い記者が引き起こした「記事盗用事件」に関連して、社内で自己検証と再発防止の努力が続けられていることを説明している。また新聞と読者をつなぐ「窓」としての広報室の機能を紹介している。
『朝日』はさらに、この春から続けられているインターネット上での政治討論の場「e―デモクラシー」や、市民の視点でニュースを伝える試み「くらし編集部」の仕事を振り返って、これからの可能性を探っている。
『毎日』は社外の識者による「開かれた新聞」委員会の創設を発表し、新しい委員による新聞への注文、批判などを中心に特集紙面を組んでいる。委員会は、従来型の社内の記事審査機構とは異なり、第三者の立場で報道のありようを監視するほか、読者からの苦情や批判に基づいて編集現場に意見を述べるなど、社外オンブズマン的な機能も果たすものになるという。もしこれが期待通りの役割を果たせるなら、新聞が自らの失敗や不注意を改め、報道による被害にも適切に対応できる、新しい仕組みに先鞭をつけることになるかもしれない。
両紙とも、それぞれが抱える問題や弱点を率直に認め、それを克服するための努力を具体的に読者に示しているという点で、学生たちは前向きに評価していた。もっとも「反省と努力」を前面に押し出しているところが「宣伝っぽい」という、皮肉な見方もあるにはあったが。
『読売』の特集は、よく言えば自信に溢れ、悪く言えば独り善がり、と受け取られそうなものだった。同紙は世論調査を基に、報道メディアとしての新聞に対する信頼度がテレビに比べて高いこと、インターネットが普及しても、紙の新聞への需要がなくなることはないことなどを指摘して、二十一世紀も新聞が「中核メディア」でありつづけるとの自信を示している。
そうした見方は、新聞で働くものならだれしも信じたいところだろうが、そうと信じきれないところに現在の業界の不安があるといっていい。『読売』の特集は思いっきりよく、そんな不安を吹き飛ばそうとしているように見えるが、果たして吹き飛ばせたかどうか。学生たちに言わせると、わが身に好都合な建前と希望的観測の色合いが濃く、なんとなく胡散(うさん)臭い、という。
『産経』は森首相の「神の国発言」など、いくつかの問題をめぐる自社と他社の社説の相違点を際立たせる特集を組んでいた。それによって『産経』の立場の正当性を主張しているように見受けられる。『産経』はまた、再販制度の維持を一方的に主張する連載記事も掲げていた。いずれも手前味噌的な印象があるのはぬぐえない。
新聞と読者のずれ
結局、学生たちの調査からは、現在の主要紙が自分たち自身についてどのような問題意識をもっているのか、定かなところを探り出すことはできなかった。おぼろげに分かったことといえば、それほどの危機感を抱いているわけではない、ということだった。意外な結果というわけではないが、これでいいのかという、割り切れぬ思いは残る。
釈然としない理由は、新聞が自分を見る目と、読者・市民が新聞を見る目との間に、相当のずれがあると思われる点にある。再販制度維持を主張する際、新聞界は決まって販売競争上の節度を守り、ルールを尊重することを自ら戒める。しかし建前とは裏腹に、限度を超える景品や実質上の値引きをえさにした拡販が行われていることは、多くの市民が実際の体験として知っている。松本サリン事件のような著しい人権侵害を犯しても、新聞は事件から一年近くたって紙面で謝罪を表明しただけで、だれかが責任をとった形跡もなければ、再発を防ぐ具体的な手立てを講じた様子もない。
今年の新聞大会では、新しい新聞倫理綱領の制定が新聞の倫理向上を担った大きな前進と位置付けられ、研究座談会のテーマとしても取り上げられていた。しかしそこに盛り込まれた高邁な理念と、日ごろの新聞の行動との間に深い溝があることも、多くの読者は見抜いている。
綱領が掲げる原則の一つに「新聞の独立」がある。特定の勢力に利用されたり、つけ込まれたりしてはならないという。なのに、例の「指南メモ」事件では、内閣記者会は結局、責任の所在をうやむやにして問題を葬り去った。メディア各社もゲタを内閣記者会に預けて、知らぬ顔の半兵衛を決め込んだ。新綱領の「独立」の文言が空々しい。
毎年、新聞週間のたびごとに読者の新聞に対する関心を呼び起こし、認識を改めさせることは結構だ。新聞社幹部が新聞大会に集まって議論するのもいい。しかしその中身が建前だけのきれいごとで終わっていては、業界内輪の、意味のない儀式になりかねない。読者が新聞を見る目は、新聞の内側にいる人たちが考えるよりはるかに厳しい。新聞の二十一世紀は、まず新聞が自分たちの足元をもう一度、謙虚に見つめ直すところから始めるべきだろう。