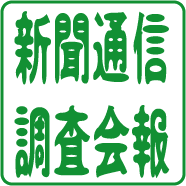 |
メディアの「公正」 2000年9月号 |
|
|
|
| 他社に抜かれた特ダネをなるべく小さく評価したがるのは同業者の常だが、度が過ぎると、著しく公正を欠くことになる。現場の人たちもそれを自覚しているはずなのに、一向に改まる気配がないのはどうしてだろう。 |
他社の特ダネ
森内閣の金融再生委員長に任命されたばかりの久世公尭参院議員が七月末、二億三千万円もの利益提供を銀行から受けていたことが明らかになって辞任に追い込まれた。利益提供を受けていたことを最初に伝えたのは二十八日の『朝日新聞』朝刊。他の各紙は同日夕刊でこれを追いかけた。『毎日』『産経』は一面に載せたが、『読売』は社会面四段と小さな扱いだった。『朝日』の特ダネでさえなければ一面トップになるはずの事件だが、『読売』の扱いが小さくなったのは、メンツのためか、それとも事件そのものの重要性を誤って判断したためか。
しかし記事の扱いよりもっと問題なのは、このニュースの伝え方である。『朝日』に先を越された他の新聞すべてに共通していたのは、この事件が「(二十八日)明らかになった」という形で報じていたことである。どの記事を読んでも、どういう経緯で「明らかになった」のか、だれが明らかにしたのか、何も書かれていない。『朝日』の記事をすでに読んでいた読者なら、抜かれた特ダネの追いかけだな、という推測もできる。しかしそうでない読者には「明らかになった」という記事が初めてのものであり、当然、どのようにして明らかになったのか経緯を説明する必要がある。
後追いした各紙の記事の内容がすべて独自の取材に基づくものかどうかはともかく、少なくともこの問題を報道するきっかけを作ったのが『朝日』であったことは確かである。だとすれば、仮に後追いの記事がすべて独自の情報に基づくものであっても、他社が先行報道したニュースであることに一言、触れるのが公正なやり方だろう。まして多少とも『朝日』の報道に依拠する部分があればなおさら、そのことに言及すべきである。
あいまいな情報源の扱い
「公正(フェアネス)」は、ニュース報道に求められる最も重要な価値の一つである。客観報道を支える柱の一つといわれることもあるし、むしろ客観主義にとって代わる価値と考えられることもある。公正を欠いたニュースはたちどころに、読者や視聴者の信頼を失ってしまう。
この公正の原則は、単にメディアが第三者に関する情報を扱う際の態度や姿勢だけに適用されるわけではない。メディア自身の報道の仕方についても当然当てはまる。報道上、重大な支障のない限り、取材の方法や情報の扱いに関して、必要があれば明らかにすべきだろう。競争紙の重要な報道を軽視、あるいは無視するような報道の仕方は、どう見ても、数百万部もの部数を誇る大新聞の行動としてはふさわしくない。競争紙の特ダネは特ダネとして率直に評価するほうが、よほどすがすがしく、好感が持てる。
もう一つ気になるのは、今回の記事に限らないが、相変わらず情報源の扱いがあいまい、ずさんなことである。「明らかになった」式の記事と同様、情報がどのような性格の情報源から提供されたものなのか、手がかりさえも示されていない記事があまりに多すぎる。特に政治家や政府、官庁を情報源とするニュースにそれが多い。
「政府は・・・する方針を固めた」というスタイルの記事はその典型といえる。官報の記事ならこれでもいい。しかし政府の立場を受け売りするようなこの記事のスタイルは、政府や政治家から一歩距離を置いて報道しなければならない、一般紙の記事にはなじまない。なのに、現実の報道に「官報型」の記事が溢れているのはなぜだろう。それほどに報道の現場が「官報型」報道に違和感なく安住し、同時に報道における情報源の扱いに無関心になっているからではなかろうか。
記事の中で情報源を可能な限り明示することは、読者に情報の価値を判断する手がかりを与えることになる。また、取材する側、される側により大きな責任感を持たせ、情報への信頼を高めることにもつながる。しかしメディアの側にいま、読者に情報の価値を判断する手がかりを提供しようという意識がどれほどあるだろう。おそらくは、「価値判断はメディアの仕事、読者は結果だけ知ればいい」というのが無意識の本音ではあるまいか。「由らしむべし、知らしむべからず」的な姿勢が透けて見える。
倫理綱領とメディア
日本新聞協会が先ごろ、新しい新聞倫理綱領を定めて公表した。一九四六年に制定され、その後五十年以上ほぼそのままだった倫理綱領をこの時期に改定したのには、それなりの理由があったのだろう。が、その意図はどうであれ、問題は新しい綱領が新聞、放送の行動規範としてどの程度、有効に機能するのかだろう。綱領の文言とメディアの実際の行動が大きくずれるようでは、立派な綱領を作ったことの意味がなくなってしまう。
新綱領の「独立と寛容」の項には「公正な言論のために独立を確保する」「あらゆる勢力からの干渉を排除するとともに、利用されないよう自戒しなければならない」との一節がある。しかし六月に表面化した、いわゆる「指南書」問題のその後のなりゆきを見ると、現在のメディアにこの綱領の文言を尊重する姿勢はまったくうかがえない。
「指南書」は記者の側が自ら進んで「利用される」ことを求めたもので、綱領を真っ向から踏みにじる内容のものだった。が、これを書いたと見られる記者が所属していた内閣記者会は問題の扱いを「各社の判断」に委ねて沈黙を守ったまま。「各社」も一部の新聞が散発的にこの問題を報じたものの、大部分は何事もなかったようにダンマリを続け、疑いをかけられた社は、「知らぬ存ぜぬ」を通して済ませている。
メディアの側は「喉もと過ぎれば」の思いで時間の経つのを待っているのかもしれない。あるいは、この問題自体、大した問題と思っていないのかもしれない。しかし読者、視聴者の目はメディアの内側の人たちが考える以上に厳しいことを軽く考えないほうがいい。今回の問題をめぐって、筆者がたまたま意見を聞く機会のあったごく普通の人たちは、メディアの対応の鈍さに驚く人たちと、どうせメディアはその程度のものと醒めた見方をする人たちの、二通りに分かれた。が、両者に共通しているのは、メディアに対する深い不信感だった。
信頼回復のために
新綱領はその前文で「読者との信頼関係をゆるぎないものにする」ことを目的の一つに掲げている。しかし最近のメディアの行動にはむしろ「信頼関係」をゆるがせるようなものが続いている。それはメディア自身がいま置かれている位置を、しっかり見極められないでいるからではないか。メディアが市民からどのように見られているのか、謙虚に見直す気持ちを失っているからではないか、と思う。
失われた、あるいは失われつつある信頼を簡単に取り戻すための特効薬はない。まず第三者の目で自分たちの仕事の現状を振り返り、問題点を洗い出すことから始めねばならない。そのうえで、日常の仕事の中でやるべきこと、できることをきちんとこなしていく以外に、有効な方法はない。抜かれたとき、抜かれた事実を率直に認めることも最初の一歩になるだろう。
メディアは政治家や役所、企業の不祥事が問題になるたびに責任の明確化や情報の公開、透明性の向上などを言い立てる。そうであれば「指南書」問題でも、同じ物差しを自分自身に当てて対処しなければならない。他人と自分に別々の物差しを当ててものを言うようでは、市民の信頼を回復することなど覚束ない。