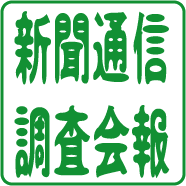 |
「メディアの資質」 2000年7月号 |
|
|
|
| なんとも腑に落ちない話である。内閣記者会に所属する記者のだれかが、「神の国」発言に関する森首相の釈明記者会見の前日、首相にメモを送ってあれこれ会見の要領を助言したらしい、という話である。『朝日新聞』(六月八日)の「天声人語」が取り上げているのを読んだあと、『週刊文春』(六月十五日号)の広告を見て、普段は買わない週刊誌をつい買ってしまった。 |
森首相へのメモ
ワープロで打たれたメモの中身は、首相が会見を無難に乗り切れるようこまごまと注意を与えたもので、予定外の言い回しはするな、質問ははぐらかせ、予定時間をオーバーするな、といったことまで記されているという。『週刊文春』は、メモの筆者がある「全国放送」の記者らしいということも伝えている。
事実だとすると、これは記者の最も基本的な職業倫理を踏み外した行為である。メディアに対する国民の信頼を根本から損ないかねない重大な背信行為でもある。この記者がそうと知りつつメモを書いたとすればその罪は重いし、それほどの意識もなく書いたとすれば、恐るべき退廃である。なにより、人間として心根の卑しさが情けない。
それにしても、この話には、腑に落ちない点がいくつかある。一つは、これが本当に記者の仕業なのか、という疑問。もしかしてメディアに対する信頼感を損なうことを狙っただれかの陰謀の可能性はないのか、との疑問さえ浮かんでくる。メモを記者室に落とすなど、その不用意さがわざとらしくも見える。
もう一つは、なぜ新聞やテレビがこの問題をニュースとして取り上げないのか、という点。『週刊文春』によると、メモを最初に拾った『西日本新聞』の記者は六月二日付の紙面でこのことを報じたという。しかし他の全国紙は、その後数日間の紙面を見た限りでは、先の「天声人語」と『毎日新聞』(七日付)が二段であっさり伝えたのを除いて、このことをニュースとして取り上げてはいない。(その後、『週刊朝日』六月二十三日号が『週刊文春』とほぼ同じ内容のことを伝えている)。ニュースとして価値を認めていないのか、それともメモの信憑性に何らかの疑問があるからなのか。メディア全体の信用に関わることだけに、新聞やテレビが沈黙を守っていることが、かえって不可解に思われる。
さらに、内閣記者会がこの問題をどう扱おうとしているのかもはっきりしない。記者会はこれまでもオフレコ破りやエンバーゴー破りなどを理由に、記者個人や社に除名や登院停止の処分をしたことがあるが、今回の問題はそれ以上に重大な問題をはらんでいるはず。『週刊朝日』によると、記者会は「各社ごとに対応することが妥当」として「"犯人"の追及はしない方針」という。うやむやにすれば、臭いものにフタをしたと批判されることになるかもしれない。
取材現場の体質
これで思い出されるのが、渡邊恒雄・読売新聞社長の回想録(『天運天職』)に描かれているエピソードの一つである。一九六〇年の安保闘争のさなか、当時、政治部記者だった渡邊氏が、重大事態に直面して混乱する岸政権の椎名官房長官に代わり政府声明を代筆した、という話。渡邊氏はこれを、いわば若き日の手柄話として紹介しているのだが、これが記者としての仕事の範囲を踏み外したものであることは、前沢猛氏が先に本会報「プレス・ウォッチ」(九九年十一月号)で厳しく批判している。当時はこうしたことが政治記者の「勲章」と考えられたのかもしれないが、いまはもはや通用しない時代錯誤、と筆者は考えていた。しかし今度のメモが記者会のメンバーによって書かれたものだとすると、渡邊氏的発想が現在の政治記者の間にもまだ生きているのか、という疑問も湧く。
外にいて限られた情報だけをもとに考えると、今回の出来事は「とんでもないこと」という受け止め方しかないのだが、もしかすると、政治取材の現場で働く記者たちにとっては、さほど意外なことではなかったのだろうか。倫理違反だの、心根が卑しいだのといった反応は、現場を知らない人間の甘っちょろい批判でしかないのだろうか。新聞やテレビがこの問題をニュースとして扱わないのは、要するに驚くようなことではなかったからなのだろうか。
仮にそうだとすると、問題はメモを書いた記者個人のモラルだけではなく、政治取材の現場全体のモラルに関わっているようにも思われる。こうしたメモを書く記者の存在をそれほど異としない空気が現場にあるとすれば、メディアの退廃は想像以上に深刻といわねばならない。
むろんこれは現場だけの問題ではない。ニュース報道に携わる組織や人間全体に関わる問題でもある。日本のメディア企業における教育はとかく、「記者教育」ではなく「社員教育」に陥る傾きがある。その結果、ジャーナリズムの普遍的な価値より、特定の企業の立場や利益を優先する「企業ジャーナリスト」がつくられ易い。メモを書いた記者は、そうした普遍的な価値基準を見失った「企業ジャーナリスト」だったのかもしれない。
癒着避けるのが鉄則
かつて一九八〇年の米大統領選挙で、共和党候補だったレーガン氏のテレビ討論の予行演習に、著名なコラムニストのジョージ・ウィルが招かれて立ち会ったことが、後に問題にされたことがあった。『ワシントン・ポスト』の政治記者デービッド・ブローダーは、ジャーナリストが政治家に助言すべきではないと言い、助言しながらその事実を隠してテレビ討論について論評するのは読者に対して不正直だ、とウィルを批判した。ジャーナリストは自分が書くものを通して助言すればいい、というのがブローダーの考え方である。
米国でも六〇年代のケネディの時代までは、大統領が親しい記者から非公式に意見を求め、参考にすることはあったとされている。しかし七〇年代以降はメディアと政府の間に不信感が強まり、政治家に接近しすぎることをむしろタブーと考える空気がメディアの側に強まった。今回のメモのようなものを仮にホワイトハウス担当の記者が大統領に渡したことが発覚すれば、その記者のジャーナリストとしての信用は完全に失われてしまう。
公正な政治報道をするには、取材対象である政治家との間に距離をおき、癒着(と見なされる恐れのあることも含め)を避けることが鉄則と、米国では考えられている。日本でも同じことが言えるだろう。むろん、きれいごとだけではすまないことも分かる。しかし、どんなに譲っても、今回のメモを書くような行為は、およそ記者の仕事とは最も遠く懸け離れたことと考えざるをえない。
情けない思い
今回の出来事について、読者、視聴者としての感想を述べるとすれば、こんなことを仕出かす記者の伝えるニュースを毎日、読まされあるいは視聴させられているのかという、情けない思いである。自分の仕事に関わることで、これほど明白な善悪の区別もできないような記者が伝えるニュースは、ご免こうむりたい気持ちである。そのニュースが国の中枢である首相官邸からのニュースとあれば、なおさらその思いは強い。
メモの筆者が心配した森首相の命運は、選挙の結果どうなるか、本稿執筆時(六月十三日)には予測できない。しかし政権の将来がどうなるにせよ、「神の国」発言はじめ、さまざまな失言や言い訳を繰り返して「首相の資質」を問題にされた森首相のことを、メディア側は笑ってはいられない。メモの筆者に「記者の資質」が欠けているのはいうまでもないが、こうした記者を生み出したメディアも、いまその「資質」を問われているといえるのではないか。#