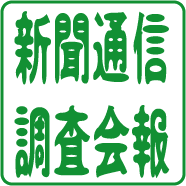 |
「提言報道」とニュースの中立性 2000年5月号 |
|
|
|
| やや旧聞に属することだが、二月二十七日の『読売新聞』(朝刊)は、石原・東京都知事が提案していた外形標準課税について「緊急提言特集」をでかでかと報じていた。一面トップには「外形課税は全国・全業種で」「薄く広く原則に二〇〇一年度実施を」と呼びかける「本社緊急提言」を掲載。二面には「税の基本に立ち返れ」という編集委員執筆の評論、そして一〇面と一一面のほとんどを使って「緊急提言」の内容を詳しく紹介する記事を掲げていた。 |
紙面の総動員も
提言の中身は、石原知事の提案を「問題が多い」と批判し、「全国同時・全業種を対象とする法人事業税の外形標準化を二〇〇一年度から実施するよう」主張、『読売新聞』として五項目の具体的な提案をしている。「提言」と銘打つとおり、普通のニュースを伝える記事のスタイルではない。「…すべきである」「…すべきでない」「…しなければならない」などの言葉が並んでいる。全文これ社説、といった趣である。
『読売』はこのところ、「提言」づいているような印象さえある。鳴り物入りで独自の「憲法改正試案」を発表したのが一九九四年、それ以来、何度か安全保障政策や行政改革問題など、折に触れて今回と同様の手法で「提言」を行っている。前後の社説やニュースの分析、解説などを見る限り、これらの問題に関しては、「提言」で打ち出された考え方が、一種の「社論」として新聞の報道の基調を形作っているように思われる。
新聞が社説で独自の主張や議論を展開するのは自由である。たとえそれが、重要な政治課題をめぐる特定の立場からの主張であっても、それが社説ないし論説として行われるものであれば問題はない。しかし「提言」となると、今回のように紙面を総動員して特定の立場に立った報道を推し進める形になり、明らかに社説で主張を展開するのとは違ってくる。
問題は、一般のニュースを伝える紙面が「提言」の方向に沿った情報だけで固められ、これに沿わない情報は排除される恐れがあることである。現に『読売』の紙面には、九四年の「提言」が打ち出した憲法改正を促す動きに比して、これに反対する動きについては、ごくわずかしか伝えられていない。この問題に関する解説や分析も、ほとんどが「提言」と同じ立場に立って行われている。
新聞の使命の一つは、多様、多彩な情報を伝え、さまざまな立場からの議論を戦わせる場を読者に提供することである。新聞が重要な問題に関して限られた情報や意見だけを伝えるようになれば、その使命を果たせなくなる。「提言」報道には新聞がそうした報道に陥る危うさをはらんでいるように思われる。
客観報道の原則破る
「提言」報道は、米国の主流のジャーナリズムでは、ある種のタブーとみなされている。客観報道を基本的な原則と考える立場からは、新聞側の主張を色濃く押し出す「提言」報道は明らかにその原則を踏みにじるものと映る。少なくとも建前としては、社説や評論の場以外で特定の主張や意見を紙面に展開することは、米国の新聞では禁じられている。
むろん「アドボカシー・ジャーナリズム」と呼ばれる「提言」報道を実際に行っている新聞もなくはない。『ビレッジ・ボイス』や『ローリング・ストーンズ』などがよく知られた例だが、この種の新聞の多くは、限られた地域や限られた読者層を対象にしたもので、いわゆる一般紙のなかにはあまり見当たらない。米国では一九六〇年代、公民権運動やベトナム戦争をめぐって社会が大きな混乱期にあったころ、特定の立場に立つ「提言」報道が盛んに行われたことがある。しかし「提言」報道は結局、その後も米国ジャーナリズムの大勢とはならなかった。
一九九〇年代には、いわゆる「シビック・ジャーナリズム」をめぐって「アドボカシー」の是非が議論されたことがある。「シビック・ジャーナリズム」は伝統的なニュース報道のあり方に疑問を呈し、ジャーナリストが第三者にととまることなく、主体的に問題解決の方法を提示するところまでコミットすべきだとの考え方に立つ、ジャーナリズム改革の実験と呼んでいい。地方紙や地域紙、地方の放送局で取り入れられているこの実験に対して、有力紙や有力テレビ局を中心とする主流派メディアは、これが「アドボカシー」だとして非難、批判を浴びせている。こうした手法では、ジャーナリストが問題解決の当事者になりかねず、いずれはジャーナリズムに対する読者、視聴者の信頼を失うことにつながる、との見方である。
「シビック・ジャーナリズム」の手法が即、「アドボカシー」につながると断じるには議論の余地があるが、仮にその危険があるとしても、これまでどおりの第三者的なニュース報道に満足できないメディアが出てきつつあることは無視できない。ただそうしたメディアはほとんどが地域社会との密着度が高い、小規模の地方紙や地域紙、地方の放送局である。有力メディアは、相変わらずニュース報道が「提言」報道に陥ることには、強く反対する姿勢を崩していない。
バランス欠く恐れも
『読売』が限られた発行部数の一地方紙なら、その「提言」報道もさほど問題にされないかもしれない。しかし一千万部を超える大新聞となれば、その「提言」がもつ意味も無視できない。なによりも、大部数を支える読者は、特定の考え方や立場を支持する人たちだけではあるまい。新聞はそうした読者に対して、社説や評論での主張とは別に、重要な問題に関して多様な情報、意見、議論を提供する使命を帯びているはずである。「提言」の方向に沿った情報や意見が紙面上で優先的に扱われるようでは、その使命は果たせなくなる。
「提言」報道はなにも新しい報道手法というわけではない。これまでも新聞が「暴力団追放」や「交通事故防止」といった問題でキャンペーンを張ったことは幾度もある。取り上げられたテーマは、異論の余地が少ない、分かりやすいものが多かった。『読売』の「提言」が注目されるのは、その内容が「憲法改正」や「安全保障政策」といった、国論を二分しかねない論議の多い問題についてあえて一方の立場を明確に主張していることである。
それはそれなりに、新聞社として勇気ある決断といえる。しかしそうした姿勢を明らかにすることで、紙面上で伝えられる関連したニュースの報道の中身に著しい影響があるとすれば、偏りのない情報提供を目指す新聞としては、読者の期待に沿えなくなる心配があるだろう。
もう一つ、この種の「提言」報道で気になるのは「提言」の方向が社内でどのような手続きを経て形成されているのか、という点である。開かれた、民主的な議論を通して結論が導かれたというのであればそれでいい。しかしその場合でも、異論は残るだろうし、その異論が自由に表明できる場が社内に確保されていなければならない。「提言」が一種の「社論」になり、それが現場の記者たちの考え方を縛るような効果を持っては、その新聞の紙面が翼賛化してしまう恐れもある。
世の中のさまざまな問題について、ただ批判するだけでなく前向きに提言をしていくことも、確かにメディアの責任である。議論を起こすことはメディアの重要な役割の一つである。しかしメディアは同時に、一方に偏らない、多様な情報や意見を伝える役割を担ってもいる。提言は社説のなかで十分行えるのではないか。社説から踏み出した「提言」報道は、ニュース報道にバランスを欠く事態を招く危険をはらんでいる。それは結局、新聞に対する読者の信頼を失う危険にもつながっている。#