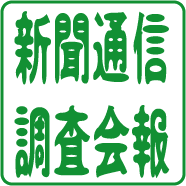 |
メディアと国益 2000年4月号
|
|
|
|
| クリフトン・ダニエル。元『ニューヨーク・タイムズ』編集主幹。二月二十一日死去。八十七歳。――日本の新聞にも載った小さな死亡記事を見て、三十四年前のほろ苦い記憶がよみがえってきた。 一九六六年六月、米ミネソタ州セントポールの大学に留学していた筆者は、この留学の終了式でダニエルの記念講演を聴いた。講演では、六一年のキューバ侵攻作戦に関する報道をめぐって、『ニューヨーク・タイムズ』とケネディ政権の間で交わされた交渉の内幕が、初めて当事者の口から明らかにされた。『タイムズ』は翌日の紙面を大きくさいて報道した。 現場で講演を聴いた筆者はしかし即座には、その内容がそれほど大きな衝撃的ニュースとは思わなかった。後でこの講演内容の持つ意味がわかってくるにつれ、自分のニュース感覚の鈍さに嫌気がさし、しばらく忸怩(じくじ)たる思いを引きずっていた。 |
報道控えた『タイムズ』
この時ダニエルが明らかにしたエピソードは、政府と新聞の関係を論じる書物のなかで必ずといっていいほど、引き合いに出されている。六一年四月、米CIA(中央情報局)に支援された亡命キューバ人によるキューバ侵攻作戦は完全に失敗に終わる。作戦に先立ち、『ニューヨーク・タイムズ』は作戦が差し迫っていることを報じようとする。が、ケネディ政権は『タイムズ』の幹部に対し報道を控えるよう要請、『タイムズ』側はこれを受けて入れて、記事を大幅にトーンダウンして小さく扱った。そうすることが「国益に沿う」と『タイムズ』の幹部は考えた。
ダニエルによると、作戦が失敗に終わったあとの六一年五月、ケネディは『タイムズ』の幹部に対し、一方で報道しようとした『タイムズ』の動きを批判しながら、他方で「事前に作戦のことをもっと詳しく報じていたら、政府がぶざまな事態に直面することはなかったかもしれない」と愚痴をこぼした、という。当初は『タイムズ』に圧力を加えて報道を控えさせておきながら、後で振り返ってみると、新聞が情報をすべて伝えていれば、侵攻作戦を見直すなり取りやめるなりできたかもしれないと思われてきた、というわけである。
大統領の言い分は、ずいぶん身勝手なご都合主義のように聞こえる。しかし、当初の判断より、長い目でみた後からの判断のほうがより「国益」にかなっていた、とするのは、正直な見方なのだろう。とすれば、初めに政府の要請をいれて報道を控えた『タイムズ』の側の判断が間違っていたということになる。ダニエルの講演には、あの時『タイムズ』が断固としてニュースを伝えるべきだった、という反省の念がにじんでいたように思われる。
当時『タイムズ』側でホワイトハウスとの交渉にあたり、報道を控える決定を下したのはワシントン支局長のジェームズ・レストンだった。後に書かれた回想録のなかで、レストンはその時の決定が間違いではなかった、と自分の立場を弁護している。しかしケネディその人の言葉を額面どおりに受け取るなら、『タイムズ』があえて事態の全容を報じることによって、キューバ侵攻作戦の失敗を回避できた可能性もあったと考えられる。事件から四十年近く経ったいま振り返っても、『タイムズ』が報道を差し控えたことは、長期的には米国の国益を損なったと見るのが、おそらく妥当な見方だろう。
当時、大統領補佐官をしていた歴史家のアーサー・シュレジンガー(ジュニア)は、後年の著書(『歴史のサイクル』)のなかで、政治家が口にする「国益」はしばしば自分の利益であったり、政権の利益であったりして、必ずしも本当の「国益」と一致するとは限らない、という意味のことを言っている。
政府に近いメディアの立場
メディアによる日々の報道活動で、日本の報道現場の記者たちが「国益」を意識することはそれほど頻繁にはないかもしれない。が、政治も経済もグローバルな関係が一段と密になっているいま、ニュースの中身に「国益」が関わってくることも増えている。外交や安全保障に関する問題は言うまでもなく、貿易や金融、財政問題のニュースもしばしば日本対外国の文脈で考えなければならなくなっている。
例えば在日米軍の経費分担削減に関する対米交渉、あるいは農産物輸入規制をめぐる世界貿易機関(WTO)との交渉など、日本のメディアはとかく日本政府に近い立場からの報道に傾きがちになる。「国益」を意識してのことか、日本政府から提供される情報に無意識的に依存する結果としてか、とにかく「日本」という色彩を帯びたニュースを伝えることにならざるを得ない。
日本のメディアであれば当然のこと、という考え方はあるだろう。メディアに国籍を捨てろ、というのは無理な相談かもしれない。しかし同時に、記者が「日本の立場」と信じて報じているものが、実は本当の「国益」とは食い違う可能性だってある、ということも考えておかなくてはならない。政府や政治家、あるいは官僚や大企業が「国益」「日本の立場」と称しているものが、単に政府や特定官庁、特定の政治家や企業の利益であって、必ずしも日本全体の利益を代表していないこともあり得る、ということである。
現場の記者や編集者に期待される役割は、「国益」のからむニュースについては、本当の「国益」と特定の役所や集団の利益をしっかり見極めて、読者や視聴者に違いを明確にすることだろう。
「わが国症候群」
どの国のメディアにしろ、それぞれの「国籍」から完全に自由であるわけではない(国際的通信社のような例外はいくつか考えられる)。日本のメディアに特別に「日本」の色彩が色濃くにじんでいるとも思えない。
が、かねてから気になっていることの一つに「わが国症候群」とでも呼べる問題がある。新聞や放送のニュース報道のなかに「わが国」という表現しばしば登場することである。どうやら役所用語としてしきりに使われる表現のようだが、これがニュース報道でもそのまま使われている。
米国の新聞は自国のことを「米国」と呼び、決して「わが国」とは表現しない。自国を客体化して見るためである。報道にあたるものが自国を「わが国」と呼んだとき、書き手自身が取材対象と一体化してしまい、自国を客観視できないような印象をあたえてしまう。日本の報道現場には、そうした違いを意識している様子がない。しかし「わが国」を当然のことのように使っていると、無意識のうちに日本と自分が一つになって、日本や「国益」を第三者として判断できなくなる心配がある。「日本」対「外国」の問題が「わが国」対「外国」の問題として意識されるとき、取材、報道にあたる記者の姿勢に「外国」に対する偏見や思い込みが生まれてこない保証はない。
メディアに「国益」を意識するなとはいえない。が、ここまでグローバル化が進んだ現在、「国益」より広い「地球益」「人類益」みたいなものを視野に入れた報道姿勢が求められているのではないか。そうした期待にこたえる努力が、これからのニュース報道をより公正で信頼できるものに変えていくことにつながるように思われる。
キューバ侵攻作戦をめぐる『タイムズ』報道のエピソードは、「国益」のからんだニュース報道についてメディアのとるべき姿勢、下すべき決断がどれほど難しいかをよく物語っている。いざというときに備えて、普段から「国益」や「地球益」に対処する考え方をしっかり定めておかねばならない。日本のメディアとしてはせめてその足がかりとして、まず「わが国症候群」を見直すべきではないかと考える。