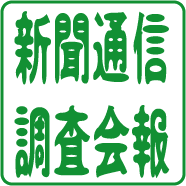 |
『LAタイムズ』の「不祥事」
2000年2月号
|
|
|
|
| 昨年十二月十九日付け『ロサンゼルス・タイムズ』の第一面に「読者へ」と題するキャスリン・ダウニング発行人とマイケル・パークス編集主幹連名の手紙が掲載された。十月に表面化した「不祥事」について、同紙幹部としての過ちを認め、信頼回復のために努力することを約束する内容のものだった。 『タイムズ』はその翌日、デービッド・ショウ記者の執筆した、「不祥事」に関する調査報告を十四㌻にわたる特別セクションを組んで掲載した。「不祥事」が起きた経緯を克明に記録したこの報告は、とりわけ発行人と編集主幹の責任を厳しく問う形になっている。『タイムズ』の親会社であるタイムズ・ミラー社のマーク・ウィルズ会長の経営方針も批判の俎上に上っている。 |
取材対象と利益山分け
「不祥事」というのは、『タイムズ』が十月十日に発行した付録の特集雑誌にからむものだ。ロサンゼルスの中心部に完成したばかりのスポーツ・センターを取り上げたこの特集号は百六十㌻を超え、『タイムズ』が得た広告収入は二百万㌦に達したという。
問題は、この収益の一部三十万㌦をスポーツ・センターに分配する約束が両者の間で事前に交わされていたこと、そしてそのことを『タイムズ』の編集局も、むろん読者も知らされていなかったことだ。取材対象との間で金銭上の取引をしてはならない、というのはジャーナリズム倫理の基本。『タイムズ』の経営者はあっさり、それをないがしろにしたわけだ。
別の新聞の報道でこの事実を知った『タイムズ』の記者、編集者の有志は十月下旬、ダウニング発行人に抗議し、真相究明とダウニング発行人の辞任を要求した。これに対しダウニング発行人は自分がジャーナリズムの倫理を「基本的に誤解していた」ことを認め、謝罪した。そしてなぜこうした問題が生じたのかを明らかにするため、社内のメディア担当のショウ記者に徹底的な調査を依頼した。その一ヵ月半に及ぶ調査の結果が、冒頭の記事である。
新聞が取材先との金銭上の取引の上にたってニュース報道にあたると、読者は当然、報道の内容が取引に影響されていると疑うだろう。新聞に対する信頼が根本の部分で揺らいでしまう。だからこそそうした取引をしてはならないし、それが疑われるような関係を持つことも避けねばならない。仮に取材対象との間に何らかの利害関係が生じた場合は、その事実を読者に明らかにしておくことが、公正な報道を保障する上での基本的なルールと、米国では考えられている。
今回の『タイムズ』の場合、営業部門が中心になってスポーツ・センターとの交渉を進め、最終的には九八年末に合意ができていたという。パークス編集主幹がこの合意の存在を知らされたのは九九年九月半ば、特集号の印刷が始まりかけたときだった。しかしそのときでも、彼が問題の深刻さを認識していれば、印刷を止めさせることもできたし、止められなくとも特集号の配布前に新聞に問題のありかを明らかにして読者に社としての立場を釈明することもできたはず、とショウ記者は編集主幹の責任を指摘している。
社の最高責任者としてのダウニング発行人の責任はさらに大きい。昨年六月に就任したばかりで、ジャーナリズムの経験のない経営者とはいいながら、それを理由に、新聞の信用を大きく傷つけたことの責任をまぬかれるわけにはいかない。
背景に利益優先体質
しかし今回の『タイムズ』の問題は、一部幹部の判断の誤りにもとづくというより、むしろここ数年『タイムズ』社のなかに強まりつつあった利益優先の思考や体質を背景にして起きた「不祥事」という性格が強いように思われる。この新聞にそうした体質を持ち込んだのは、自らも一時期発行人を務めたことのあるウィルズ会長だ。
ウィルズ氏は九五年に食品企業ゼネラル・ミルズからタイムズ・ミラー社に移ってきた人物で、『タイムズ』のほかタイムズ・ミラー社傘下の新聞の経営建て直しを強引に推し進めたことで知られるようになった。ウィルズ氏が初めの二年間で解雇した人員は『タイムズ』だけで七百人、ほかの新聞や関連企業を含めると三千人に上った。ウィルズ会長は、現在百万部強の『タイムズ』の発行部数を五十万部増やすと公言しているが、これは簡単に実現する見通しはない。
ウィルズ氏が『タイムズ』の経営に関わって最も熱心に推進したのは、編集と営業の間の「壁」をなくすことだった。これは、営業が編集に干渉してはならないというジャーナリズムの不文律に真っ向から挑戦する考え方だった。ウィルズ氏は両者の間の協力関係を強めることで、もっと効率的に収益のあげられる新聞づくりを目指したのである。
その方針に沿って『タイムズ』では、編集各部と営業・広告担当の間の調整役が任命され、営業・広告サイドの意見や希望が編集局の取材方針や企画記事に反映されるケースが出てきたという。こうした仕事のあり方に嫌気がさして『タイムズ』を辞めていった記者も少なくない。
しかし経営的な観点からすると、ウィルズ氏の手法は失敗したわけではなかった。『タイムズ』社の株価はウィルズ氏が移ってきた五年前と比較すると三倍近くに上がっている。ジャーナリズムの立場からは批判されたが、ほかの新聞社のなかにもウィルズ氏の手法を真似て「壁」を取り払う動きが広まっていた。
ジャーナリズムの衰退
今回の事件で当初、編集局側は問題の約束について、事前にまったく知らされていなかったと伝えられていた。しかしショウ記者の報告を読むと、約束は厳重な秘密にされていたわけではなく、編集部門の関係者が特集号企画の協議の席などで、それを事前に知りうる機会はあったようだ。ただそれがジャーナリズムの根幹に関わるような問題をはらんでいることを、あえて指摘するものがいなかったというのが、真相に近いように思われる。利益を優先させて「壁」を取り払う状況のなかで、パークス編集主幹をはじめとして、現場の記者たちのなかに、ジャーナリズムの価値を守ろうとする意思と感覚が薄れていたのではなかろうか。
十二月十九日付けの紙面で発行人と編集主幹は、『タイムズ』が信頼回復に向けて努力することを読者に約束している。ショウ記者の詳細な調査報告は、社幹部を含むすべての関係者による一切のチェックを受けずに公表されたという。その後始末のつけ方は「不祥事」に対処する『タイムズ』の真剣さの表れと言えるかもしれない。
しかし『タイムズ』にとって、ひいては米国の新聞界にとって問題が片付いたわけではない。これで『タイムズ』でも他の新聞でも、いったん崩した編集と営業の間の「壁」が再構築されるとは思えない。ジャーナリズムの質より利益を優先する新聞の体質が急に変わることはまずあるまい。米国のジャーナリズムの将来に対する懸念は当分消えそうにない。
翻って、日本の新聞には同様の問題がないと言い切れるだろうか。取材対象との間に一切の金銭的な利害関係は持たない、ニュース報道に際して広告主に一切影響されないといった原則を、新聞やテレビは忠実に守っているだろうか。そして仮に『タイムズ』と同じような問題が指摘されたとき、日本の新聞は『タイムズ』がしたように思い切った後始末をつけられるだろうか。
日本の新聞にも、ジャーナリズムとしての責任より利益の確保を優先する誘惑が確実に忍び寄ってきている。編集と営業の間の「壁」が健在かどうか、いま一度見直すことも無駄ではあるまい。